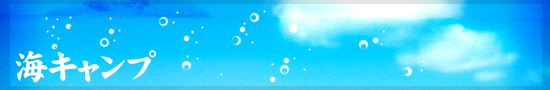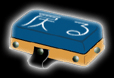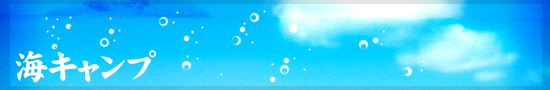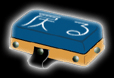●「海キャンプ」 オープニング

テントの設営も終わり、今は楽しくも大騒ぎな夕食の準備があちこちで行われている。大概、数名の学生達がグループを作り手分けして作業をしているのだが、普段から料理に慣れ親しんでいる者もいれば包丁を持った事もない者もいる。どこのグループでも何かしらのハプニングが起こり、派手な喚声や怒号、賞賛、感嘆の声があがっていた。
このグループではオーソドックスにカレーライスを作ろうとしている。キャンプでは最も定番で基本的なメニューだ。手順が簡単だし失敗も少ない。しかし、各自がそれぞれ具材を一つずつ持ち寄り、オリジナリティ溢れるカレーライスを目指しているので、完成品の出来は今ひとつアブナイ感じがその製作工程からも明らかにわかる。
そんな賑やかな炊事場からある光が見えた。日の落ちた暗い海の上を漂う無数の小さな光の数々だ。始めは気のせいかと思った者も、まるで初夏の清いせせらぎに群れ集う螢が見せる淡い光の様に踊る様子にただ声もなく、目を離す事も出来ず立ち尽くす。光達は群舞の様に海の上を無秩序に旋回すると、やがて一つに集まって海に飛び込むように消えた。辺りはまたなんの変哲もない夏の光景となった。
夢を見た様だった。カレーライス作りは中断してしまっている。
「見たのかな?」
それは繭神・陽一郎の声だった。いつ近寄ってきていたのか、生徒会長の姿がそこにあった。その眼差しは先ほどまで光が揺れていた場所をまだ見つめている。陽一郎が消えてしまった光の事を言っているのは明白だ。
「あれがなんだったのか、もしわかったら教えてくれないか?」
それだけいうと、陽一郎は軽い砂の音を残して立ち去っていった。
海に浮かぶ螢の様な光の群れ、興味がないと言ったら嘘になると思った。
●ライターより
・カレーライスの具を1つ書いてください。
・光の正体に対する予想を書いてください。口外するかしないかも教えてください。
・どうやって調査するか具体的な行動を書いてください。
・調査後、陽一郎に協力的か非協力的かを教えてください。
|
|