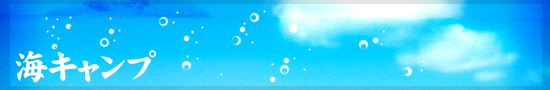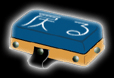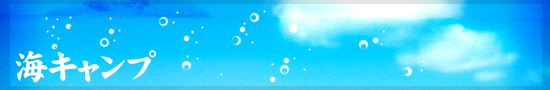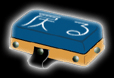●「海キャンプ」 オープニング

照りつける陽差し、息を呑むほどの真っ赤な落日のあとには、やわらかな宵闇が、海辺をしっとりと包み込む。
海キャンプの一日は喧騒とともに過ぎていった。
水平線の彼方には漆黒の夜のとばりが降り、決して都会では見られない、驚くほどの星々がまたたきはじめる。
そして――
キャンプファイヤーを囲む歌、夜が更けてもなお騒ぎたりない男子学生たちの声、女の子たちのひそやかなおしゃべりと、それに混じるときおりの嬌声も、しだいに遠のいてゆき……、生徒たちがみな寝静まった頃のことである。
ただ波の音だけを残して静まりかえる海辺の、砂を踏むかすかな足音。
「誰だ?」
突き刺さるような誰何の声が発せられた。そして、闇に慣れた目を射抜く懐中電灯の光――。
「……きみはたしか――……。どうしたんだ、こんな時間に」
それは、繭神陽一郎だった。
生徒会長は怪訝な顔で問いただしてきたが、よく考えれば、そういう陽一郎自身、なぜこんな真夜中に海辺を歩いているのだろうか。
「やれやれ、困ったもんだな。今夜は……他にも眠れない連中がいるらしい」
●ライターより
海キャンプの夜、あなたはなんらかの理由で眠らずに海辺を歩いています。そこで、繭神陽一郎、または他の学生たちと出会うのですが……。
プレイングでは、あなたが「夜に出歩く理由」と、誰かに出会ってしまった時の行動を教えてください(おまかせでも結構です)。
※「海キャンプ(日常)」ですが、多少、真相にかかわる部分をほのめかす可能性があります。
|
|