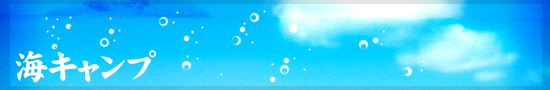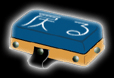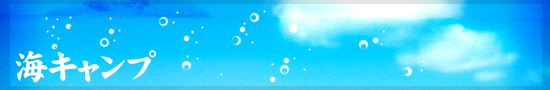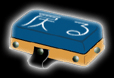●「海キャンプ」 オープニング

普段は神聖都学園で勉強して部活動がんばって……オトナは口を揃えて『高校生の時はよかったな〜』とか言うけど、実際にやってる方はそうじゃなかったりする。勉強でも進学とか夢とか、部活でもインターハイとか全国大会を目標にしたりするとそれしか考えられなくなるし、いくら若くたって余裕なんかなくなっちゃうわけ。それが高校生ってもん。そりゃ世間に揉まれてるオトナが抱えてる苦しみとか悲しみとか、そんなんよりかは小さいかもしれない。けど、俺たちにはその大きさで十分。それだけでも一日中悩んだりすることだってあるんだからさ。
小さい頃、合宿とかの学校のイベントではすごく素直になれた気がする。今よりももっと子どもだった時、あの暗闇の中で友達と呼べるみんなにいろんなこと相談しなかった? 学校の先生の悪口とか家のこととか……好きな人のこととか。自分から相談はしなくても、相手の相談を聞いた記憶はない?
今度の海キャンプの夜も、みんなきっとそんなことを思い出して相談し合うのかな。きっと星が煌く夜はみんな素直になれると思う。テントの中でも外でもいいから、なんとなくオトナになる前にちょっとスッキリしてみない? 知らない人との出会いとか、知ってる人の意外な一面が見えたりして面白いかもね。こんなにきれいな夜空だからさ、ほんのちょっと素直になろうよ。ね?
●ライターより
皆さんこんにちわ、市川 智彦です。
幻影学園奇譚ダブルノベル、海キャンプということでこういうネタにしてみました。こういう学校のイベントで真っ先に思い出したのがこれだったので、素直にそれを形にしてみました。こういう思い出、皆さんにはありませんか?
今回はお友達との交流やNPCとの会話などに重点を置いたオープニングになっています。お友達同士で参加してプレイングをまとめて下さいましたら、それに沿った形で書かせて頂きます。もちろんおひとりで参加されても、誰かと出会えるようにしますのでご安心を(笑)。皆さんのプレイングの内容を読んで、個別で反映するか全体で活かすかなどを考えさせていただきます。どの場合においても、全体・個別ノベルで他のキャラクターさんと絡む可能性がありますのでその辺はご了承下さい。
なお登場可能なNPCに関しては、幻影学園奇譚特設ページにあります「神聖都学園の有名人」をご参照下さい。この中に登場するNPCなら描写可能です。
幻影学園奇譚に参加されているキャラクターの意外な一面を少しでも引き出せたらと思い、今回のオープニングを作りました。素敵なロマンスやモノローグを楽しみたいキャラクターさんの参加をお待ちしています!
|
|