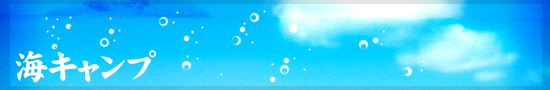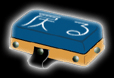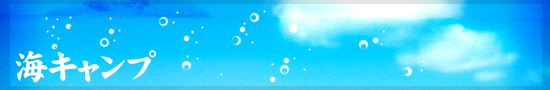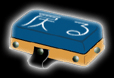●「海キャンプ」 オープニング

もう、傾いてきた太陽の日差しが、砂浜の透明な砂粒に斜めに降りてきていて、その弱まった光波の僅かな信号をキャッチした砂粒たちは、キラキラと、新たな信号を誰かに向けて発信している。一方でうねる水面に落ちた光は、反射と屈折を選択し、あるいは深い底面へ向かって四散する。
目を瞑れば、もうイメージを描けないし、見つめていても、同じ場面は二度と戻らない。人の位置や、波打ち際の湿った面積。エッジにオレンジ色を閉じ込めたガラスの小瓶。
押し寄せる波と言ったら、貝殻の屍骸や、海藻の切れ端、誰かの永久に届かない恋文など、気の抜けた物しか運んでこない。
次第に聞こえてくる騒々しい作業音。少数の生徒は夕飯の支度に取りかかっているようだ。コンクリートブロックの突貫工事で竃を作り炊飯を行うグループと、鉄板にガスバーナを用意してバーベキューの準備をしているグループと、大きく色分けされているようにも伺える。
空にはいつの間にか月がでていて、しかしまだそれほど暗くは無い。半数の人間はまだ浜辺で体力の消耗に勤しんでいる。
脚が痺れてきたので、鍵屋智子は背後の砂を払って立ち上がった。ただ立ち止まっていても気味が悪いので、貝殻の欠片の無い、安全なルートを選んで浜辺を少し歩く事にした。水辺まではまだ遠い距離だった。キャンプをしている広場から海辺までは、緩やかに下る放物線を描いている。彼女は海辺と平行して移動していた。進行方向の少し遠い所に、岩石の高く隆起した場所が見える。そこで何人かが今でも遊んでいるのが見えた。多分4人。いや、5人? 現在目視できるのは4人だが、そのいずれもが同一の方向へ反応を示している。そちらの方向(つまり、彼らの見ている方向)は、この位置からは岩陰になって確認できない。
一目、水面の辺りをあても無く伺った時、二人の人物に気がついた。浜辺に半身を起こしている人物と、もう一人は……生徒会長の、何と言ったか。とにかく、その二人だ。生徒会長は彼を見下ろしながら何か催促している様子だった。一瞬だけれど、何かを手渡すのが確認できた。これでも目は良い方だ。
鈍く光る物体のようにも見える。あるいは、水晶か、それに相当する輝度を有する個体。それが一瞬のうちに取引されていた。一見すると不気味でしかない。「その石綺麗だね」なんて空前絶後の会話が繰り広げられていたのだろうか。その仮説を破棄するとしたら、彼の規則に反する行為による接収なのか。だが、いずれも不自然極まりない。
鍵屋はルートの確認を諦めて、斜面に対して垂直に浜を降りた。夕暮れの色で分からなかったけれど、声をかけられていた側は髪を茶色に染めていた。近くまで寄って、それがようやく判明した。一応、姿は記憶しているけれど、名前はインプットしていない。静かに背後まで接近する。
「ごめんなさい。差し出がましいようだけど、彼と何の交渉をしていたのかしら?」
「は?」男が振り返る。上体を反らして、辛そうな体勢だ。
「もう一度言う?」鍵屋は両手を両腕を抱きかかえる様に腕を組んだ。
「な、何にもしてねえっての。誰だよ、あんた」彼はくるりと鍵屋に向かって居ずまいを直した。
「事を有利に進めたいのなら、相手に譲歩することが必要」
「意味が……、日本語で喋れっての!」
「ねえ、草間くん。私は貴方が生徒会長に渡していた物に興味があるだけ。教えてくれない?」
「何で、俺の名前知ってん……」
「ご丁寧に、背中のシャツのタグに、名前が書いてあったわよ」
「あっ! くそ、誰だ、あんのババァ、勝手に!」草間は上半身を捻ってその位置を調べようとしている。シャツを引っ張っているが、脱がなければ見える訳が無い。
「ご親切な両親ですこと。それより、どうなの?」
「知らねえよ。俺が石みたいなのを拾ったら、なんか、くれって言ってきて。そんでなんか、そこの辺に結構あるらしいってよ」
「……そう」
そう言うと鍵屋は短い距離を小走りに進んだ。そして、急にかがみ込むと思うと、顔だけ反転させて彼にきいた。
「もしかしてこれのこと?」右手には先ほどの小石がある。透明度が高く、何かの結晶体だろうと鍵屋は予測する。
「ああ、多分な」
「目、悪いの?」
「わかった。それだよ。それ!」
彼女は片目を閉じて、左手を真っ直ぐ伸ばし、海の方へ身体を向けた。左手の人差し指と親指を伸ばし、Lの字を作っている。そうやって、何かを望遠しているようだ。
「私は何光年も先が見える……」
「んなわけないじゃん」
小声で呟く草間の微かな抵抗に、鍵屋はまるで死んだ子犬を慈しむような目で彼を見た。
「貴方って、本当に哀れね」
「放っとけ!」
その時、それほど遠く無い、二人より少し手前の方で数人のヒステリックな会話が聞こえてきた。
「あれ、なんだ?」草間もそれに気がつき、脚の砂を払うと立ち上がった。
「生徒会長ね。君、名前知ってる?」
「繭神だろ? おいおい、生徒会長の名前くらい、っておい」
鍵屋はすでにそちらへ歩き始めている。やはり貝殻が足下で痛かったけれど、短距離なので我慢する事にした。草間もその背後を追ってきている。足音でそれがわかった。
「どうしたの? 騒々しいわね」鍵屋は興奮気味に話している生徒に目をやる。二人の女子だった。
「ああ、どうやら所定の場所以外で調理しているグループがあるらしくてね」繭神は両手の掌を上に挙げるジェスチャを見せた。いよいよ疲労してきた、という素振りだ。
「あるらしい、じゃなくて、あっちの岩場の方へ行くのをちゃんと見ました!」
激しく声を浴びせている方の女子は、水着にTシャツを着ていて、右手には黄色のメガホンを持っている。時々、そのメガホンを左手にポンポンと打ち付けていて、それが何となく鬱陶しい。
「ああ、貴女、風紀の方?」
「あなたこそ誰よ?」
「その質問には飽きたわ。繭神くん、私たちが見てこようか。ああ、勘違いしないで。どうせ私たちは食事の準備とかには無縁だし、貴方たちと言えば他の雑務に忙しいのでしょう? 物事を大きくしないためにも、あるいは効率の問題ね。私個人の嗜好や好意とは違うわよ。そう、ボランティアかしらね。これで今までの欠席日数を多めに見積もってくれるかしら?」
「なんっで、俺……」
「悪い。助かるよ。では、わたしは生徒会本部のテントにいるから、結果を後ほど報告してくれないか」
鍵屋は無言で頷く。視線は岩場の方角へ向かっている。その崖の上では、海猫の一家がぐるぐると旋回していて、時々遠くの風が運んでくる、ニャアニャア、という鳴き声が耳に残る。
「さ、行くわよ」
「マジ、かよ」
●ライターより
さて、プレイヤーは調理器具を持って岩場へ向かった失踪グループになってもらいます(プレイヤの参加人数が少なくても、物語に支障はございません)。内容は単純なエクスプローラ(探索)ノベルになります。ただし、要素(ジャンル)としてはオカルトSFホラーとなりますので、予めご了承ください。
物語のパートとして、「洞窟の探索」「未知の生物との遭遇」「光る小石の究明」と章がわかれております。比較的ボリュームのあるノベルとなります。
また、物語に入れて欲しいパートなど、ご希望があれば意見を反映させて盛り込ませたいと思っています。どうぞ、お気兼ねなくお申し付けください。
では、夏の良い日を。
|
|