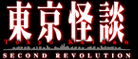 |
|
|
|
||
|
|
調査コードネーム:砂の満ち引き 執筆ライター :碧川桜 【オープニング】 【 共通ノベル 】 【 個別ノベル 】 |
|
|
|
||
|
|
||
|
|
 【オープニング】
【オープニング】温泉の種類は数多くあれど、誰しも一度は砂蒸し温泉なるものの名前を聞いた事があるだろう。 砂蒸し温泉とは、湯に浸かるのではなく、温泉で暖められた砂に身体を埋める入浴法である。一般的に、普通の温泉の数倍の効果があるとされている。血液の循環促進による老廃物の排出や炎症性・発痛性物質の洗い出し、十分な酸素、栄養の供給がその効果をもたらすらしい。最近では、ペットの為の砂蒸し温泉場もあるそうだ。 「砂と一口に言ってもいろいろある事は知ってるかしら?石を砕いて作られた砂は角が尖っているの。川底から揚げられた天然の川砂は、硬く、形は丸みを帯びているから、コンクリの骨材にも最適だし砂場の砂にもいいわね。海砂は塩分を含んでいるし、山陸砂は強度に欠けるから、川砂程には骨材には向かないわ。…あなたのお好みの砂は、どんなのかしらね?」 ………え。 「ふふ…何を不思議そうな顔をしているのかしら。ここは高峰温泉よ。ただの砂蒸し温泉である訳がないでしょう?」 ゆったりと、優美で官能的なラインを描く足を組み替えて、沙耶が口許で笑った。 「ここの砂蒸し温泉の砂は、浸かる人に合わせていろいろとその色や質を変えるわ。温泉の心地好さについうとうとしてしまう人も多いけど、それは要注意よ。だってここの砂には、蟻地獄が住むっていうもっぱらの噂なのよ。…そう、人の夢を食らうと言う蟻地獄が」 高峰温泉の砂蒸し温泉は、身体の老廃物だけでなく、浸かった人の夢や想いをも押し出すと言う。それは、その人がそうありたいと願う未来への希望と言う意味での夢であったり、普通に睡眠中に脳で感じる夢であったり。或いは、遠方の人が強く願う生き霊の類いであったりといろいろであるが、いずれにしても共通するのは、ここで見る夢の中では、それが『現実』であると言う事。 「気をつけなさいね。夢の中で死んでも、いつもなら死にはしないけど、ここでは本当に死んでしまうわよ」 あ、それと、と沙耶が思い出したように言う。楽しげに、指先で自分の頬を突きながら微笑みを浮べた。 「砂は例え混ざり合っても、その粒子が本当に溶け合ってしまう訳じゃないわよね?それと一緒。ここでは他人の夢と自分の夢が混ざり合ってしまう事も多いのよ。しかも、ちゃんとそれぞれ自己主張するから気をつける事ね。白と黒が混ざり合えば灰色になるけれど、ここでは白は白のままで黒は黒のまま。自分の夢が平和なものであっても、混ざった他人の夢が暴力と嘆きに満ちていたら、死ぬのはその夢の持ち主ではなく、あなたになる可能性もあるのよ」 「え、特殊能力?そうね、夢が『現実』になるぐらいですもの、夢の中でも各自の能力は変わらず使えるかもしれないし使えないかもしれないし。普段は無い能力が、この場限りで使えたり、或いはいっそ全く使えなくなって、無能になるかもしれないわね」 とにかく、無事に帰る為には、自分の夢がどれであるかをしっかりと把握し、帰る道を模索する事。一人で意地を張らずに、人と協力し合う事も時には有効ね。 「でも、中には反発する事で帰る道が見つかる事もあるから、その辺りは臨機応変に対処しなさいな。目覚める事が最短の逃げ道ではあるけれど、それだけが手段とは限らないわよ」 しかしそれにしても、砂蒸し温泉と言うのは一般的に浜辺にあるものだと思うが。ここの砂を暖めている熱源は、本当に温泉の湯なのであろうか。 「案外、地獄の業火かもしれないわね?」 冗談よ、と笑う沙耶の微笑みを見ていると、満更嘘でもないような気がして来た。 【ライターより】 ☆各自の特殊能力について 特に指定がなければ、PC設定に従ってこちらで描写させて頂きますのでご了承ください。貴PCにこの場限定の能力を付与する場合はその旨お書き添えください。なお、無能設定はご指定がない限り、こちらから設定する事はありません。無能設定にすると、何か特別な事があるかも無いかも(どっち) |
|
|
|
||
|
|
||
|
|
【共通ノベル】 【side-A】 朝目覚めたら世界は一新していた、なんてのはファンタジーやSFの序盤としてはよくある話ではあったけれど。 まさか、砂蒸し温泉でほっと一息ついていたら、その間に世界が変わっていたなんて、そんな話、聞いた事が無い。 「…あーあ、わたしはここに癒されに来たって言うのに、なんでこう言う目に遭うのかしらねー?」 イヴ・ソマリアはそんな風にぼやきつつ、白い靄の懸かった細い道を歩いている。行こうとしている先は果てしなく遠く、その先は靄に霞んで様として知れない。また、今まで自分が歩いてきた道を振り返ってみれば、それもまた同じく、果てしない距離がイヴの後に残り、自分がやってきた筈の先も、白く靄に融けこんでいるのだった。 「まぁいいわ。そのうち何とかなるでしょ……あら?」 ふと、イヴがその歩みを止める。その視線の先には、相変わらず細く長い道が続いているのだが、その道の端にひとりの少年が足を投げ出して座り込み、背を丸めて項垂れていたのだ。 「ねぇ、起きて。あなた、大丈夫?」 「……う、−ん…」 跪いたイヴが少年の肩を軽く揺さぶると、少年は微かな呻き声を上げて目を覚ました。呻いたのは、深い眠りから覚める時の意識の軋み故だったらしく、怪我のようなものもなく、気分が悪そうな様子もない。 「寝てただけかしら?あなたももしかして、どこかからこの夢の世界に落ち込んじゃったのかしら?」 「どこか、って…高峰温泉の砂蒸し風呂に、一緒に居たじゃありませんか」 「ええ?嘘ー?!……って、あ、そうだわ。七重クンじゃないの」 少年の赤い瞳と静かな声で思い出したか、イヴが小さく苦笑いをした。忘れられていた事を特に指摘する訳でもなく、尾神・七重はそうです、と頷く。イヴは顔の前で手の平をぱちんと合わせ、片目を瞑る。 「ごめんなさいね、だって髪の色が違ったんですもの、だからすぐには分からなかったのよ」 「………え?」 イヴの言葉に、七重は自分の髪を片手で触ってみる。勿論、手の平に視覚がある訳ではないので、それで見える訳ではない。イヴが持っていた、小さな手鏡を借りて見てみると、そこに映ったのはいつもの鈍く光を反射する銀色の髪ではなく、カラスの濡れ羽色と評されるような、艶めいた真っ黒の髪だったのだ。 「…僕の髪、……」 「ね?でも、髪の色一つで随分印象って変わるものね…何故だか分からないけど、七重クン、顔色も良さそうだし、凄く元気に見えるわ?」 「そう言うあなたは、また派手に可愛い格好をされてますね…」 今度はイヴが「え?」と驚く番だ。今まで自分の格好には然程注意を払っていなかったが、そう言われて改めて己の服装を見下ろしてみると、砂蒸し温泉に入った時の浴衣姿ではなく、白とピンクと水色の、フリルつきの可愛いミニワンピースを着ていたのだ。 「それは、イヴさんのステージ衣装なのですか?」 「そうだけど…でもこれは、この世界での衣装ではないわ……」 呆然と呟くイヴの脳裏に、さっきまで見ていた夢の一つが甦る。この衣装を着て華やかな舞台に立っていた頃の自分、『今』でも『此処』でもない、異世界での自分の記憶が走馬灯のように駆け抜けていったのだ。少し寂しげな表情のイヴを、座り込んだままだった七重が立ち上がり、彼女に向かって片手を差し出した。 「…七重クン?」 「ここでこのまま座っていても何も変わらないと思います。行きませんか?」 どこかに。今の段階では、目的も目標も何も無いのだから、その表現が一番的確であった。にこりと笑って、イヴは差し出された七重の手を取る。その手に助けられて立ち上がり、手でスカートの埃を払う。 「そうね、行きましょう。考えてるだけじゃ、分からない事もあるものね?」 「…とは言え、どっちに行けばいいのかしらね」 イヴが道の真ん中で立ち、両の拳を細腰に宛がって唇を尖らせる。その瞳は、自分が今まで向かおうとしていた道の先と、これまでに歩いてきた道の先を代わる代わる見つめている。 「右と左、どっちも、その先に何があるかはさっぱり分かりませんね…予想も付きませんし、どっちに行っても同じじゃないですか?」 イヴと向かい合う姿勢で、七重も同じように二つの道の先を遠く眺めて答える。内心、自分にしては珍しい、行き当たりばったり的なものの考え方に首を捻りつつも、それは決して嫌な感じではなかった。そんな七重の思いに気付いているのかいないのか、何でも無い事のように、そうね、とイヴが小さく頷いた。 「だったら、コッチに行きましょ。どっちに行っても同じだとは思うけど、それでも今まで自分が歩いてきた道を逆戻りするのは、なんだかつまんないんですもの」 「そうですね、じゃあこちらの先を目指して歩いてみましょう。…あ、先にお断りしておきますが、僕は体力には自信がありませんので…ご迷惑をお掛けするかもしれませんが…」 「構わないわよ、困った時はお互い様でしょ?急いでいる訳じゃないもの、ゆっくり休み休み行けば済む話よ。疲れたらすぐに言ってね?」 尤も、急いでても行き先が分からないんじゃ、急ぎようも無いしね。そう付け足して笑うイヴに釣られたよう、七重も口元で笑った。 そんな二人が肩を並べて歩き出すと、それまで一人が歩けるだけの幅しかなかった細い道が、不思議な事にいつの間にか、二人が並んで歩けるだけの広さになっていたのだ。その事に気付いて、七重が隣のイヴの顔を見る。 「どうやら、ここは固定された世界ではないようですね…何かの影響によって、いろいろと変化するみたいです」 「ここは、本当に夢の世界のようだもの。夢って、自分の都合のいいように変えたりできる時があるじゃない?それと同じようなものなのかもね」 「願望…と言うか希望…と言うか、ですね。案外、眠っている時に見る夢も将来や未来に馳せる夢も、同じようなものなのかもしれませんね」 「そうね…自分の好きなように出来たら、そりゃ嬉しいかもしれないけど…でも、それって何か、安直って言うか…そう言えば、七重クン。率直な意見を言ってもいいかしら?」 不意にイヴがそんな事を言い出す。何の事か分からない七重は、取り敢えずいいですよ、と頷き掛けた。 「ん、ありがと。あのね、今の七重クン…なんて言うのかしら…最初に砂蒸し風呂で会った時より、随分ハッキリして見えるのよね。ヘンな表現だけど、前はもっと儚げって言うか、浮世離れしてたって言うか…でも今は」 「どこにでも居る、普通の中学生…とか?」 イヴの言葉を七重が引き継ぎ、それに同意してイヴが頷く。 「…そう言えば、さっきから結構な距離を歩いていますけど…以前なら、もう今頃は息を切らしていたような気がするんです。お話しながらだから、気も紛れて疲れを感じ難くなっている、とも考えられますけど、…どっちかと言うと、夢の中なので体力も普通の中学生並みになっている、そんな感じがします」 言葉どおり、七重は息を切らすどころか、まだまだどこまでも歩けそうなぐらい歩調も軽く、身体も楽であった。告げる言葉もしっかりと、いつもの倍以上の言葉数を喋り続けてもいる。 「これが僕の夢…なんでしょうね……」 イヴに聞かせると言うよりは、独り言のような七重の呟きに、イヴは何も答えずにただ隣に居る少年を見た。すると、前方をぼんやりと臨んでいた七重の瞳が驚いたように見開かれる。歩みが止まり、緊張したようにきゅっと下唇を噛み締めた。 「…? どうしたの、七重クン……あ、……」 イヴも釣られて、二人が向かおうとしていた道の先へと視線を移す。そしてイヴもまた同じように、驚いてその緑の瞳を見開いた。 道の先、白く煙った靄の中から、何かが現れようとしている。それは、この世のものではない異形。その時、二人の脳裏に、沙耶の声が甦った。 この夢の中では、そこで起こった事が現実となって影響を及ぼす事がある 二人は、来たるべき衝撃に備え、その場で身構えた。 【side-B】 どさり、と生々しい音がして、肉の塊になったそれが倒れ込む。生臭く飛び散る血飛沫も切れ切れになった肉片も、相当なリアリティを持っている事から、この『夢』の本来の持ち主には、こんな異形とかなり深く触れ合った経験があるのだろう。それが、その本人の意によるものか、そうでないのかまでは分からないが。 「案外、あっさり仕留められたものですね。由代さんのお陰でしょうか」 原形を留めない異形の傍らで真っ直ぐに立つモーリス・ラジアルが、たった今、使用したばかりのメスを指先で閃かせ、自分の懐にしまう。足元に転がった肉片を踏まないように気を付けながら、邪魔そうに魔導着の裾を捌いている城ヶ崎・由代の元へと近付いた。 「それはお互い様でしょう。僕一人では、ここまで素早く対処できなかったかもしれない。なにしろ、ついさっきまで、柄にも無く少々動揺していたのでね」 と、動揺なんて言葉とは無縁な様子で由代は静かに笑った。 「では、私達二人のお陰と言う事で…ひとつお尋ねしても宜しいですか?」 モーリスの言葉に、由代は無言で視線を向ける事で、了解の意を伝える。承諾を得たモーリスは、視線を足元に転がった異形の末路に一度だけ向け、そしてまた由代へと戻す。 「…これらは、由代さんの『夢』、ですか?」 そう問われ、由代は改めて足元の肉塊を見下ろす。暫しその塊を眺めた後で、ゆっくりと首を左右に振った。 「いや、見覚えはないな。…ない訳ではないか。知識としてはあるが、実際に遭遇した事は無い、と言うべきかな?」 「と、言う事は、これらは魔界の住人なんでしょうか」 あまりそちらの方面には詳しくないもので、と、自分で言う程無知な訳では無さそうな表情でモーリスが付け足した。 「その問いは、正解とも言えるし、そうでないとも言える。異世界の全てが魔界であると位置づければ、キミの言葉は正しいが、その一括りはあまりに大雑把過ぎやしないかい?」 「魔界の一言では定義付けられない異世界もある、と言う事でしょうか」 モーリスの返答に、由代は黙って頷いた。 「俗に言うパラレル・ワールドと言うものも異世界の一部なら、僕達が生活しているこの世界と同じ異世界もどこかに存在しているのだろう。そこを、魔界と呼んでしまっては、僕達の世界も魔界と同じだとも言えてしまうからね」 「ですが実際、今のこの世界であっても、そこに渦巻く人の悪意や憎悪、憐憫や恐怖。それらは目に見えないだけで、実情は魔界とほぼ変わらぬグロテスクさを秘めているのではないのですか?」 と、答えたのはモーリスではない。いつの間に彼らの元に近付いてきていたのか、或いは空間転移のように、瞬間的に姿を現したのか。それは分からないが、ともかく、由代とモーリスの傍らに、三下が立っていたのだ。 「三下君。いつの間に」 「いつの間に、と言われましても、私も気が付いたら、ここにいましたね。血の匂いが私を引き寄せたとでも言うのでしょうか…しかし、私は現実の血生臭さには興味が沸かないのですがねぇ…」 「…三下君……では、ありませんね?」 緩く首を傾げて疑わしそうな目をするモーリスに三下は、三下ではあり得ないような嗤い方で口元を歪めた。 「混ざり合っても溶け合う事は無く、ただ渦巻くのみのここの砂。私と同じで実に興味深い。だが、私の姿そのままで砂蒸し温泉に浸かっては、本当に砂の一部と化してしまいかねないので、三下サンの姿を借りたのですよ」 そう言って口端を持ち上げるその表情は、元々の無我・司録のものと寸分たりとも違わなかった。 三下の姿形はそのままで、ただ喋り口調と自嘲的な嗤い方が違うだけで、考えてみれば似合わなさ過ぎる可笑しな取り合わせだが、それでもこうして実際に目の前に存在されると、三下の平和そうな容貌も、案外引き締まって見えるから不思議なものだ。 「もしかして、こいつらはキミの『夢』かい?」 次第に融け始める、異形の残骸を靴先で突付きながら由代がそう尋ねると、司録は、それに一瞥を与えた後、首を左右に振って否定を示す。 「元より、私自身には『夢』等と言うものは存在しません。あるとすれば、以前に私が人様から頂戴した夢の欠片…ですが、このようなものが登場するものは記憶にありませんな」 「由代さんのでも私のでもなく、司録さんのでもない。では、ここにいる三人以外で、この世界に落ちてきてしまった他の人がいるかもしれませんね」 「そう言う事だろうな。他に何人落ちてきているかは分からないが、こんな『夢』を持った人ばかりでない事を祈るよ。こんなのは僕ひとりで充分だ」 由代の靴先がそれと示すよう、足元で厭な湯気を立てる、消え掛けの固まりを踵で踏み潰して苦笑いをした。 三人が居るのはイブや七重が居る場所とは違い、道も何も無い、ただのまっ平らで薄ぼんやりとした空間である。地面と言う程のものもなく、ただそれぞれの二本の足が踏み締めて立っていられるから、そこが地面なのだろうと認識する程度であった。 「人の夢と己の夢が混ざり合っている、と言うのは、正直あまり心地よいものではありませんねぇ」 どこへともなく三人揃って歩き出しながら、モーリスがそう零す。が、笑み混じりの語調ゆえ、言葉ほどには今の状況を嫌がってはいないようにも聞こえる。 「その口調では、まるで他人事のようですねぇ…この空間の中には、あなたの夢も混ざってる筈ではないですか?」 若干揶揄うような言葉で、司録が低く喉で笑う。応えた様子もなく、モーリスも口元で笑い返した。 「私は、夢の中の私には会いたくないなぁと、その程度ですよ。自分で自分を相手にする事ほど、厄介な事はありませんからね。それに、大概、夢の中では、人はあり得ない無敵になってたりするものですし」 「自分を相手にはしたくない、ってのには同意だね。自分ってのは、一番良く分かっていて一番良く分からない相手だ。…己自身に打ち勝つ勇気が、ここから脱出する鍵、なんて陳腐なオチにはならないだろうね?」 柄じゃないんだ、と由代のバリトンが静かな笑いで震えた。 「恐らく、このメンバーではその解決方法はあり得ないでしょうな…柄じゃないのはあなたに限った事でもなさそうだ。大体、私には打ち勝つべき自分と言うものがありませんから、それが本当の鍵ならば、私は永遠にここから出られない羽目になる」 「そもそも、この温泉の目的とは、何なのだろう?」 由代がそう言って魔導着の裾を捌く。宙で何かを掴むような仕種をするモーリスが、二人の視線に気付いて、何でもありません、と笑顔を返しつつ、由代の問い掛けに答える。 「温泉ですから、やはり心身共の休息と癒し、でしょうか」 「…いや、それは、一般的な温泉の効能であって……」 「砂蒸し温泉の特徴として、発汗作用を促す事により、体内の老廃物を排出する、と言うものがありましたな」 確か、と何か物事を深く考える三下と言うのが物珍しく、思わずまじまじと見てしまう由代とモーリス。だが、中身は司録なのだから当たり前だが、いつものように「な、何を見てるんですかぁ〜、あっ、密かに僕の事バカにしてますね!?」と騒ぐ事はなかった。 「…そうだな、夢は、体内に残った老廃物みたいなものかもな」 ぽつりと、由代は呟いた。 「人の内側に留まり、大抵はその存在感は殆どないが、時折、宿主の表層や内面に影響を及ぼしたりする。眠ってみる夢は一過性のウィルスみたいなもの、覚めてみる夢や過去の想いは、自覚症状の無い腫瘍みたいなものか」 「では、この空間は、そんな人々の夢や想いが排出され、満たされている…と」 なるほど、と付け足してモーリスは目には見えないそれらを捜すよう、空間へと視線を彷徨わせた。 「では、そうして排出させた夢を、何に活用するのでしょう? それに、夢は老廃物とは違って、例えここで排出されても、持ち主の中から無くなってしまう訳ではありませんよね?」 「そう言えば、沙耶サンが言ってましたね。ここには、人の夢を喰らう蟻地獄がいる、と」 司録がそう言うと、他の二人は頷いて同意を示した。 「実際にウスバカゲロウの幼虫、或いはそれに類似するものが居るのかどうかは分からないが、何者か、この空間を創造する主たる何者かがいる事は間違いないだろうね。そして、そいつが人の夢を排出させている事も」 「では、その蟻地獄が、わざわざ人の夢を吸い出す、その理由はなんでしょう?」 問答のような遣り取りが続く。司録の問い掛けに、モーリスが視線を彼に戻して答えた。 「案外、司録さんと同じような理由かもしれませんね?」 「私と?」 尋ね返す司録に、由代がその意見に同意したよう、笑って頷く。 「ああ、なるほど。司録さんが人の『恐怖』や『噂』、『悪夢』を愉しむのと同じように、ここの主は人の夢を味わう事を愉しみに、或いは糧にしている、と」 「それはそれは…ますます居心地が悪く感じられますねぇ…味わいの嗜好は違うとは言え、似たような楽しみを持つ相手と言うのは。同好の士と言うよりは、私のお株を獲られたような気分で複雑ですね」 くつくつと吐息で嗤う司録だが、やはり言葉どおりに不快であるようにはあまり見えなかった。 「ではやはり、その主とやらに会いに行かないと話しは終わらないような感じですね。ここから、実際に温泉に浸かって眠っている現実の私達にアプローチするのは難しいそうですから」 「一番手っ取り早いのは、ここの家主に掛け合って出してくれと頼む事だな、確かに。だが、その家主の居場所は……」 由代が途中で言葉を途切れさせる。それに気付いたモーリスと司録は、由代の視線の先を辿って、薄ぼんやりと白く霞む向こうの方を見た。 そこに居たのは、『此処』ではないどこか異世界の住人。どんなと人の言葉では形容できないようなその形状に、惧れからか或いは高揚からか、三人がそれぞれに武者震いをした。 そんな彼らの目に、彼らの前に立ちはだかる異形の向こう側に、何者か二人の人の姿が見えたような気がした。 【side-A,and B】 「来るわよ」 常とは違う、緊張を孕んだ声でイヴが呟く。隣で、七重がひとつ浅く頷く気配がした。 目の前の異形は、イヴが今まで見てきたものとは若干違うようだ。七重クンの『夢』かしら、と横目でちろりと隣の少年へ視線を向けてみるが、彼は白い頬を僅かに紅潮させ、唇を引き締めているだけだった。 自分の故郷の魔物であれば、魔力で自分に使役させる事も可能なのだろうが、目の前に居る見覚えの無い異形にも、その力が及ぶかどうかは疑問だった。 「大体、ここは夢の世界なんですもの、いつもの自分の力が思い通りに使えるかどうかも分からないんですものね…」 「…………」 イヴの言葉は単なる独り言だったのだが、それにビクリと反応して七重が身体を強張らせた。それに気付いたイヴが、意識を異形と七重と両方に等しく分けて、七重に向けては心配そうな色を濃くした。 「…どうしたの……?」 「…今更ですが、気付いたんです……さっき、イヴさんが僕に言った事、……」 「さっき……ああ、七重クンの印象が違う…って事?」 イヴの言葉に、七重は無言で頷く。 「ええ、普通の中学生みたいに見える…って仰いましたよね。…確かに、今の僕は、どこにでも居るただの中学生…のようです」 「…どう言う、……」 尋ね返しつつも、イヴの語調には、まさか、と言う懸念の色が隠せない。そのまさかです、と七重が歪んだ笑みを浮かべようとした時だった。 「危ないっ!」 イヴの鋭い叫びと共に、七重の身体は横薙ぎに押し倒される。その後の空間を、異形の禍々しい爪が引き裂いていった。 いきなりの異形の攻撃を、イヴが七重も一緒にして間一髪で避けたのだ。 「大丈夫?七重クン」 「僕は大丈夫…イヴさん、僕の事は構いませんから」 「七重クンッ!」 ぴしゃりと、イヴが諌めるように語気を強める。 「言ったでしょっ、困った時はお互い様だって! もしも七重クンが何の力も使えない状態なら、使えるわたしが何とかしなきゃ!持ちつ持たれつだって言ったでしょッ」 「………」 七重は思わず下唇を噛む。『普通』とは、こんなに歯痒く頼りないものだったのか。いや違う。これはあくまで、七重が自分の内に思い描いた『普通』のイメージだ。普通であると言う事は、こんな、己の身も自分で守れない程に弱々しく情けない存在な筈ではない。平凡である事と、無価値である事は同意語ではない。 七重君。その現実を、直視するかい?キミがキミである所以、その唯一無二の事実を。 どこかで聞いた事のあるような、静かなバリトンが響いた。 その頃、その異形の向こう側には、由代、モーリス、そして司録(その姿は相変わらず三下のものだったが)の三人がいたのだ。この目の前の異形が誰の夢であるか等と言う事は、この際二の次だ。ここの主が、それぞれの夢を味わって悦楽に浸っているとするならば、今己らが対峙している誰かの夢、その中央に、主は胡坐を掻いている筈である。だとしたら、多少荒っぽいが手っ取り早い手段として、目の前の異形へと歯向かっていく事が、蟻地獄の真ん中への一番の近道だと三人は予想したのだ。 「…向こう側に誰か居ますね」 司録の言葉に、既にその事実に気付いていた二人は頷く。 「この夢の持ち主かもしれませんね。或いは、混ざり合って生まれたキメラか。いずれにせよ、当事者がこの場に揃うのは好都合ですよ。恐らく、それぞれから滲み出る夢も濃くなるでしょうから、蟻地獄の元にもより近付くと思われます」 「では、皆さんにもっと多くの夢を排出して頂ければ、近道を更に引き寄せる事も可能かもしれませんね?」 そうして、現実の皆さん自身に、気付いて頂きましょう。 そう言うと、三下の顔の中で、何故か白い歯を剥き出した口元だけが強調され、それだけが視角に残る。にやりと両端を持ち上げて嗤うその表情に、その場に居た人はそれぞれ違う声を聞いた。それは自分の親しい人の声や愛する人の声であったり、或いは忌むべき相手の声であったり。声も内容もてんでばらばらではあったが、それらは一応に、自分達が今居る白い靄のようなものでも、ちゃんと踏み締めていられる事実を、思い出させたのだった。 「……あら、三下さん?」 イヴの澄んだ声が聞こえた。いつしか、異形を真ん中にして、五人が円を描いて立っていた。 【side-END】 「…違うわね、三下さんじゃないわね?」 鋭く、その違いに気付いたイヴは、三下の顔をした司録の目をじっと見詰める。低く喉を鳴らして嗤うその様子に、あっと声を上げて自分の口元を押さえた。 「やだ、司録さんじゃないの。どうして、三下さんの姿をしているの?」 「いやはや、さすがイヴサンだ。女性の観察眼は、やはり鋭いものですなぁ…」 司録の言葉に、イヴはくすくすと揶揄うような笑い声を零す。 「誰だって分かるわ。だって三下さんは、そんな意地悪そうな笑い方はしないもの」 「そんなのんびりオハナシしている暇はなさそうですよ、イヴさん」 そう言いつつも、くすくすと笑いを漏らしながらモーリスが言った。 「…皆さん、何だか、すごく余裕あるように見えるんですけど……」 七重が、傍らの由代の顔を見上げると、由代は笑って肩を竦める。 「始終こんな調子だったからね、多分、僕達の夢はあんまり美味しくなかったんだろう。邪魔だからとっとと皆で揃って帰れ、とここに呼び付けられたんだよ」 「ひどいですねぇ、由代さん。それでは、私の夢もつまらなかったと仰るのですか?」 自分の夢が垣間見え掛けると、片っ端からあるべき場所、あるべき姿に、人知れず戻していたモーリスが言えた義理ではないが。 「まぁ、いずれにせよ、この目の前に居る誰かの夢を追い詰めなければ、僕達はここから帰る事も叶わない、と踏んでいるんだ。これだけ揃っているんだ、手早く済ませてしまわないか?」 由代のその言葉に、七重が下唇を噛み締めて俯く。ふ、と視線をあげ、目の前の異形を見詰めると、そっちへと向かって歩き始める。イヴが、慌ててその袖を掴んで引き止めた。 「七重クン?ダメよ、幾ら夢の中だって言っても、ここは違うのよ!? もしここでやられちゃったら、現実の七重クンもどうなるか分からないのよ!」 「大丈夫ですよ、イヴさん」 七重が、薄らと微笑んで、袖を掴むイヴの手を優しく解く。 「夢です、ここは所詮は夢の世界です。例え、本当に現実になってしまう夢であっても、曲げようの無い事実を凌駕してしまうような夢ならば、元より現実の僕はその程度のものだったと言う事ですよ」 怖れるに足りない。そう口の中で呟くと、七重は再びその足を踏み出す。近付き、より巨大になる異形のシルエットに、恐怖とも違う、何かの高揚感に七重はその背中を押し出された。 「七重君!」 由代が空に何かの文字を描く。シジルによって召還された何者かがその姿を完全に現す前に、異形に向かって飛び出していった七重の姿ともども、白い靄のその世界も、大量の熱い湯に溶けていく一匙の生クリームのよう、瞬く間に薄らいでいった。 「…まさか本当に、自分自身に立ち向かう事が鍵だったとは」 溜息混じりにそう呟くモーリスの傍らで、元の服装に戻った由代が微かに肩を揺らして笑う。 「だから、僕達だけではきっと、もっと帰ってこれるのが遅れたかもしれないね。若さの勝利かな」 「…からかわないで下さい。これでも僕は必死だったんですから……」 自分の銀色の髪を指で摘みながら、七重が困ったように薄らと笑った。 気が付くとそこは、元々いた世界だった、なんて王道の展開で戻ってきた皆は、改めて周囲へと視線を巡らせる。目に映る色、輪郭、その全てがさっきまでの薄靄の世界よりもずっと鮮明に輝いて見えるのは、単なる先入観の所為だろうか。 「他にも多分、戻る為の鍵はあったのでしょう。夢は十人十色、きっかけや手段も千差万別と言う訳です」 「…司録さん、やっぱりその姿の方が、なんだかしっくり来るような気がするわ」 そう言って見詰めてくるイヴの瞳に、でしょう?と司録は鍔広帽子の陰で白い歯を剥き出して笑った。 「三下サンの格好でいるのはなかなか心地良かったですけどね…だがしかし、固定されたイメージはどうにも私の性には合いません。この姿が一番ですよ」 「案外、元の世界に戻りたいと一番強く願っていたのは、司録さんかもしれないね?」 揶揄混じりの由代の言葉に、同意する訳でも否定する訳でもなく、司録はただ口端を持ち上げる。 「元より、ここに居る皆さんは、見果てぬ夢に叶わぬ期待を載せて嘆くタイプでもありませんし、リアルを認識して頂いても、然程ダメージを受けてませんでしたしね。そう言う意味では、蟻地獄は満足できずに羽化し損ねたと言うところじゃないですかね」 「…そっか、じゃあ、とっとと異世界召還で戻ってきても良かったのねー…」 何気なく呟いたイヴの言葉に、モーリスがにっこりと完璧な笑みを浮かべて彼女の方を見詰めた。 「…イヴさん、そのような便利な能力をお持ちな事、最初から分かってて…?」 「……………。……ええと」 えへ。と可愛く笑って誤魔化すイヴに、クッと誰かが口角で笑んだ。 まぁいいじゃないか。寄り道も、また一興。 出口も入り口も、ひとつ限りではないのだから。 おわり。 □■■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■■■■■□ ■ 登場人物(この物語に登場した人物の一覧) ■ □■■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■■■■■□ 【 1548 / イヴ・ソマリア / 女 / 502歳 / アイドル歌手兼異世界調査員 】 【 2557 / 尾神・七重 / 男 / 14歳 / 中学生 】 【 2839 / 城ヶ崎・由代 / 男 / 42歳 / 魔術師 】 【 2318 / モーリス・ラジアル / 男 / 527歳 / ガードナー・医師・調和者 】 【 0441 / 無我・司録 / 男 / 50歳 / 自称・探偵 】 |
|
|
|
||
|
|
||
|
|
【個別ノベル】 【0441/無我・司録】 【1548/イヴ・ソマリア】 【2318/モーリス・ラジアル】 【2557/尾神・七重】 【2839/城ヶ崎・由代】 |
|
|
|
||
|
|