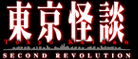 |
|
|
|
||
|
|
調査コードネーム:あかずの間探索行 執筆ライター :織人文 関連異界 :【時空庭園】 【オープニング】 【 共通ノベル 】 【 個別ノベル 】 |
|
|
|
||
|
|
||
|
|
 【オープニング】
【オープニング】「あかずの間、ですか?」 蓬莱館のロビーの一画で、湯上りにアイスクリームなど食べながらくつろいでいた妹尾静流は、同じくアイスを食べながらくつろいでいた碇麗香の言葉に、思わず問い返す。 彼女が言うには、この蓬莱館には誰も入ったことのない「あかずの間」があって、そこには百年前、ここが現世に出現した時遊びに来て取り残された人間がいるという噂があるらしい。 問い返す静流に、彼女はたしかな筋から聞いた話だと付け加えた。 静流は、アイスをスプーンですくって口に運びながら、これだけ広ければ、使われていない部屋の一つや二つぐらいあってもおかしくはないだろう、と考える。が、本当だとしたらそれはそれで面白い。そもそも、百年前の人間が、まだ生きているものなのだろうか。静流は、ふと思いついて言った。 「面白そうですね。どうでしょう? 他の方たちも誘って、その『あかずの間』とやらを探してみるというのは」 言われて麗香はしばし考え込んでいたが、やがて大きくうなずいた。 「そうね。これだけ広い場所なら、探索のしがいもありそうだし。そうと決まったら、他の人たちにも、声をかけてみましょうか」 やおら立ち上がる麗香に、静流はアイスの最後のひとかけらをスプーンで口に入れると、慌ててその後に続いた。 【ライターより】 ※妹尾静流についての詳細は、「異鏡現象〜異界〜」内、【時空庭園】を参照下さい。 |
|
|
|
||
|
|
||
|
|
【共通ノベル】 【プロローグ】 蓬莱館のどこかにあかずの間があって、そこに百年前の人間が閉じ込められている――そう言いだしたのは、休暇で高峰温泉にやって来て、蓬莱館に泊まっている碇麗香だった。 他の人間ならばともかく、怪奇雑誌としては中堅どころの『月刊アトラス』編集長である彼女の言葉だ。あながち嘘とも思えない。 たとえ嘘だったところで、それはそれで、温泉旅館での一つのレクリエーションと割り切って笑って済ませることができるだろうと妹尾静流は考え、彼女と一緒にそのあかずの間を探すことにした。 とはいえ、二人だけではさほど広範囲を調べることは無理だ。そこで他にも一緒にあかずの間探しをやろうという人間はいないだろうかと、二人は自分たちが泊まっている棟の中を散策を兼ねて歩いた。 彼らの泊まっている蓬莱館は、ずいぶんと広く、いくつもの棟に別れている。 麗香と静流の部屋があるのは、「桃花(とうか)亭」と呼ばれる棟で、建物のそこかしこに桃の花の意匠が使われ、庭や入り口傍には桃の木がいくつもあって、すでにその花の季節は過ぎているというのに、花をつけ、宿泊客の目を楽しませていた。 建物そのものは、木造でずいぶんと古いようだが、床は光るほどに磨き込まれ、どこもかしこも清潔で気持ちがよかった。 出される料理は場所が富士山の麓であるせいか、山の幸である山菜や、猪、雉、鳩などの肉、川魚がふんだんに使われ、なかなかに美味だった。 むろん、宿の最大の目玉である温泉も悪くなかった。 大きな露天風呂は二ヶ所あって、一ヶ所は男性たちが喜びそうな、混浴である。また、室内にある大浴場には、ごく一般的なものと、ジャグジーなどを備えたスパ風のものとがあった。他にも、各棟ごとにいくつか小さな露天風呂が設置され、ただそれらを回るだけでも充分楽しめそうだった。 そんな充実した宿だというのに、客の姿はあまりない。 彼らのいる桃花亭がそうなのか、それともこの蓬莱館自体が寂れてしまっているのだろうか。 静流がそんなことを思い始めたころ、彼らはやっと宿泊客の一人に遭遇した。季節はずれの桃の花が咲き乱れる中庭でのことだ。小さな人工池の傍に佇む桃の木の下に設置されたベンチに座して、その人は読書の最中だった。ショートカットの黒髪に、銀縁メガネ、長身のその人は、肌の白さと線の細さを引き立てるような濃紺のパンツスーツを身にまとい、一見すると線の細い男性のようでもある。年齢は、二十二、三歳ぐらいか。 都立の図書館に、司書として勤める綾和泉汐耶だった。 「汐耶さん」 静流が声をかけると、彼女は顔を上げ、こちらをふり返った。 「あら。妹尾さんも、ここへ来ていたんですね」 「ええ」 静流はうなずいて、彼女が膝に広げている本をちらりと見やる。 「新しい収穫ですか?」 「ええまあ。……少し遠くまで足を伸ばして古書店を巡って、疲れを取るために、ここへ来たの。あの高峰さんの招待だから、どんな所か興味もあったし」 「ああ、なるほど」 曖昧にうなずいて言う汐耶に、静流が相槌を打った。 そんな二人のやりとりに、麗香が尋ねる。 「何? あなたたち、知り合いなの?」 「ええ、まあ」 静流は、曖昧にうなずく。旧知の仲というほどではないが、ちょっとしたきっかけで知り合って、同じ読書好きということで、互いに顔と名前は印象に残っていた。 うなずく静流を、麗香は軽く目を細めて見やり、小さく肩をすくめる。 「まあいいわ。それより汐耶、面白そうな話があるんだけど、一口乗らない?」 「話の内容にもよりますね」 汐耶は冷静に答えて、広げていた本のページに栞を挟むと閉じた。 「どんな話でしょう?」 問い返して、汐耶が話を聞く体勢になった時、静流と麗香の背後から、ふいに声が響いた。 「それなら、私も聞きたいわ、その話」 驚いて背後をふり返った静流と麗香は、そこに立っている女性に軽く目を見張った。 「シュライン!」 「シュラインさん!」 二人が同時に声を上げる。 いつの間にか彼らの背後に現われたのは、翻訳家でもあり草間興信所の事務員でもあるシュライン・エマだった。年齢は、二十五、六歳というところか。長く伸ばした黒髪を後ろで一つに束ね、長身でほっそりした体には、この蓬莱館備えつけの浴衣をまとっている。 浴衣といっても、ここのは一般的な着物ではなく、和風プラス中華風とでもいうのだろうか。手首に行くほど広がった袖のある前合わせの着物の上に、中国風の襟のある袖のない上着を重ね、そこに帯を巻くといった独特のスタイルだ。 シュラインは、いくつか色があるその浴衣の中の、濃紺の地に濃い赤の縁取りのあるものをまとっていた。細い体に、それがよく似合っている。胸元には、いつもどおり、色つきのメガネが揺れていた。 声を上げる二人に、シュラインはわずかに目を見開いて苦笑する。 「そんなに驚かなくても……」 「ああ、すみません。この建物にはあまり人がいないですから、つい……」 「シュラインも、急に後ろから声をかけたのがいけないんじゃない?」 静流が謝るのへ、汐耶が傍から言った。 「あ……。それもそうね」 シュラインも、気づいて軽く目で天を仰ぐ。彼女自身は優れた聴力で彼らの話し声が遠くからでも聞こえていたのだが、彼らの方からしてみれば、いきなり自分が現れたように思えたのだろうと気づいたのだ。 「別に、気にしてませんから……」 それへ静流が慌てて言う。そして、麗香にあかずの間について話すよう、目で促した。 麗香はうなずき、小さく咳払いすると、汐耶とシュラインに改めてあかずの間の話をした。 聞き終えて、汐耶とシュラインは思わず顔を見合わせる。 「それが本当なら、興味深い話だわね」 「ええ。……ここは静かで、読書するには最適だけど、少しは体を動かすのもいいわ」 シュラインの言葉にうなずいて、汐耶は小さく首をかしげた。 「ところで、そのあかずの間に閉じ込められている人というのは、どんな人なんですか?」 「百年前といったら、一九〇四年……ちょうど日露戦争の始まった年じゃなかったかしら」 尋ねる汐耶に、シュラインも言った。 「よく知ってるわね」 麗香が、感心したように返す。 「日露戦争の始まった年の四月に、タバコの専売法が公布されてるの。それが、明治三十七年……つまり、ちょうど百年前の一九〇四年だって聞いたことがあったから」 肩をすくめて言うシュラインに、「ああ、タバコね」と麗香は意味ありげな目をして笑った。そして、彼らに長くなるからと、汐耶が座しているベンチに座るよう促す。 シュラインと静流が腰を降ろすと、彼女はあかずの間に閉じ込められてしまった人物について、語り始めた。 その人は、名を咲耶(さくや)と言って、当時まだ十五、六歳の少女だったという。この蓬莱館の近くの小さな村でくらしていたが、両親は早くに亡くなり、彼女は祖母と二人ぐらしだった。 この時代、地方にくらす少女たちは、農家であれば家業を手伝うか、早くに同じ村落の若者に嫁ぐか、さもなければ都市の工場や商家へ働きに行くかが普通だった。だが、咲耶には小さいころから優れた霊力があり、それで村人たちの悩み相談に乗ったり、病気や怪我を治したりして日々の食い扶持を稼ぎ、祖母を助けて小さな畑を耕してくらしていた。 村人たちは、彼女を敬いながらも恐れ、けして粗雑に扱うことはなかった。 だが、日露戦争の始まったその年の夏、村は時ならぬ集中豪雨に襲われ、多くの家や田畑が崩れた崖の下に埋まり、水に流され、半壊するという事態になった。呆然自失する村人たちに、所用で他所へ出かけていて帰って来た者が、この豪雨は村の近辺だけだったと教えたことから、彼らの怒りは咲耶に向けられた。村人たちは、咲耶が村を守れなかったばかりか、その霊力で雨を呼んで村をこんなふうにしたのだと糾弾したのだ。 むろん、実際には彼女にはそこまでの力はなかっただろうし、何より祖母も、その豪雨で死亡していたのだが、村人は彼女の無実の声に耳を傾けようとはしなかった。 結局彼女は、村はずれの洞窟に閉じ込められ、やがて再建された村の中央に、人柱として埋められることが決まった。 だが、さすがにそれを哀れと感じる者もいて、その手引きで咲耶は閉じ込められた洞窟を逃れ、この高峰温泉・蓬莱館へとたどり着いたのだという。 「――咲耶は、ここの人たちに助けられ、介抱されたらしいわ。でも、当人にはもう生きる気力はなかったみたいね。それを説得したのが、たまたまここに泊まっていた高僧だったそうよ。でも、結局説得は成功せず、その僧は、最後には咲耶の懇願に負けて、彼女をこの蓬莱館のどこかへ閉じ込め、封印することを承知したそうなの」 「それがつまり、あかずの間ということね?」 ずっと黙って話を聞いていたシュラインが、たしかめるように問う。 「ええ。その高僧は、ほとぼりが覚めたら、咲耶を出してやるつもりだったようだけど……結局病死してしまって、その後は誰も封印を解ける者もなくてそのまま、だったようね」 麗香がうなずいて言った。 「でも、百年っていったら、けっこう長いですよね。はたしてその人、生きているんでしょうか?」 汐耶が、幾分考え込みながらそれへ問う。 「そうよね。第一、そんな所に閉じ込められっぱなしじゃ、食べ物とかもないだろうし」 シュラインもうなずく。 「さあ、それは私にもわからないわね」 麗香は幾分冷たく肩をすくめた。 「普通なら、死んでるでしょうけど、強い霊力があったというから、生きているかもしれないわ」 「生死の有無はわからないですが、魂は転生していません。その場に留まっている可能性が高いですね」 ふいに静流が言ったので、三人は驚いたようにそちらをふり返った。 「それ、どういうこと?」 「妹尾さんは、そういうのがわかるんですか? 前にお会いした時には、そんな能力はないと言ってましたけど」 シュラインと汐耶が、それぞれ違うことを問う。 静流には、他人の前世を見る能力があった。当人の感覚では、ちょうどビデオテープを見るような感じなのだそうだ。 ちなみに、彼と草間の間に親交があるため、シュラインは彼のこの能力を漠然とだが知っていた。が、汐耶の方は知り合って日が浅いこともあり、知らなかった。 二人の問いに、静流はまず自分の能力について告げてから言った。 「普段は、その当人を目の前にしないと何もわからないんですが……今、麗香さんの話を聞いていて、ふと頭の中に浮かんで来たんです。この人はまだ、現世に転生していない、魂は行くべきところに行っていないかもしれない、と」 「ああ……」 シュラインも汐耶も、納得したようにうなずいた。 「もしそれが封印のせいなら……解放してあげたいですね」 汐耶が、何を思うのか軽く目を伏せるようにして呟く。 「そうね。……可能性は薄いかもしれないけど、もし生きているなら外に出して少しでも楽しい思いをさせてあげたいし、そうでないなら、魂だけでも自由にしてあげたいわね」 シュラインもうなずく。 こうして、彼ら四人は、あかずの間を探し、そこに閉じ込められた百年前の少女・咲耶を助けることを決めたのだった。 【時じくの香の木の実】 そろそろ、午後のお茶の時間になろうかというころ。 汐耶は静流と二人、自分たちが泊まっている桃花亭から少し離れたところにある、「時じく亭」なる棟にいた。 あの後、更に麗香が言うには、あかずの間を見つけるためには、まずそこに続く通路を見つけないといけないらしいのだ。 この蓬莱館の建物はたくさんある上に、かなり入り組んでいるようだ。高僧はそれを利用して、咲耶を一種の隠し部屋のような所に閉じ込めた。それがつまり、彼女たちの探している「あかずの間」だった。その部屋に続く廊下は「菊」「橘」「桃」の三つの鍵によって閉ざされており、しかも「桃」の鍵は他の二つを開けてからでなければ、開くことができないのだという。 麗香は、彼女たちをここに招待したそもそもの張本人である高峰沙耶から聞き出したのだと言って、自分で作成したらしい蓬莱館の大雑把な見取り図を持っていた。それによれば、蓬莱館の建物には、桃花亭という名でもわかるように、草花の名前をつけられた建物が多いらしく、「菊花(きくか)亭」というのが存在した。四人はここに「菊」の鍵があるのではないかと考えたのだ。 一方、「橘」に該当するのは、今汐耶と静流がいる時じく亭ではないかと推測された。なぜなら古来、橘は「時じくの香(かく)の木(こ)の実」とも呼ばれていたのだ。 そこで四人は二組に分かれて、まず「菊」と「橘」の鍵を探すことにしたのである。 誰と誰が組むかを決めたのは、麗香だった。 そしてその結果、麗香はシュラインと共に菊花亭へと向かい、汐耶は静流と共にこの時じく亭へやって来たというわけだった。 時じく亭は、彼女たちのいた桃花亭がそうだったように、季節はずれの花をつけた橘の木がそこかしこに立ち並び、さわやかな香をあたりに漂わせていた。 だが、ここにもやはり、泊まり客の姿はない。にも関わらず、客室と思しい部屋はどこにも鍵がかかっておらず、二人は片っ端からそれらの室内を調べて回ったが、「橘」の鍵らしいものは見つからなかった。 かなり歩き回ったせいで、喉も乾いている。ちょうど廊下の途中がロビーのようになっている場所に出たこともあって、汐耶は静流に、少し休むことを提案した。静流も賛成し、二人はそれぞれ自動販売機でジュースを買って、そこに設置された合成革を張った椅子に腰を降ろす。ちなみに、汐耶の手にあの時読んでいた本はなかった。ここへ来る前に自分の部屋に置いて来たのだ。 「それにしても、他の建物にならもっと人がいるかと思ったのに、私たちがいた建物と、あんまり変わりませんね」 缶の中身を半分ほど飲んでから、汐耶はあたりを見回して言った。 「この温泉のことを聞こうと思って、高峰さんに電話した時は、かなり大勢の人を招待したようなことを言ってましたけど」 「ええ。私も、そう聞きました。……草間さんも零さんを連れて来るって言ってたんですが」 「ああ……そういえば、シュラインも同じこと言ってましたね。来てるはずなのに、会えないって」 言いながら彼女は、半ば無意識にジュースの缶を再び口元に運ぶ。 次第に、何か変だという気持ちが、彼女の中に募り始めていた。従業員らしい者の姿が見えないのは、まだ納得できる。あの高峰沙耶の持ち物なのだ。ここの従業員が人間ではなかったりしたとしても、まったく不思議ではない。だが、客が自分たち四人だけらしいというのは、いったいどういうことだろうか。 (通常の空間から切り離されてしまったということ?) 彼女はふと、そんなことを胸に呟く。だが、物事が確定しないうちは、決め付けは禁物だ。そう自分に言い聞かせ、彼女はもう一つ気になっていたことを、静流に質した。 「ところで、碇さんは、お仕事でここへ来たんでしょうか?」 「いえ、休暇だって言ってました。三ヶ月ぶりだそうですよ」 静流は答えて、苦笑する。 「なんだか、休暇中には見えませんけどね。……まるで取材に来たみたいで」 「そうですね」 汐耶も笑って相槌を打った。 そこへ、蓬莱館の唯一の従業員である蓬莱が姿を現した。十五、六歳ぐらいとおぼしい中国風の衣装に身を包んだ愛らしい少女である。彼女は手に、籐の籠を下げていた。 「お客様、ふかしたての桃饅はいかがですか?」 二人の姿に、笑顔で歩み寄って来て尋ねる。見れば籠の中身は言葉どおり、あつあつの桃饅だった。汐耶は幾分空腹を覚えていたので、それを一つ手にした。蓬莱は静流にも勧めたが、彼は小さくかぶりをふって断る。そして、ついでのように訊いた。 「ここは、ずいぶんと人の姿が少ないですが、宿泊客は、私たち四人だけなのですか?」 途端、蓬莱は一瞬だったが軽く目を見張った。が、すぐにそれを隠すように微笑む。 「いいえ。他にもたくさんの方がお見えです。……この蓬莱館は広いですから、それでお客様が少ないように見えるのだと思います」 言って、軽く目をしばたたき、蓬莱は続けた。 「ところで、お客様はどちらもお部屋はこの時じく亭ではなかったかと思いますが……?」 問われて、二人は思わず顔を見合わせる。ややあって、汐耶は正直にあかずの間を探してここへ来たのだと告げた。途端に蓬莱は、小さく溜息をついた。 「いまだにあの噂は絶えていないんですね。……申し訳ありませんが、蓬莱館にはあかずの間などございません。あれは、昔この温泉の支配人だった者が、客を呼ぶために創作した作り話です」 「作り話……ですか」 「はい」 問い返す汐耶に、彼女はきっぱりとうなずいた。 再び、汐耶と静流は顔を見合わせる。休暇中とはいえ、あの麗香がただの作り話でここまで熱心に動くはずがない。それに、もし作り話なら、桃花亭の庭で静流が感じたものはなんんなのか。 「話そのものは、創作だったとしても、その元となった出来事か何かが、あるのじゃないですか?」 今度は、静流が尋ねる。 蓬莱は、その彼を困ったように見やった。ちらと汐耶をも見やり、彼女も真剣に自分を見詰めているのに気づくと、蓬莱は小さく溜息をついた。 「――ここの中庭に、小さな離れがございます。そちらに行ってみてはいかがでしょう」 言うと彼女は二人に一礼し、踵を返す。何か声をかけることさえためらわせるような、強い拒絶の色の漂う背中だった。そのまま彼女はそこを立ち去って行く。 それを二人は、みたび顔を見合わせ、見送った。 桃饅を食べ終えると、汐耶は静流と二人、蓬莱に言われたとおり時じく亭の中庭に出た。 そこは、さほど大きくはないが、満開の花をつけた橘の木が何本も植わっており、その香で一杯だった。少し行くと、小さな建物が目に入った。それが離れのようだ。 ここもやはり鍵はかかっておらず、狭い玄関を抜けると、短い廊下の先に部屋があった。 蓬莱館は全体に作りが和風と中華風のミックスされた、不思議な様式を持っていたが、この離れは完全に中華風だった。部屋はさほど広くはなく、中央に木のテーブルがあって、それを囲むようにまっすぐな背もたれを持つ椅子が何脚か置かれている。 テーブルの上には、両手で持ち上げられる程度の大きさの盆栽が置かれていたが、長方形の鉢に植えられているのは精巧な作り物の橘の木だった。 また、入り口の正面の壁には掛け軸が掛かっていたが、描かれているのは山門で、手前には橘の木が描かれていた。 「ここも、橘づくしですね」 呟くように言って、汐耶はテーブルの上の作り物の橘の木を見やった。木には花は咲いておらず、かわりに橙色の丸い実が成っていた。よく見るとその実はトパーズで、幹や枝は黒檀、葉はエメラルドで作られている。それに気づいて、汐耶は思わず目をしばたたいた。いくらなんでも客室にこんな高価そうなものを飾るというのは、物騒すぎないか。 「妹尾さん……」 何か言おうと顔を上げ、静流の方を見やった彼女は、思わず言いかけた言葉を飲み込む。 静流は、壁の掛け軸の橘の木のあたりに手を触れていたのだが、その部分がまるで水面に手を触れた時のように波打っているのだ。だけではない。墨で描かれているはずの橘の木の実が、見る間に橙色に色づいて行く。 当の静流も驚いたらしい。慌てて手を離す。途端に掛け軸の表面は元どおりになったが、色づいた橘の実だけは変わらなかった。 その異変に、汐耶は直感的に、その掛け軸こそが「橘」の鍵で開かれる扉だと察した。彼女の持つ封印能力を逆に応用すれば、鍵開けはさほど難しいことではない。だが、ここの場合、そう単純なものではないはずだと彼女は考える。 そして、ふとテーブルの上の作り物の橘の木を見やった。 (ああ、なるほど) 彼女は胸にうなずき、その木に軽く手をかける。封印を開ける時の要領で、自身の持つ力を逆転させて送り込んだ。作り物の木から、実が一つころがり落ちる。豆粒ほどの大きさのそれは、ころがったテーブルの上で、トパーズの小さな鍵と化した。 鍵は、ゆるやかに浮かび上がると、真っ直ぐに壁の掛け軸の所まで飛んで、墨絵であるはずの山門の扉に掛けられた南京錠の鍵穴に収まった。途端、小さく鍵のはずれる音があたりに響く。 「……すごいですね」 静流が、低い感嘆の声を上げた。掛け軸が、一瞬にして水と化してその場に流れ落ち、その後ろから本物の扉が現れる。扉には、封印の札らしいものが貼られていたが、それはすでに破れていた。その下の床には、先程のトパーズの鍵が落ちている。汐耶はなんの気なしにそれを拾い上げ、上着のポケットに収めた。 「これで、『橘』の鍵は開いたようね。行きましょうか」 彼女は小さく微笑み、静流を促した。そして、先に立って扉を軽く押す。小さくきしんで開いた扉の奥へと、二人は黙って足を踏み入れた。 【菊花】 そのころ、シュラインは麗香と共に菊花亭の方にいた。 麗香はまるで、建物の間取りを知っているかのように、先に立って歩いて行く。その後に続きながら、シュラインはずっと奇妙な居心地の悪さを感じていた。 その居心地の悪さの原因は、あたりに人の姿がないにも関わらず、人の気配を感じるというところから来ている。それは、桃花亭にいた時にもかすかに感じてはいたものだが、あそこでは、努めてあたりの気配を気にしないようにしていた。だが今は、逆に鍵のありかを捜すため、周囲の音や気配に耳を澄ませている。だからよけいに敏感になっているのだと言えば言えた。 それにしても。 ぱたぱたと誰かが通り過ぎて行くような足音に、驚いてふり返っても、そこには誰もおらず、どこかで笑い声や話し声を聞いたと思って、そちらへ行ってみても、やはり人の姿がないというのは、いったいどういうことなのだろうか。 (沙耶さんの持ち物ですものね。案外、幽霊宿だった、ということも考えられなくないわね) 彼女はふと、そんなことを考えてもみる。だが、たとえそうだったにしても、人間の客もいるはずなのだ。実際、高峰沙耶はかなりの人間をここへ招待したと言っていたし、草間からは零を連れて来るつもりだと聞かされていた。 (何か変よね) 胸に呟き、彼女は前を行く麗香の背に、改めて視線を向ける。 変といえば、この女も変だ。 むろん、あかずの間とそこに閉じ込められている少女の話を聞いて、麗香が興味を持つというのはわかる。もともと好奇心は強いのだろうし、職業柄というのもあるだろう。にしても。なんだか強引すぎないだろうか。 たとえば、この組み合わせのこともそうだ。まるで他の者に別の考えを持たれることを恐れるかのように、さっさと決めてしまった。 シュラインにしろ、誰と組みたいという希望があったわけではないし、麗香とは旧知の仲だ。別にこの組み合わせに否やがあるわけではない。ないのだが……何か、これまた妙な感じがするのである。 そんなことを考えながら、人の姿がないのに人の気配のする建物の中を歩き回っていると、なんだかだんだん気が滅入って来た。 「麗香さん。庭の方へ出て、少し休憩しない?」 前を行く麗香に、そう声をかける。 「え……。ああ、そうね」 麗香は驚いたようにふり返ったが、すぐにうなずいた。 やがて二人は、菊花亭の庭に出た。 菊花亭は、名前のとおり、どこもかしこも菊の花と菊の意匠で一杯の建物だった。庭にも白や黄色、赤紫といった色とりどりの菊が季節はずれにも関わらず、咲き乱れている。 二人は、庭へ降りる入り口の傍にあった自動販売機でそれぞれ缶ジュースを買って、庭の一画にあるベンチに腰を降ろして、休息を取った。 歩き回ったせいで、すっかり喉が乾いていたシュラインは、ベンチに座るとすぐに缶のプルトップを開け、中身を喉に流し込む。 そうやって一息ついてから、彼女は麗香を見やった。 「麗香さんは、その鍵について、他には何も知らないの? どういう所に隠されているとかなんとか」 「そこまでは、さすがに調べきれなかったわ。ただ、それぞれにつけられている名前が、ヒントなんじゃないかと思ったぐらいね」 「そっか」 うなずいてから、ふとシュラインは訊く。 「そういえば……麗香さんは、この建物に前にも入ったことがあるのかしら。なんだか、詳しいわよね?」 「え、ええ……まあね」 麗香は幾分慌てたように、曖昧にうなずいた。そして少しだけバツが悪そうに笑う。 「実は、昨日一人でここを調べたのよ。でも、一人で全部調べるのはとうてい無理だってわかって、誰か協力してくれる人を捜そうって思ったの」 「それで私たちに?」 「まあね」 うなずいて、麗香は笑った。 二人は、缶の中身を飲み干すと、今度は庭を探してみることにして、立ち上がった。 しばらく行くと、小さな緑の築山の向こうに、離れと思しい建物が見えて来た。 「こんな所に離れがあるのね」 「そうね。あそこも見てみましょう」 呟くシュラインに、麗香がうなずいて言うと、先に立って歩き出した。 やがてたどり着いたそこは、完全に中華風で、居間と寝室、トイレと内風呂があるだけの、ごくこじんまりとした作りの建物だった。 シュラインは、隠し部屋の有無を調べるために、建物の中を見て回りながら壁を叩いてみたり、壁の向こうの物音に耳を澄ませてみたりもした。 だが、不自然な音を立てる壁もなく、ここでは菊花亭の中で感じたような奇妙な人の気配も感じなかった。 二人はやがて、玄関の近くに位置する居間へと戻って来た。 そこは、中央に長方形のテーブルと高い背もたれのある椅子が何脚か置かれ、透かし彫りのある衝立を配した部屋で、入り口の正面の壁には、掛け軸がかかっていた。描かれているのは、菊だった。また、テーブルの上には鉢植えの菊が一つ置かれている。 「ここにも何もないってことかしらね」 小さく溜息をついて言いながら、シュラインは椅子の一つに腰を降ろした。が、その拍子につまさきで何かを蹴飛ばした感触に、彼女はテーブルの下を覗き込む。少し離れたところに、何か落ちていた。椅子から降りて、テーブルの下に潜り、それを拾い上げる。テーブルの下から出て、彼女はそれをしげしげと見やった。 それは櫛だった。それも、現代ではせいぜい土産物屋か何かでしか見かけないような、半月形の柘植の木でできたものだ。誰かが使っていたものなのだろうか。櫛は持ち手のあたりがわずかに黒ずんでいた。が、よく見るとそのあたりには、本来は何かの模様が彫り込まれていたらしい。 (これって……桜?) 目を近づけて、しげしげと眺めながらシュラインは呟く。その脳裏に、ふとある旋律が浮かんだ。なんの気なしに、その歌を口ずさみ、それが明治のころに流行した歌の一つであることを思い出す。 傍に歩み寄って来てシュラインの手元を、身を乗り出すようにして熱心に覗き込んでいた麗香が、その旋律に顔を上げ、目を見張る。 「それって、『青葉茂れる桜井の』よね。……懐かしい……」 「懐かしい?」 麗香の呟きに、今度はシュラインが目を見張った。 「これ、明治時代に流行った歌よ。……私は以前に人から聞いて、教えてもらったんだけど」 「え……ああ、私も祖母に聞いたのよ。昔、よく歌ってくれたから」 「ふうん」 うなずきながら、シュラインは内心に首をかしげる。年上とはいえ、自分とさほど年齢の変わらない麗香の祖母が明治生まれとは、考えにくい。 (やっぱり、麗香さん、何か変だわ) 胸に呟き、シュラインは手の中の櫛をもう一度見やる。どうしていきなり自分が明治の流行歌などを思い浮べたのかも、謎ではあった。 たしかに、最初あかずの間に閉じ込められた少女の話を聞いた時、彼女は、その部屋を探す時に、当時歌われていた歌を口ずさんでみれば、何か反応があるかもしれないと考えた。だが、『青葉茂れる桜井の』というこの歌は、同じ明治時代ではあっても、日露戦争よりは幾分前の流行歌だったと記憶している。その歌に、はたして少女が反応するのだろうか。 (まあいいわ。……そのことは、心に止めておきましょ。それに、この櫛も。もしかしたら、咲耶っていうその少女のものかもしれないし) 胸に呟き、彼女は櫛を帯の間に差し込んだ。 そうして、改めてあたりを見回し、今まで本物だとばかり思っていたテーブルの上の鉢植えの菊が作り物だということに初めて気づく。 「麗香さん、これ見て」 呼ばれて麗香も、テーブルに歩み寄った。しげしげと眺めて、目を丸くする。 「作り物ね。にしても……こんな高価そうなものを、客室に置くなんて……」 彼女が驚くのも無理はない。テーブルの上のそれは、茎と葉はエメラルド、白い花びらは象牙で作られていたのだ。 「客の少なさといい……ここまで来ると、宿というより、どこかのお屋敷ね」 シュラインが溜息と共に呟く。それへ笑って麗香が言った。 「もしかして、これがその『菊』の鍵だったりして」 「まさか」 「でも、菊には違いないわよ」 冗談めかして言う麗香に、シュラインは笑いを引っ込め、まじまじとその作り物の菊を見る。たしかに、菊には違いない。しかも、ここにある大量の菊の中では、たった一つ作り物だ。まさかと思いつつも、たしかめてみる価値はあると、彼女は胸にうなずく。 手を伸ばし、菊の花と茎の境目あたりをつかんだ。そのまま試しに引っ張ってみるが、それはびくともしなかった。そこで今度は押して見る。するとそれはわずかに沈む感じがあって、左右に回るらしい手応えがあった。彼女はためらいもなく、時計の反対回りに動かした。 途端。どこかでカチリと何かのはずれるような音と共に、火の燃えるような音がする。驚いて、二人が壁を見やると、掛け軸が燃えていた。それは、二人が呆然と見ている前で炎と化して消え、その下から破れた封印の札が張られた扉が姿を現す。 二人は思わず顔を見合わせた。が、やがてシュラインがそちらに歩み寄り、扉に手をかける。それは、かすかにきしんで開いた。 「どうやら、鍵は開いたようね」 呟いたシュラインは、扉の傍に象牙の鍵が落ちているのに気づいて、拾い上げる。ふり返ってみると、テーブルの上の作り物の菊はいつの間にかなくなり、ただ鉢だけがそこに置かれていた。 (本来の姿に戻ったってこと?) 怪訝に思いつつも、彼女は鍵を浴衣の袂に収め、麗香を促して扉の向こうへと足を踏み入れた。 【あかずの間の咲耶】 静流、麗香、汐耶、シュラインの四人が再び顔を合わせたのは、桃の花の咲き乱れる小さな庭園の中でだった。 時じく亭と菊花亭のそれぞれの離れの一室に隠されていた扉から続く通廊は、どちらもこの庭園へと続いていたのだ。そして、その咲き乱れる季節はずれの桃の花から考えて、ここはおそらく、四人が泊まっていた桃花亭の一画に違いない。他からは入ることのできない、秘密の庭園といったものなのだろう。 その庭園の中にもやはり、こじんまりとした離れが建っており、その離れの居間らしい一室には、桃の咲き乱れる谷を描いた掛け軸と、四角い鉢に珊瑚と黒檀で作られた小さな桃の木が飾られていた。ただし、木には、花ではなく実が成っている。 四人は、その部屋を見やって顔を見合わせた。おそらく、他の二つの部屋と同じ要領で鍵は開くのだろう。 汐耶が、時じく亭の離れの部屋でしたように、作り物の桃の木に手をやって、封印の力を逆転させ、解放の力と化して鍵を開けた。 途端、どこかでかすかに掛け金がはずれるような音がして、部屋全体が小さく揺れた。ふいに全員をエレベーターに乗った時のような浮遊感が襲う。 「まさか、この部屋……降りてるの?」 「そうみたいね」 室内を見回し呟くシュラインに、汐耶がうなずく。 再び、軽い振動があって、浮遊感は消えた。と、まるで風にあおられたかのように、ふわりと掛け軸がめくれ上がり、そのまま空中に溶けるようにして消える。その下からは、扉が現れた。ここのも封印の札が貼られていたらしいが、それは破れている。 「最後の鍵も開いたようですね」 静流が言って、扉を軽く押した。かすかにきしんで、それは開く。静流は、その下に落ちている珊瑚の鍵に気づいて、それを拾い上げた。 「行きましょうか」 他の三人を促して、彼は歩き出した。その後に、汐耶、シュライン、麗香の順で続く。 少し歩くと、すぐに四人は新たな扉にぶつかった。 「これが、あかずの間の扉のようね」 言ったのは、麗香だ。たしかに、そうらしい。だが、その扉には何か見るものの寒気を誘うようなものがあった。扉は、至る所呪符だらけだったのだ。 観音開きの二枚の扉の中央には、三つの鍵穴があり、その上にも封印の札が貼られている。これに関してはまだわかるが、札は中央の上下にも貼られ、更にそれぞれの扉の上にも隙間なく貼り巡らされているのだ。 いかに咲耶という少女の意志が固かったにせよ、これではまるで、魔物か悪霊をでも封じたかのようだ。 「いくら強い霊力を持っていたといっても、少女一人を閉じ込めるのに、ここまでする必要があるの? しかも、少女は自分の意志でここにこもったはずでしょ?」 思わず呟くシュラインに、汐耶と静流もうなずいた。 「そうね。まるでこれは、悪霊か何かを封じたみたいに見えるわ」 「ええ、私にもそう見えます」 言って静流が、汐耶をふり返る。 「でもこの封印、もしかして、解けかけてませんか?」 「ええ。……一部が解けて、中の者の力が、外に漏れ出しているような……そんな感じですね」 汐耶がうなずいた。 そんな二人のやりとりに、シュラインが苦笑する。 「二人ともいつの間にそんな霊能力めいたものを身につけたの?」 「いえ、そういうのじゃなくて、あそこ……札が一枚、破れてますから」 静流は生真面目に言って、扉の合わせ目の上部を指さした。たしかにそこの札だけが、真ん中から破れ、ちぎれてしまっている。それを見やってシュラインは、かすかに眉をひそめた。霊能力などないはずの彼女だったが、何か嫌な感じがする。 ふいに、三人の胸にほとんど同時に、あかずの間を開けていいのだろうかというためらいが浮かんだ。ここにたどり着くまでは、百年前の少女のたどった数奇な運命を哀れだと思い、せめて解放してやりたいと思っていたはずの彼らだ。だが今は。 まるで、そんな三人のためらいを突き崩すように。ふいに背後から、麗香が促した。 「ここまで来て、何をためらっているのよ。咲耶を解放してやるんでしょ。さ、その扉を開けて。貼られている札をはがして、鍵穴に、その鍵を差し込むのよ」 三人は、思わず顔を見合わせる。だがやがて、静流が代表するように、鍵穴の上に貼られた札に手をかけた。三枚とも、剥がす。鍵穴は、周囲をそれぞれトパーズと象牙と珊瑚で縁取りされていた。その縁取りに対応するよう鍵を穴に差し込む。 三つの鍵が次々に開けられ、最後に下部に張られていた札を剥がして、静流が扉を押すと、それは音もなく奥に向かって開いた。 四人は、その中へゆっくりと足を踏み入れる。 中は薄暗く、かび臭かった。彼らは、戸口で目が慣れるまでしばし立ち尽くす。 やがて薄闇に目が慣れると、静流、汐耶、シュラインの三人は初めて室内を見回した。部屋は、壁も床も天井も、全て朱色に塗られており、天井は高いが、全体としては狭い。中央に、ベッドが据えられており、そこに少女らしい人物が横たわっていた。 静流たち三人は、そのベッドへとそっと歩み寄る。が、横たわった人物を見下ろして、彼らは声もなく息を飲んだ。 そこに横たわっているのは、十五、六歳ぐらいの美しい少女だった。きめ細かな肌は透き通るように白く、細い眉が美しく弧を描き、長いまつげが頬に濃い影を落としている。ふっくりとした唇は、赤くみずみずしい果物を思わせる。長い黒髪はつややかで、一束だけを頭の後ろの高い位置でまとめ、あとは背に流したままだ。身に着けているのは、長い裾を持つ白い着物で、胸前で銀糸のししゅうのある帯を結び、同じく白い打ち掛けのようなものを羽織っている。明治というよりは、元禄の芸妓を思わせる衣装だが、その色のせいか、艶っぽさよりも神聖な空気が濃かった。が、それは朽ちてもほころびてもおらず、少女はただそこで、健やかな眠りをむさぼっているだけのように見えた。 この少女が、あかずの間に百年間閉じ込められたままだった咲耶なのだろうか。 三人の誰の頭にも、そんな疑問が浮かぶ。 彼らとて、超常現象には何度も出会っているが、それにしてもこれは、いったいどう考えればいいのだろうか。 「生きているのかしら」 シュラインが、誰にともなく低く呟いた。 「わからない。でも……この子が本当に、咲耶なの?」 汐耶も、小さくかぶりをふって、やはり呟くように問い返す。 「麗香さん、あなたはどう思いますか?」 静流が、意見を求めて、一人戸口から動こうとしない麗香をふり返った。シュラインと汐耶もそちらを見やる。 と、麗香の口元が奇妙な形にゆがんだ。 「どうって、決まっているわ。生きているわよ。……だから、あなたたちをここへ呼んだんですもの」 「麗香さん?」 シュラインが、怪訝な声を上げる。麗香の口調は、何か変だ。 その彼女と汐耶、静流の目の前で、麗香の輪郭はふいに崩れた。色を失い、それは白い雲のような塊となる。そして、驚愕に目を見張る三人を尻目に、ベッドに横たわっている少女の口の中へと、それは吸い込まれて行った。 「エクトプラズム……!」 シュラインが、思わず声を上げる。 それは、霊媒師が心霊相談の相手の死んだ家族などの姿を取らせて、会話させるのに用いる霊的媒体のようなものだった。 (麗香さんが変だったのは、本物じゃなかったからね) シュラインは、改めてそう納得する。 それが完全に口の中に吸い込まれると、少女はふいに目を開けた。ぎょっとして思わず三人が身を引くのへ、にっと笑いかける。身を起こし、身軽な動作でベッドから少女は降りた。 「私が咲耶だ。よくぞこの部屋の封印を解いてくれた。そなたらには礼を言うぞ」 尊大な口調で言って、三人を眺めやり、咲耶と名乗った少女は再び口元に笑みを浮べる。 「ついでに、そなたらには、私の起き抜けの食糧となってもらおう」 「なっ……!」 思いもしない言葉に驚く三人を、再び彼女は睥睨した。その目が赤い光を放ち始め、ふっくりとした愛らしい唇が、ストローをくわえた時のようにすぼめられる。 途端。 「な、何……?」 「体から、力が……!」 「いったい、どうして……!」 シュライン、汐耶、静流――三人の口からほぼ同時に驚愕の叫びが漏れ、その体が力なくその場に崩れ折れて行く。手にも足にも力が入らず、頭を上げると眩暈がした。まるで、長時間激しい運動を続けた後か、空気の薄い高地に一気にエレベーターで連れて行かれていきなり放り出されたかしたかのようだ。 ぐったりと床に力なくうずくまる三人を見下ろして、咲耶は笑った。 「苦しいか? さもあろう。今、そなたらの体に宿る命の炎を、私がこうして吸っておるゆえの。私が吸い尽くせば、そなたらは死ぬことになる。が、安心いたせ。死した後は、私が術を施して、生ける死人とし、下僕として使こうてやろうほどに」 「くっ……! 冗談じゃ……ないわ……!」 シュラインが歯を食いしばり、なんとか身を起こそうとしながら、低くうめくような叫びを上げる。 「なんで……私が、そんなものに……ならなきゃいけないのよ……!」 「同感ね。……温泉に骨休めに来て……死ぬなんて……笑い話にもならない……」 「私も……同感です……」 汐耶と静流も、やはりどうにか身を起こそうとしつつ、うめくように言った。 「封印を解いて、私を助けようなどと考える輩(やから)だけあって、さすがにしぶといの。だが、所詮はただの人間であるそなたらが、この私にかなうはずがないのだ。諦めて、私の力となるがいい」 三人を見下ろし、口元をゆがめて変わらず尊大に咲耶は吐き捨てる。そして再び、朱唇を小さくすぼめた。 「あっ……!」 必死に体勢を立て直そうとしていた汐耶の腕が崩れ、彼女は床に身を伏せた。シュラインも、静流も次々と床に倒れて行く。対して咲耶の頬はやわらかく紅が射し、目は更に赤く禍々しい輝きを増した。 その時だ。 「咲耶! もうやめてっ!」 室内に、ふいに鋭い叫び声が響いた。咲耶は、小さく身を震わせてそちらをふり返り、シュライン、汐耶、静流の三人もどうにか頭を上げて、朦朧とした目で声のした方を見やる。 その視線の先――戸口には、蓬莱が立っていた。 ここまで走って来たのだろうか。肩を小さく喘がせながら、ただ真っ直ぐに咲耶を見据えている。 その姿に、咲耶はわずかに顔をしかめた。赤く燃える瞳で、蓬莱を睨み据える。 「私の邪魔をしに来たか。……だが、もう遅い。この部屋の封印なくば、私をこの地に捕えることは誰にもできぬ。ましてや、おまえになど」 「それでも……それでも、私は言うわ。もうやめて、咲耶。その人たちは、なんの関係もないのよ。そして、あなたの村はもうないわ。あなたにひどいことをした村人たちも、みんな死んでしまった。復讐の意味も、もうないわ」 蓬莱はしかし、視線をそらすことなく咲耶の目を受け止め、穏やかで真摯な口調で言った。それへ咲耶は、禍々しく笑って返す。 「そうかもしれぬ。だがそれでも、私の胸は癒えぬ。両親を、愛してくれたばばさまを殺され、私自身もまた殺されそうになったその苦しみ、悲しみ、怒り。その全てを拭い去るためには……何も知らず、のうのうとくらす者どもに同じ思いを味あわせてやる以外、すべはない」 「そんな……! あなたはまた、百年前と同じことを繰り返すつもりなの? そうやって、関係のない人々まであやめて、またこの地に封じられる方がいいと……!」 蓬莱は、聞くなり目を見張り、半ば絶望したように叫んだ。 「いいや。今度は、私は封じられたりはせぬ。……ここにはもはや、そのような力を持つ者はおらぬ。違うか?」 咲耶はかぶりをふり、嬉々とした顔で言う。途端、蓬莱の色をなくした面に、更に驚愕と絶望が刻まれた。 二人のやりとりに、シュラインはそっと身を起こした。咲耶が蓬莱に気を取られているせいか、幾分体のだるさがましになっていた。そっと汐耶と静流の方を伺うと、彼らも同じく、動けるようになったようだ。 それを確認し、彼女は再び咲耶と蓬莱に視線を戻す。 どうやら、彼女たち三人が麗香の姿をしたエクトプラズムから聞かされた話は、嘘だったようだ。おそらく、彼女たちにあかずの間を見つけさせ、封印を解かせるためのものだったのだろう。ここの扉の前にたどり着いた時、扉の上部の札がはずれていたが、エクトプラズムは、その隙間を縫って外に出したものだったのかもしれない。 ともあれ、咲耶をこのままここから出せば、とんでもないことになりそうだ。むろん、それ以前に自分たちの命も危ない。 (なんとかして、咲耶を封じないと……) シュラインは、なんとか立ち上がろうともがきながら、胸に呟いた。 それと同じことを、汐耶も思う。もとより、彼女には封印能力がある。だがしかし、今のこの自分の体を動かすことすらままならない状態では、その能力も発揮できるとは思えなかった。ましてや、この部屋に再び封じ直すためには、自分たち全員が咲耶を残してこの部屋から出る必要がある。が、そんな隙が作れるのだろうか。 そしてまた静流も、二人と同じことを思う。 そんな彼らの思いを代弁するかのように。蓬莱が、色をなくし驚愕と絶望を刻んだ顔を上げ、言った。 「いいえ、います。……あなたも、それを知っているはず。だから、その人の生命力を吸い尽くし、他のお二人ともども生ける死人と化して下僕にしようとしたのでしょう? そうしたら、二度と自分は他人から封じられる心配もなく、むしろ邪魔な者を封じることさえできると」 「黙れ!」 それは図星だったのか、咲耶の顔が一瞬にして朱に染まる。だが彼女は、もはやシュライン、汐耶、静流の三人が動けるとも、いまだ自分を封印することを諦めてもいないのだとも、思ってはいなかった。口元を小さくゆがめて彼女は吐き捨てる。 「おまえの命の炎も、こやつらと共に、吸い尽くしてくれるわ!」 そして、再び唇をすぼめようとした。 その時だ。ふいに室内に、朗々とした歌声が響き渡った。 咲耶が小さく息を飲み、動きを止める。その目は驚きに大きく見張られていた。いや、彼女だけではない。蓬莱も、汐耶も静流も、驚きに目を丸くして、そちらを見やっていた。 歌っているのは、シュラインだ。床の上に座り込み、天井を仰ぐようにして、澄んだ声で朗々と。曲は、『青葉茂れる桜井の』である。明治時代の流行歌だが、平成の人間の耳には、軍歌のようにも聞こえるそのメロディを、彼女は切々と優しい調子で歌っている。 「その曲は……」 咲耶の口から、低い呟きが漏れた。その目から、禍々しい赤い光が静かに消え、優しい黒い瞳が現れる。彼女はまるで、何かに操られるように、シュラインの方へと歩み寄った。 シュラインは、歌いやめるとその彼女の方に、帯の間に挟んであった柘植の櫛を抜いて差し出した。 「これ、あなたのでしょ?」 「あ……」 咲耶は目を見張り、シュラインの手の中の櫛を見詰める。 「菊花亭の離れの部屋に落ちてたの。私がこれを見つけた時、エクトプラズムの麗香さんは、ずいぶん熱心にこれを見ていたわ。そして、あの歌を私が口ずさんだら、『懐かしい』って言ったのよ。今になって、わかった。あれは、あなただったのよね?」 シュラインは言って、櫛を取るように促した。 咲耶は、そっとそれを取り上げる。そして、さっきシュラインが歌った『青葉茂れる桜井の』を小さく口ずさんだ。その目から、涙がころがり落ちる。 「この櫛は、母の形見……。ばばさまが、幼い私の髪をこれで梳きながら、よく母の話をしてくれた。ばばさまは、いろんなことを知っていた。薬草のこと、古い言い伝えのこと、天候を見るすべや、上手に作物を育てるすべまで。そんな話の合間に、あの歌を歌ってくれた。私は、そんなばばさまが大好きだった……」 低く呟き、彼女は手の中の櫛を握りしめる。そうして、しばらくの間、涙を流し続けていたが、やがてふと顔を上げた。涙に濡れた目で、真っ直ぐに汐耶を見詰める。 「そなた、私をこの櫛に封じてくれぬか。……私は、人の身に生まれながら、もはや人ではなくなってしまった。どのような高僧であろうとも、私を人の仏が行く場所へ送ることはできまい。かというて、またこの場に封じられるは嫌だ。ここで、また百年封じられて過ごせば、また憎しみが大きくなろう。だが、今ならばよい。今、この母の形見の、ばばさまの思い出の残る櫛に封じられるならば、私は承服できる」 穏やかな言葉だった。その目もまた澄んで、どこか安らかとさえ言っていいものをたたえている。 汐耶は、それに気づいてうなずいた。まだ力の入らない足をどうにか踏みしめ、立ち上がる。咲耶の傍に、歩み寄った。咲耶が、目を閉じる。汐耶は、その額に片手を、櫛にもう一方の手を添えると、封印の力を発動した。 一瞬、咲耶の体が白い光に包まれた。が、すぐに光と共にその姿は消え、汐耶の手の中にはただ、柘植の櫛だけが残された。 【エピローグ】 その日の夕食後。 静流と汐耶、シュラインの三人は、桃花亭の玄関傍にあるロビーで蓬莱から咲耶にまつわる話を聞かされた。 彼らが最初に碇麗香の姿のエクトプラズムから聞かされた話には、嘘と真実が入り混じっていたのだ。 咲耶が、百年前、この近くの小さな村で生まれ育ち、その霊力で村の助けになっていたのは、本当だった。だが村人は、必要以上にその力を恐れ、生まれた時には彼女を殺そうとまでしていた。彼女の両親は、そんな村人から娘を守ろうとして死んだのだった。 村人は、咲耶の両親を死なせてしまった罪の意識から、祖母が彼女を育てることを黙認した。また、彼女の祖母は物知りで村人たちからは重宝されていたこともあって、この人が育てるならばと誰もが思ったらしい。 だが、日露戦争が始まった年の夏、集中豪雨のために村は半壊した。村人はその咎(とが)を咲耶に向け、更に彼女を育てたその祖母へも向けた。やがて村人によって咲耶の祖母はリンチ同然に殺され、咲耶もまた人柱にされそうになって、村から逃げ出したのだという。 「――この蓬莱館へたどり着いた時、彼女はすでに追って来た村人をその霊力であやめていました。祖母を殺され、両親の死の真相を知って、怒りと憎しみに霊力は暴走し、それまでの彼女にはなかった力を生み出していたようでした」 蓬莱は、静流たち三人の前に座し、幾分うなだれて語る。 「そして、たどり着いたここでも、彼女は何人かのお客様をあやめました。お客様の中には、霊力のある方もおいででしたので……彼女は、そういう方をあやめることで、相手の力を取り込んで更に霊力を増し、そのことに慢心しました。ですが幸い、綾和泉様と同じ、封印の能力を持つお坊様がお客様の中におりまして、その方が、あの部屋に咲耶を封じて下さったのです」 「じゃあ、もしもその人がいなかったら……」 「はい。その時にこの蓬莱館にいたお客様は全て、咲耶に命を奪われ、彼女は膨大な霊力を身に着けて、東京……いえ、日本を血の海に変えていたかもしれません」 軽く目を見張って言うシュラインに、うなずいて蓬莱は言った。 「あの……一つ気になったのですけれど、蓬莱さんは、どうして百年前のことに、そんなに詳しいんですか? あかずの間で、咲耶にも言ってましたよね? 『また百年前と同じことを繰り返すのか』って」 汐耶が、軽く挙手の仕草をして問う。 「百年前にも、私はここに……この蓬莱館にいたからです」 蓬莱は、少しだけためらった後に言って、再び話し始めた。 「もう、お気づきかもしれませんが、私は普通の人間ではありません。……この蓬莱館は、異界なのです」 「ここが、異界?」 静流、汐耶、シュラインの三人は、思わず顔を見合わせる。異界現象は、東京だけではなかったのだと驚く一方で、それならば納得できると三人はそれぞれ思う。たとえば、季節はずれに咲き誇る花々や、蓬莱以外に従業員の姿が見えないというのに、きちんとサービスが行き届いていることなどなど。それらは、通常の世界でならあり得ないことだが、異界ならば、そこだけの別の理が働くのだから、充分あり得ることだ。 そんな三人に、蓬莱は語る。自分は、この地に異界を築くために贄(にえ)となった存在なのだと。 彼女を贄として、この地に異界・蓬莱を築いたのは、二千年前はるか中国から時の皇帝の命を受け、不老不死の仙薬を求めて三千人の男女と共に日本へやって来た徐福だった。彼はしかし、そのような仙薬などこの世にはないと察し、土地を定めて儀式を行い、自らと随行する三千人の魂を代償に、不老不死を実現する異界を生み出した。それがこの異界・蓬莱なのだった。 「――私は、その異界を存在させる核として、贄になりました。徐福様も他の者も全て肉体を失い、魂だけの存在となりましたが、私はこの異界の中心で眠り、百年に一度目覚めては、この世界を維持するための力を得るため、こうして宿を経営しています」 「つまり、この宿の他の従業員はその徐福と一緒に来た従者たちで……いわば、霊なので、我々の目には見えない、ということですか? そして、咲耶はちょうど百年前、今と同じようにあなたが目覚めてここに蓬莱館が開いたところへ、やって来たと?」 蓬莱の話に、静流が尋ねる。 「はい。……そういうことです」 うなずいて、蓬莱は言葉を続けた。 「咲耶にも、ここがなんらかの霊的空間であることは、わかっていたようです。ですから彼女は、ここで力を蓄えれば、村人に復讐ができると考えたのかもしれません。ただ、私が本当は何者なのかには、気づいていなかったようですけれど」 言葉を切って、彼女は三人に深々と頭を下げる。 「ともあれ、このたびは、お客様にご迷惑をおかけして、申し訳ありませんでした」 「いえ、そんな……。あなたのせいじゃないわ」 シュラインが、慌てて言った。 「そうですよ。それに、蓬莱さんは、私と妹尾さんが時じく亭にいた時、あかずの間探しを止めようとしたじゃないですか」 汐耶も言って、思い出したように問う。 「結局、あの離れのことを教えてくれましたけど。……あれは、どうしてだったんですか?」 「あの時、妹尾様が、時じく亭にも桃花亭にも他にお客様がいない、とおっしゃいました。それを聞いて、妹尾様と綾和泉様は、もう咲耶の術中に落ちている……と察したからです。咲耶の術に落ちたのならば、その目的が成就されねば、術は解けないだろうと」 「ああ……」 蓬莱の答えに、汐耶はあたりを見回して、小さく肩をすくめた。ロビーには、ずいぶんと人がいる。彼女たちは、庭に面したやや奥まった一画に陣取っているのだが、他にも数組のカップルや家族連れなどが、思い思いにソファや椅子に腰を降ろし、夕食後の一時を楽しんでいた。 あかずの間から桃花亭の中に戻った時三人は、いきなり大勢の客の姿を目にしてかなり面食らった。実際には、蓬莱館には大勢の客がいて、彼女たちがあかずの間探索をしているころには、更に客が増え、桃花亭だけでなく、時じく亭も菊花亭もずいぶん賑やかになっていたのだ。 おそらく、彼女たちがここに到着した時には、すでにあの封印は一部が破れ、静かに咲耶の術が宿の中に広がっていたのだろう。三人はそれに引っかかってしまったのだ。そして、それに気づいて麗香の姿のエクトプラズムが近づいて来た。そういうことなのだろう。もしかしたら、エクトプラズムを麗香の姿にしたのも、三人の共通の知人だったからかもしれない。 汐耶の視線を追って、他の客たちに目をやっていた蓬莱は、改めて三人をふり返ると口を開いた。 「……それでも、皆様を危険な目に遭わせたのは、私の責任です。百年前、咲耶を封じたお坊様にも言われていました。百年後に私が目覚め、蓬莱館がここに出現した時には、封印はその衝撃でほころびるかもしれないと。本当にそのとおりでした。ですから、私が気をつけていなければ、いけなかったのです。それを……」 言いさして、彼女は小さく唇を噛む。その肩を、静流が身を乗り出すようにして、軽く叩いた。 「蓬莱さん、どうぞ、あまり気にしないで下さい。『終わりよければ全てよし』ですよ。私たち三人は、誰も怪我もしていないし、死んでもいません。封印は解かれたけれど、咲耶は結局、更に殺戮を重ねることはなかった。そして、自らの意志で封印を受け入れたのです。あなたが気に病むことは、何もありませんよ」 「妹尾さんの言うとおりよ。ね?」 シュラインも、なだめるように蓬莱に微笑みかける。汐耶も黙ってうなずいた。 「皆様……」 蓬莱は、そんな三人を驚いたように見やる。が、やっと笑顔になってうなずいた。 彼女の笑顔に、静流たちも安堵したように笑って顔を見合わせる。その後、ふと思い出したように、シュラインが訊いた。 「そういえば、あの櫛のことだけど……もし持っていても大丈夫のようなら、記念に私が持って帰りたいんだけど」 「そうね。もう危険はないと思うから……」 汐耶がうなずく。そして、尋ねるように蓬莱を見やった。 「綾和泉様がそうおっしゃるなら、大丈夫だと思います。むしろ、ここに置くよりは、咲耶のためにはいいかもしれません」 蓬莱も言う。 それを聞いて汐耶は、あかずの間から戻った後も、ずっと持っていた柘植の櫛を上着のポケットから取り出し、シュラインに手渡す。シュラインは、受け取ったそれに微笑みかけてから、最初していたように、浴衣の帯の間に挟んだ。 そのやりとりを見やって、静流が蓬莱をふり返った。 「ところで、麗香さんは、どうしましたか?」 「碇様は、まだおいでになっていません。今朝早くにお電話があって、到着は夜になるとか」 答えて蓬莱は、ふいにまるで誰かに呼ばれたかのように、ロビーの入り口をふり返る。そして、破顔した。 「どうやら、お着きになったようです」 言って立ち上がり、彼女はそのままロビーを出て行く。 その姿を視線で追って、三人は、今度こそ本物の麗香に会えると苦笑を交わす。 静流たち三人が、大荷物を抱え、なぜかよれよれになった麗香の姿を、桃花亭の玄関に見出すのは、それからしばらく後のことだった――。 □■■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■■■■■□ ■ 登場人物(この物語に登場した人物の一覧) ■ □■■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■■■■■□ 【整理番号 / PC名 / 性別 / 年齢 / 職業】 【1449 /綾和泉汐耶 /女性 /23歳 /都立図書館司書】 【0086 /シュライン・エマ /女性 /26歳 /翻訳家&幽霊作家+草間興信所事務員】 |
|
|
|
||
|
|
||
|
|
【個別ノベル】 【0086/シュライン・エマ】 【1449/綾和泉汐耶】 |
|
|
|
||
|
|