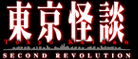 |
|
|
|
||
|
|
調査コードネーム:蓼喰う獣も、午後を 執筆ライター :モロクっち 【オープニング】 【 共通ノベル 】 【 個別ノベル 】 |
|
|
|
||
|
|
||
|
|
 【オープニング】
【オープニング】陰秘学を研究する小説家のもとを高峰沙耶が訪れ、切っ掛けがつくられた。 「ホウライカン? 温泉宿……ですか」 高峰沙耶のことを、リチャード・レイは知らなかったわけではない。知っているどころか、何度も沙耶の研究所(研究所らしからぬところだと、レイは常々思っていた)を訪れてもいるのだ。沙耶のもとをそうして何度も訪れても、いつも交わす会話は研究や依頼で得た情報の交換のためのもので、雑談らしい雑談もなかった。 だというのに、沙耶は突然レイを『蓬莱館』なる山中の温泉宿に誘ったのである。温泉宿の背後にある驚くべき古き真相も、沙耶がかいつまんで説明した。 「構いませんが、何故?」 「理由は、行けばわかるわ」 沙耶の腕の中で、猫が微笑んだようだった。 レイは、ちらりと傍らに目を送る。傍らには、黒尽くめの蔵木みさとの姿がある。 彼がいま身柄を保護している少女は、趣味の裁縫の手をすでに止めていた。彼女はあまり自己主張をしない大人しい性分だった。――が、その金の目は、期待と哀願の光に満ちていた。 「……わかりました。その温泉宿を調べて、レポートにまとめても?」 「構わないわ。むしろ、お願いしたいわね。あすこで、何かが起きなかったためしはないから」 「……その温泉宿は、100年に一度現れると仰いましたね。タカミネさん、『以前に』行ったことがおありですか」 「あの宿で起きたことを、知っているだけよ」 またしても、猫が微笑んだようだった。沙耶は最後にゆったりと微笑むと、立ち去った。沙耶の姿が見えなくなるのと同時に、みさとが口を開く。 「温泉、行くんですね? 先生」 「そうなることになりますね」 「準備します! あ、陸號さんも勿論誘いますよね?」 「えっ? 彼は――」 「呼んできます!」 「ミサトさ――」 レイの制止もむなしく、みさとは応接室を飛び出した。 そう、ここはアトラス編集部。高峰沙耶は、きっとアトラスにいる人間全員に、温泉宿蓬莱館の話を触れ回っているだろう。応接室の前に立ち尽くすつぎはぎの人造人間の耳にも、話は入っているに違いない。明治時代に生み出された人造警備員ではあるが、温泉がどういったところであるか理解出来る程度の知能は持っているし、誘えば素直についてくるだろう。意思はあるものの、主体性は皆無なのだ。 「……彼には、防水加工が成されていないのですよ……」 ほんとうに、レイの制止はむなしいものだった。 3年ぶりの休暇をとった碇麗香、そして高峰沙耶が富士の裾野に向かった日―― リチャード・レイと蔵木みさと、温泉には入れない身体の人造人間『芹沢式』陸號もまた、富士の昼なお暗い森の中に分け入っていた。 「温泉なんて……初めてだなぁ。あたしでも、あったまれるかなぁ」 「自分は お部屋の 留守を 預かります」 「えっ?! 陸號さん、入らないの?!」 「長時間の 潜水は 皮膚 及び 内部機構に 異常を きたす 原因と なります」 「ですから、ロクゴウさんには防水加工が成されていないと何度も……」 「……先生、入りますよね?」 「いえ、わたしはこの宿について調べなければなりませんので」 「……ひとりかぁ。つまんないなぁ」 けん、とみさとは足元の白い石を蹴飛ばした。不可思議なほどに白いその石は、濃緑の茂みの中に消えた。 みさととレイが先に蓬莱館の中に入っても、つぎはぎだらけの警備員は、ぴたりと入口の前で足を止めたきり動かなかった。硝子の眼球が、濃緑の茂みを見つめていた。 客間に通され、蓬莱館の第一印象から逐一レポートにまとめているレイ、ぱたぱたと広い客間を見て回っているみさとのもとに、陸號が来た。戻って来た、と言うべきなのか。 「……ロクゴウさん、それは?」 「……陸號さん、それなに?」 レイとみさとは目を点にして、陸號が抱えているものを見つめ、困惑しながら問い質す。 「不明 です」 ぎし、と陸號が首をかしげた。 彼が抱えているものは、かたかたと震える卵型の白い石であるようだった。 【ライターより】 どんな内容になるかは、ほぼPCさまにお任せです。ただし、こんなオープニングでは想像もつきにくいところですが、戦闘があります(笑)。例によってほんのりクトゥルフテイスト。けれども、主にNPCとともに温泉宿 「蓬莱館」での一夜を楽しんでいただくというかたちになります。コメディチックな部分とシリアスな部分のギャップはスゴイものがありましょうが、それをも楽しんでいただければ幸いです。 ご参加、お待ちしております。 |
|
|
|
||
|
|
||
|
|
【共通ノベル】 ■赤い道しるべ■ 『与護栖の間』の襖がビシャーンと開き、赤い飛沫を撒き散らしながら、ひとりの男子大学生が飛び出した。彼はものも言わずに襖の前にいた男女を押し退け、ついには「うおおおお」などという雄叫びを上げながら、いずこかに走り去っていった。 「……何じゃ、ありゃ?」 「一緒に仕事したことあるじゃない。確か山岡風太クン」 「いやそりゃ知ってるよ。俺はあの振る舞いが疑問なの。……鼻血出てたぞ」 「あたしに聞かないでよ……。何が起きたかは、訊けばいいわ」 しっかり『蓬莱館』オリジナルの浴衣を着込んだ男女は、藍原和馬と田中緋玻。幸い、飛び出してきた山岡風太と云う学生の鼻血は、その白地の浴衣についてはいなかった。 「風太さん?!」 開きっぱなしの襖の奥から現れたのは、青褪めた肌と金の眼の少女。癖毛は、きれいだが簡素に結い上げられている。心配そうに飛び出してきた彼女も、緋玻と和馬の姿を見て、たちまち笑顔になった。 いつもの黒いレインコートやゴム長靴、黒手袋姿ではなかった。彼女もしっかり白地の浴衣を着ていたのだ。その色合いは、確か入口の浴衣引渡し所で、「女性用五番」と番号が振られていたものだ。緋玻は知っていたし、何故か和馬も知っていた。 「おお、新鮮」 「あら、似合うじゃない」 「着付けの仕上げは武神さんにしていただきました! 髪の毛やってくれたのは九尾さんです!」 いつもは黒尽くめの蔵木みさとが、満面の笑みでぴょこりと跳ねた。 「……でも、そんなに肌出しちゃって、大丈夫なのか? 光はダメなんだろ?」 「それなら、心配ないようだ」 和馬の疑問に、襖の向こうの声が答えた。 『与護栖の間』から現れたのは、その浴衣の着付けを手伝ったという、浴衣が似合う男だった。いつでも和装の彼は、武神一樹。和装と同じ属性の『和装』でありながら、白地に青藤色の浴衣は彼にいつもとは違う印象を与えるのだった。 おや、どうも――と、一樹の後ろからしずかに顔を出したのが、これまたいつもとは違うたたずまいの男。バーテンダーの格好でもなく、黒コートを羽織ってもいない。それが一樹やレイの友人である九尾桐伯であることに気づくのに、少し時間がかかるほど――浴衣は、彼の様相を変えた。 「何でもこの宿は特別な処らしくてな。配っているこの浴衣も特別製らしい。出迎えてくれた不思議な女の子がいただろう? あの子が説明してくれた」 「身体に悪い影響がでるものは何でもはね返すそうです。9ミリパラベラムもグレネードの衝撃波も瘴気さえも」 「はア?!」 「あー、謎が解けたわ。さっきの学生くん……みさとちゃんの浴衣姿に殺られたのね」 緋玻が苦笑すると、みさとの表情がさっと変わった。 「あっ、そうだった! 風太さん! ……あたし見たらいきなり飛び出していっちゃって……探しに行ってきます!」 「ああ、よせよせ! その格好で『きゃハ、風太さハーんん』なんて駆け寄ったら、あいつ出血多量で死んじまうぞ」 「な、なんでですか?!」 「男だからだ!」 「行かせてやりなさいよ」 「そうだな、行かせてやれ。青春ってやつだ」 一樹と緋玻に説得され、和馬はぱっとみさとの腕から手を離した。みさとは短く一行にことわってから、嬉しそうにぱたぱたと走り出した。風太を追うのは簡単だ。床に点々と残る血は、パンの道しるべと同じ役割を果たしていたから。 「青春ね」 「青春だな」 「うむ、青春だ」 「ええ、青春です」 「……くだらん」 ぱ・ちん。 『与護巣の間』の片隅で、どうにも覇気のない陰口を叩いたのは、『男性用三番』の浴衣をきっちり着込んだ軍司郎だった。この客間にはいたずらに人が多いのだが、談笑からは一歩も二歩も引いたところで、黙々と詰め将棋を嗜んでいる。いつも気難しい表情の彼ではあるが、この日は輪をかけて厳めしい顔つきになっていた。彼がここに居て、この浴衣を着ているのは、彼にとってはかなり不本意なのだ。 そんな一言にちらりと灰の眼を動かしたのは、いつの間にやら白地に浅葱の浴衣に着替え(させられ)たリチャード・レイ。 「……お相手しましょうか」 「チェスではないぞ」 ぱ・ちん。 「どういうわけかチェス盤もあります」 「チェスはわたしが知らないのだ」 ぱ・ちん。 「どういうわけか絶版のテーブルトークRPGもあります」 ぱ…… 「……」 「……」 「……キーパーの役目は貴君が負うのだろうな?」 「シナリオのネタにならば事欠きませんから」 「……」 さらにそのふたりを正座した体勢で無言で見つめているのは、いつの間にやら黒地に赤蘇芳の浴衣に着替え(させられ)た人造警備員録號。彼は浴衣に着替えても、何故か警帽をかぶったままだった。しかも、かたかた震える卵じみたものを抱えている。 へんだった。 ■悪夢のような夢がはじまる■ 「そこで正気度チェックですね」 「なに?」 「1D100です。さ、どうぞ」 「待て、足元を見ただけだ」 「そこに闇の跳梁者が潜んでいたわけです」 「理不尽だな」 「理不尽なものなのです。さ、どうぞ」 「……賽がなくなった」 「なくなった? あ!」 「こっちに逃げてきたぞ、ダイスが自分で」 「大人気ないぞカゲヤマ!」 「その台詞、貴君にそっくり返してやろう」 「レイさん、このお宿の調査はどうなりました?」 桐伯の尤もな問いかけに、ぴくりとレイが振り向いた。 桐伯は何故か微笑んでいる。それも悪戯っぽく。桐伯の言葉を聞き取って、温泉談義していた一樹と緋玻もレイを見た。和馬は――ケタケタ笑う10面ダイスを2個、睨むようにして観察しているところだ。 レイがルールブックを閉じて溜息をついた。 「いや、忘れていたわけではないのですが」 「では、温泉に行きましょう」 「遠慮させていただきま……」 「まあまあ、そう言うな。旨い酒があるらしいんだ。露天風呂で一献やろう。なあ、九尾」 「ええ。どうも、この温泉というシチュエーションにはデジャ・ヴュのようなものを感じましてね。そして何故か、レイさんには『今度こそ』露天風呂に入っていただかなくてはという気がするのです」 「奇遇だな、俺もだ」 「あの――ちょっ……」 「ごはん食べる気分じゃないし、あたしもとりあえず入るわ。藍原さんは?」 「行くー」 笑うダイスを放り投げた和馬は立ち上がり、無言でいる陸號と、同じく無言の軍司郎を見やった。軍司郎はすでに詰め将棋を再開しているし、陸號はちゃんと卵の管理という皆からのおねがいをまっとうしてくれる様子だ。 「じゃ、フロから上がってきたらその卵調べっから。うっかりなお方に代わって見張り頼むわ」 「ご心配 なく」 わずかに唇の端を持ち上げて、陸號が奇妙なほど頼もしい返事をした。 リチャード・レイはすでに、毛を剃られた猿の如く、ふたりの男に両腕を掴まれて『与護栖の間』を連れ出されていた。 『与護栖の間』を誰よりも先に飛び出した山岡風太の凄まじい鼻血は、蓬莱館の廊下を点々と汚したのだが、程なくしておさまった。 「こ、興奮して鼻血なんて……中学生かよ、俺」 鼻を拭った手の甲についた血は、すでに固まり始めている。それから彼はようやく、白地の浴衣や、檸檬色の帯が血で汚れてしまったことに気がついた。借り物だということは頭にあるので、風太は後ろめたさに頭をかいた。 「大丈夫ですか?」 不意にかけられた少女の声に、ぎくりとして風太は振り向く。 そこに立っていたのは、この蓬莱館に入ったときに自分たちを出迎えてくれた、桃色の髪の少女だった。確か、蓬莱、と名乗った。この温泉宿の女将のようなものだとも言って笑っていた。 今はその笑顔がない。どこか、焦っているように風太には見えた。それを詮索するほど、いまの風太に余裕が無かったのは、不幸なことだったかもしれない。 「ああ……ケガしたわけじゃないんだ。浴衣、汚しちゃった。ごめん」 「替えのもの、脱衣所の前にたくさんあります。どうぞお気になさらずに、お着替えになって下さい」 「そ、そう。どうもありがとう」 「じゃ、私、ちょっと用事がありますので……ごめんなさい、慌しくて」 蓬莱はぺこりと頭を下げ、ぱたぱたと廊下を駆けていった。 桃色のその後ろ姿を見送ってから、ふと風太は周囲を見回し、首を傾げる。 広い温泉宿だ。そこかしこに案内板が表示されているので、それに従えば迷うこともないだろうが――従業員は、あの蓬莱だけなのだろうか。いや、そう疑問に思う以前に、そうでしかありえないとも考えてしまう。高峰沙耶の話を聞いて訪れている者も確かにいて、ちらほらとその姿を見かけるが、宿の関係者には一切出くわさないのだった。 廊下を掃除している者も、何かを運んでいる者もない。 それでも――風太が、耳をすませると―― 聞こえてくるわけではないのだが、 聞こえてくるような気がするのだ。 ここで働いている者たちの声や、立てる音が。 「……不思議なとこだなあ」 「ほんとに、そうですよね」 相変わらず、黒髪のその少女には気配がなかった。風太は驚いたが、みさとが来てくれたのは、正直嬉しくもあった。 「鼻血のあと、辿ってきました」 みさとは良質の漫才をみたときのような笑顔だ。 「きっと、先生とか皆さんも温泉に入ると思うんです。風太さんもどうですか? ……鼻血出たばっかりだから、無理です?」 「い、いや、もう大丈夫。露天風呂あるんだっけ? 俺も入るよ」 「よかった。……あ、混浴だったらどうしますか?」 みさとの無邪気な冗談に、 風太はまた鼻血を噴いた。 ■香の湯■ いつもは何事にも何人にも冷めていて、きつい言動もデフォルトである緋玻がにこにこしている。レイとともにこの温泉を訪れた一行の中では、女性は緋玻とみさとだけだった。 「こういうところの温泉ってまず混浴って感じだけど、ちゃんと仕切ってあるのね」 「男湯の方は大変みたいでしたね」 拉致されるイギリス人保護者と、いきなり鼻血を噴く青年の姿を思い浮かべて、みさとが噴き出した。 緋玻はみさとの肌に視線を滑らせた。 見たことがある肌だ。つめたく変色し、紫色の血管がうっすらと皮膚の上に浮き上がって見える。地獄の底で苦しむ死者のものだった。 「じゃ、じっくり温まっていきましょ」 死者の肌には何も触れずに、緋玻はがらりと露天風呂に通じる戸を開けた。 「わ、いい匂い!」 ふわりと脱衣所に流れてくるのは、確かに、ふくよかな香りであったのだ。 「なに……? 硫黄の臭いなんてちっともしない……嗅いだことないわ。結構な数の温泉に入ってきたつもりだったけれど」 緋玻は香りを吸いこんでから、ふと笑みとともに漏らした。 「ああ、浄土の温泉には行ったことがないわね。ひょっとしたら、この匂いは浄土のものなのかしら?」 すでに、石造りの湯船には先客がいた。温泉に入っていてもなお、黒猫ゼーエンを抱いた高峰沙耶だ。 「ふふふ……やっぱり、皆最初に露天風呂に入るのね」 沙耶がしなやかな腕を湯から出し――湯は、うっすらと桜色を帯びた白い濁り湯だった――緋玻とみさとを手招きした。 「いいお湯よ。堪能するといいわ」 「ええ」 「次に入れるのは、100年後だから」 「……え?」 みさとと緋玻が、同時に沙耶に訊き返す。沙耶は相変わらず、何もかもに余裕を持っているかのような微笑みを浮かべていた。 「あらあら、レイさんはまだ何も貴方たちに話していないのね」 「調べがいのある温泉宿だとは言ってたけど――」 緋玻は湯につかり、思わず言葉を切った。 濁り湯の加減は、本当に極楽浄土を模しているかのような素晴らしさだったからだ。 「尤も、知らない方がいい真実もあるけれど」 「沙耶さんは、全部知ってるんですね」 「貴方たちが望むなら、今ここでのぼせるまでこの温泉での出来事を話してあげることも出来るわ」 「遠慮しとく」 緋玻が苦笑し、みさとと顔を見合せた。 「ゆっくり静かにつかっていたいお湯よ。それに、真実は自分で調べて、それでわかる範囲のものだけ知れば充分。でないと、つまらなくなるから」 「緋玻さんと同じです。……でも、ちょっとだけ、聞きたいかな」 みさとははにかんで唇を噛み、指で「ちょっとだけ」を示してみせた。沙耶は頷いた。 「それなら、ちょっとだけ話すわ」 黒猫が、目を細めた。 「覗くなよ、藍原」 「な、俺が覗きするような雑魚に見えるのか?!」 「そうだったらどうする?」 「傷つく」 「もうだいぶ傷つけられているような……」 「ああ、仕切りつきでよかった。混浴だったら俺、失血死してたかも」 「鼻血出たばっかりの身体で温泉入るのはかなり無鉄砲だぞ」 「あの、ですからなぜわたしが温泉などに……」 「レイさん、ほんとその刺青すっごいですねえ」 「いえ、これはタトゥーではなくて……」 「うあーコイツ呪われてるよー、コレとかコレとか『ネクロノミコン』で見たぞー」 「つつくな! たわけ!」 「殴んなよ! 八兵衛の癖に!」 「喧嘩はやめて下さい、こんなにいいお湯なのに。ああ、このお宿のお酒はかなりいい味ですよ。お二人とも是非お召し上がり下さい」 「『蓬莱』か……土産もので売ってないのか、これは」 「あが、は、はなぢがまた……」 「あ、風太さん、『蓬莱』を呑みましたね?」 「上向け」 「いえ、鼻血が出たときはまず下を向いて……」 「くそ八兵衛!」 「野犬めが、角の猟犬に喰われるがいい!」 「おや、レイさん、そのまま動かないで下さい。うっかりを治せるツボがいい角度で……」 「な、何をする気ですかキュウビさん!」 「針ですよ、みさとさんのたってのお願いでしてね」 「おお、そんなツボあんの?」 「あるんです」 「よし、やれ九尾!」 「触らないで下さいタケガミさん!」 「すみませんね、鍼がないので鋼糸で代用を――」 「貴様ら全員アザトースに呪われろ!!」 「……くだらん」 「――影山、いつの間に……」 女湯での想像通り、男湯は大変なことになっていた。 ■裏■ 「大変だ……どうしよう……どこに行っちゃったんだろう……」 桃色の髪と衣服の主は、ぱたぱたと宿の中を駆けずり回っていた。 聞こえないようで聞こえるざわめきは、大きくなってきている。蓬莱の焦りが大きくなるにつれ、ざわめきと気配も膨張しているようだった。 「……私たちの、神様……」 蓬莱は、ふと立ち止まる。 自分の手を見て、愕然とする。 彼女の白い手のひらに、かさかさとした乾いたささくれが目立ち始めている。 ばきっ! 不意に館の梁が大きく軋んで、そう鳴いた。 「早く、早くみつけなくちゃ……!」 ■留守番■ ぴしっ、とかすかな音がした。 1時間前から全く姿勢を変えずに座っていた人造人間が、ゆっくりと音の出所を見つめる。 ぴしっ、と再び呟いたのは、間違いなく、彼が守っている白い卵のようなものだった。 「異常事態 発生 かな」 彼が独り言を呟くこともあるということを、知る者はまだない。 ■異常事態 発生 かも■ 酒と湯とちょっかいが織り成す喧騒とは一歩引いたところで、「まあせっかくだから」というような気持ちから湯につかっていた軍司郎が、ふと顔を上げた。 「……?」 目に見えて何が変わったということもない。 だが、確実に何かが変わろうとしている。 桜と梅のそよ風の中に、一糸の木枯らしが混じったような、奇妙な感覚を覚えたのだ。 「ほら、呑め呑めリチャード! 風太のやつがダウンしたんだ。責任持って全部いけ!」 「何故わたしに責任があるのですか?!」 「はは、武神さん、お酒の無理強いはいけませんよ」 「って言いながらアンタはがいじめにしてんじゃないの、八を」 「なんかしゅっけつたりょーでしにそ……」 「なら上がれー!」 「あー、あっついっす……」 軍司郎がちらりと視線を送った先では、おそらくこの変化の前触れのようなものに気づいていない(気づくどころではない)5人の男。 いや、楽しむのは個人の自由だし、旅行先でむっつり黙って過ごすというのはまず少し常識からは外れていることだから、頭ごなしにけなすつもりも軍司郎にはなかった。 それに、楽しんでいれば気づかないひずみに気づかないことは、罪だろうか。 「……そうか」 鼻血が止まりかけた風太が何気なく漏らした一言、「あっついっす」。 濁った薄桃色の湯は、確かに温度が上がっているようだ。入ったときは、ひどく心地いい頃合の温度であったはずなのだが――。 おい、そろそろ食事だろう。 そう一行に声をかけてから湯を出ようかと思った軍司郎だが、……結局無言で先に露天風呂を後にしていた。 「緋玻さん、なんか……」 「ええ」 女湯の方でも、酒も笑い話も入っていなかった緋玻とみさとが、かすかな兆しに気づいたところだった。 沙耶から、一通りの話は聞いている。 「蓬莱が何か困っていたら、力を貸すわ。あなたはどうせいつものように何もしてくれないんでしょう?」 「そうかもしれないわね」 「……あたしは、100年後にまたこのお湯に入りたい。だったら出来ることをするだけよ」 「頼もしいわ」 「……みさとちゃん、上がりましょう。何もしないでいたら、ごはんは返上かも。それだけは勘弁だわ。お湯がいいところは食事もいい、ってね」 「はい!」 夕食どころか、楽しい旅行の夜も台無しになってしまう。 ふたりは、明らかに温度が上がり始めた湯から上がった。 珍酒『蓬莱』は、泡盛のようで米酒のよう、辛口かと思いきや甘口のような気もする、不思議な酒だった。どちらかと言えばきつめの酒だったことだけは間違いない。5人の男は揃ってその『蓬莱』に脳髄をやられかけていたが、一樹と桐伯は湯の変化に気づいたし、和馬は匂いの微妙な変化に気がついた。 その3人がわずかに顔色に翳りを見せたとき、濡れ髪に浴衣の緋玻が、いきなり男湯の戸を開けて姿を見せたのである。 「ぉわ?!」 5人の男は妙な声を上げた。 「あなたたち、もう上がりなさいよ。ごはんの前にやらなくちゃいけないことがあるかもしれないんだから」 「お湯も滴るいい女……」 にや、と嬉しげに牙を見せた和馬に、かっぽーんと手桶が命中した。無論、緋玻が投げたものだった。 「この湯宿は、異界なのよ。知ってるでしょ? 並行世界のひとつってわけ。この中にいる限り、ありとあらゆるものが不老不死なの。 でもその存在を維持するのに、どこかの次元の神様の力と、能力者の『徳』が必要なんですって。 力を蓄えるために、この湯宿は100年に一度、あたしたちの世界と重なり合うの。 100年に一度目覚める神様に、『徳』を捧げなくちゃならないのよ」 「別の次元の神様か。何やら雲行きが怪しくなってきたな」 「ええ、本当に。――次の100年が思いやられます」 「でも……神様なんて、どこにいるんだ?」 「う、なんか俺、ちょっと気分が……」 『蓬莱館』は、明らかに歪み始めていた。案内表示板の矢印が、天井や床を指していたりする。障子の格子は、奇妙な幾何学模様に変化していた。 漂う匂いに和馬と桐伯が顔をしかめ始めた。 「湯の中に10日間突っ込まれたホトケさんの臭いがするよ……」 「栓をするのを忘れてしまったワインの臭いでもあります」 桐伯はそして、鬱々たる少女の声を、軋みの中に聞き取った。 彼が探そうとしていた伝説が、声の中にある。 ■望まれない孵化■ 『ああ……ああ、今までに保ってきたこの姿が変わってしまうの。それが運命だというのなら仕方ないけれど……ああ、私たちは、このままでずっといたかった……』 陰鬱な声は、蓬莱のものだ。 今や音を立てて変化を続ける蓬莱館の中を、一行は駆け抜け、『与語栖の間』に辿りついた。道のりは、明らかに行きよりも長くなっていた。 「遅かったな。楽しんだか」 歪んだ襖の前には軍司郎と陸號が立っていた。何かあったか、と誰かが尋ねる前に、陸號が襖を開ける。彼の両腕には力がこもっていた。すでに人間の力では開けるのが難しいほど、敷居と鴨居がひずんでいるのだ。 「あ――」 みさとがそう声を上げたきりで、全員が言葉を失った。 一瞬中のものを見せると、陸號がすばやく襖を閉めた。 浴衣の不可思議な力が、一行の正気を保ったのか――。 『与語栖の間』を埋め尽くしていたのは、名状し難い白い神であった。 「い、今のグロゲロゲチョグチョネチャニチョはなんだ?!」 「孵化 しました」 「孵化……? あの石か!」 「与えてた『徳』で食中り起こしたんだわ」 緋玻が苦虫を噛み潰した顔になった。その顔で、ぎらっと陸號を睨みつける。 「神様の形や力で、この『蓬莱館』の姿は変わるのよ。神様が見ている夢みたいなものだもの……あのお湯、100年後にも入るって決めたんだから……何とかしないと」 「『蓬莱』も、無くすには惜しい銘酒です」 「だが、殺せばこの異界は消えてなくなるぞ」 「……消えてなくなればいい。異形の神の力を借りた宿など」 「カゲヤマさん……あのお湯が惜しいとは思いませんか?」 「……」 「あの、1回食べたもの吐いてもらって、それからまた新しく食べてもらったら……どうかな。無理ですか?」 みさとの提案に、一行は顔を見合せた。 それでいくか。 山岡風太の姿が消えていることに気がついたのはみさとだったが、もう少し後になってからのことだった。 ■ローマの晩餐■ 陸號が襖に手をかける。その硝子の目が、「いいですか」と一行の覚悟を確かめた。 レイとみさとが大人しく襖の前から下がり、人造人間はそのつぎはぎの両腕にぐっと力をこめて、勢いよく襖を開けた。 5人が『与語栖の間』に雪崩れ込むと同時に、襖はぴしゃりと閉められた。 「テケリ=リ、なんて鳴き出しそうじゃないか」 白い神を前にして、一樹は苦笑した。 テケリ=リと鳴き出しそうな一見の神は、常に脚の数を変えるヒトデのようなもので、ぐるぐると捻じ曲がりながら蠢き、天井を這いずり、壁に張りつき、或いは床を転がった。 「笛も吹き出しそうですよ」 桐伯は浴衣の袖から、いつもの鋼糸を繰り出した。生物のようにしなる糸が、神に巻きつき、動きを封じた。しかし―― 「先日やっていたでしょう。『ヒトデは 全身を縄で縛られても抜け出すことが出来る』」 「あれは取り上げられるまでもなく常識だよな、九尾」 「ええまあ」 「ぼーっとしてるだけで戦り合うつもりはないみたいだが」 和馬の言う通り、白い神はしょっちゅう目玉のようなものを作ってはきろりきろりと5人を見つめるだけで、敵意も殺意も帯びてはいない。縛られても、あまり抜け出ようとする意思がないようにも見えた。ヒトデのように、早送りにしなければわからないほど動きが緩慢というわけでもなさそうだ。 「吐かせるなら、鳩尾に一発お見舞いか」 「鳩尾があればの話よね」 「ごもっともです」 「どけ」 「ぅおっち?!」 和馬の後ろから、軍司郎が蹴り飛ばしたものがあった。 1足の下駄だ。浴衣と一緒に入口で渡されたものだった。右足の下駄が上顎で、左足の下駄が下顎の、奇妙な生物が飛んでいった。下駄の歯はまさしく歯であった。下駄は白い神にがぶりと噛みつき、神の皮膚をみちみちと剥がし始めた。剥がれた皮の中から、どろりと奇妙な色合いの液体が流れ出す。 「旦那、今のリモコン下……」 「使えるものを使っただけだ」 さすがに表皮を剥がされながらもぼうっとしているような性分ではないようで、耳障りな悲鳴を上げた。流れ出した液体は、床に広がるはしから蒸発するようにして消えていく。 「『徳』だわ」 緋玻がふうっと焔の息を吐いた。 「皮を全部剥がせば解決ね」 彼女は言うなり、のたうつ触手をひょいひょいと掻い潜りながら、白い神に飛びついた。生ける下駄が食い剥がす神の表皮に手をかけて、ぶちぶちと引き千切っていく。 鶏もも肉の皮剥がし。それから黒胡椒と塩ひとふり、じっくり丹念に揉みこんでから、こんがり表面を焼いて、酒と醤油で煮込んで―― ぎいっ、と突然神の表面に現れた人間の顎が、緋玻の腕に噛みついた。 「あっ、いたた! 何すんの!」 「そりゃ皮剥がされりゃ抵抗しますわな」 緋玻の悲鳴に動いた和馬が、彼女の腕に噛みつく顎をこじ開けた。彼の怪力はこじ開けるだけに留まらず、ばりりと上下に引き裂いてしまった。 「フェンリルの最期を実写化!」 牙を剥いて、和馬は笑った。緋玻は、……特に礼を言わなかった。 神が悲鳴を上げて、全身の力を振り絞った。桐伯の鋼糸が千切れ、戒めを解いた神の身体が、どろりでろりと広がった。 だが―― かれが、一行に危害を加えることはなかった。鈴の音にも似た振動が、神を鎮めたようなのだ。 その『音』を生んでいるのは、一樹が揺らす神宝だった。 「その『徳』は、お前の身体のためにならない」 一樹の声は穏やかで、神がいくつもある目を細めた。 「少し、辛抱してくれ」 神がまだ悲鳴を上げていた頃、襖の向こうで起きた物音に、軍司郎が振り向いた。 確かに、みさとの短い悲鳴だった。 軍司郎は襖を開けようとしたのだが、歪んだままの敷居と鴨居が、襖をしっかりくわえこんで動かそうとしなかった。 ちいっ…… 静かな舌打ちが口の中で起きる。 その腕だけは諦めることなく、襖を開けようとしていた。 ががががと音を立ててねじれる廊下の向こうから、ぼろぼろの皮膚の塊のようなものが、風とともにやってきた。それは乾いた腐臭をまとい、ばらりと骨のない触手を広げて、『与護栖の間』の前に降り立った。 『神は――この星に、いくつも要らぬ……』 囁く風が、ぎろりとみさとを睨みつけた。 『うぅぬ、汚らわしい水の使徒。神の前に、まずおまえを砕いてやろう――』 みさとが短く悲鳴を上げた。異形のものが、槍のように鋭く触手を伸ばしたのだ。 幸い、陸號が命令もなしに、純粋な親切心で動いた。囁く風の塊に突進し、組みついて、触手をとめたのだ。 「レイさん」 ガラスの目が、レイを捕らえた。 レイは返事もせずに襖に飛びついた。中の仕事がひと段落ついていれば、助けを呼べる。問題はこの歪んだ襖だ。 ちいっ…… 静かな舌打ちが口の中で起きる。 痛みも疲れも消し飛ばし、イギリス人は襖をこじ開けた。 開いたのは、襖の向こう側にも力が加わっていたおかげだった。 「すみません! 助けて下さい!」 軍司郎が、返事もせずに廊下に飛び出した。陸號が押さえつけているのは、ぼろぼろの黄衣をまとったもののような、ぼろぼろの黄衣そのものであるような、恐るべきものだった。 「風か」 彼は露骨に顔をしかめた。 「厄介な客だな」 皮を剥がされた白い神がのたうちながら縮んでいく。 割れた風船ほどの速さではない。空気を抜かれゆくビニール製のボールの速さで、神は小さくなり、最後には、陸號が抱えていた石ほどにまで縮んでしまった。それきり神は縮小を止め、声も立てず、動きさえも止めた。 「俺の『徳』でよければ、食うといい。誰も知らない夢の世界の力よりは、まだましだろう」 一樹はだまって蒸発していく未知の『徳』をかきわけて、神を抱いた。 湯あたりしたときのような疲れが、一樹を襲った。 だが、それだけだった。 神に再び亀裂が走り、桜色を帯びた白い光が駆け抜け、『蓬莱館』を包みこむ―― 陸號が押さえつけているものや、ねじれた回廊、煮立つ灰色の湯、曲がった敷居が、 歪みが、 たちまち癒されていくのを、彼らは見た。 陸號が、押さえつけていたものを解放した。どたりと廊下に倒れこんだのは山岡風太で――しかし、みさとは不幸中の幸いか気絶していたので、何も見なかったのだ。 見たのは、軍司郎と陸號だけだった。レイは『与護栖の間』に飛びこんでいたのだ。 「貴君が風か……盲点だった……」 どこから持ち出し、どこに隠していたのか、軍司郎は軍刀を持っていた。それを振りかぶり、風太めがけて振り下ろす。 ばちん、と明らかに肉を裂く音ではない音が響いた。 陸號が、軍司郎の軍刀を白刃取りしたのだ―― 「山岡さんは 蔵木さんの お友達 ですから」 若干ながらもばつが悪そうに、陸號は刃の後ろから顔を出した。 「どうか 殺さないで さしあげて 下さい。山岡さんが 亡くなれば 蔵木さん 泣くでしょう 絶対に」 「殺さねば、いつか泣くどころの騒ぎではなくなるぞ」 ぎり、と軍司郎は軍刀に力を込めた。 「それでも、いいと言うのか――」 「旦那、物騒なモン持ってるねえ」 襖の向こうから顔を出したのは、襖の向こうにいた5人。危機感はなく、物珍しそうな視線を、軍司郎と陸號に向けていた。 「きゃあっ!」 不意に、軍司郎の背後で悲鳴が上がる。 みさとが顔を真っ赤にして、『与護栖の間』に飛びこんだ。悲鳴は、軍司郎と陸號を見たから上げたものではなかったようだ。 「ふ、風太さん、最低っ!」 「あ」 「あああ」 「あらあら」 「あー」 陸號の後ろに倒れている風太の姿を見て、『与護栖の間』の5人は深い溜息を漏らした。 「……何故山岡さんは裸なんでしょうか、影山さん?」 「……知らん方がいい」 「それより目の前のふたりがこんな危ないことしてるのに気づきなさいよね、みさとちゃんも……」 「青春なのでしょう」 「うむ、青春だ」 「青春だねえ」 「……くだらん」 軍司郎が、あからさまに不機嫌な顔で軍刀をおさめた。 山菜と猪を使った料理の匂いが、ふうわりと漂ってきた。 「それにしても……神様は? 武神さん」 「さあてな。どこかに行ってしまった。まあ、そう遠くはないところだろうが」 「そうですね、この部屋にもいるかもしれません」 「お客さまあ――ご夕食の準備が整いました。……本当に、すみませんでした。……お待たせしてしまって――」 襖の向こうに立っていた蓬莱は、多くを語るつもりもないようで、首を縮めて微笑みながら、そう言ったのだった。 ■次の100年と明日■ 白い神の100年が始まる。 『蓬莱館』は、蜃気楼か、もしくは夢のようなものだった。 浴衣を返し、一行が蓬莱に見送られながら館を出て、もう一度降り返ったときには――すでに姿を消していたのである。 ありがとうございました、と蓬莱はいつまでも頭を下げていた気がする。 しかし、桐伯と一樹が背負った鞄と風呂敷には、礼として贈られた銘酒『蓬莱』が、確かに1ダースは入っているのだ。特にこのふたりが『蓬莱』の味に惚れたことを、蓬莱はどこでどう知ったのか、呆れるほど多くの瓶をふたりに渡してきたのだった。 夢まぼろしなんかじゃないわ、と緋玻が呟く。彼女は確かに、この世のものではないと感じるほど素晴らしい湯に入った。夕食(騒動)前、夕食(騒動)後、明け方に。 覚えてるさ、あのおねーさんの胸のデカさなんて特に、と和馬が笑った。彼はそう言ってから、けして女湯を覗いたわけではなくて、廊下を歩いている高峰沙耶を見ただけだと恐ろしいほどの必死さで主張した。 鼻血出しすぎたせいであんまりよく覚えてないです、と風太は少し残念そうだ。しかもみさとが朝から妙に自分を避けていることをひどく気にしていた。風太が何を話しても、真っ赤になって黙りこむだけなのだ。 影山軍司郎の姿は、レイが気がついたときにはすでに消えていた。 変わらぬ明日が始まる。 『蓬莱館』も、太古から変わらぬ100年を生きるのだろうか。 100年後のレポートは、100年後も変わらず生きていられる者に頼んでおこう。 リチャード・レイは、そういった文句で高峰温泉レポートを締め括る。 「温泉というのも、そう悪いものではありませんでした」 彼のその言葉が、社交辞令だとは思えない―― 彼は、うっすらと笑っていたから。 <了> □■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□ 登場人物(この物語に登場した人物の一覧) □■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□ 【0173/武神・一樹/男/30/骨董屋『櫻月堂』店長】 【0332/九尾・桐伯/男/27/バーテンダー】 【1533/藍原・和馬/男/920/フリーター(何でも屋)】 【1996/影山・軍司郎/男/113/タクシー運転手】 【2147/山岡・風太/男/21/私立第三須賀杜爾区大学の3回生】 【2240/田中・緋玻/女/900/翻訳家】 □■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□ |
|
|
|
||
|
|
||
|
|
【個別ノベル】 【0173/武神・一樹】 【0332/九尾・桐伯】 【1533/藍原・和馬】 【1996/影山・軍司郎】 【2147/山岡・風太】 【2240/田中・緋玻】 |
|
|
|
||
|
|