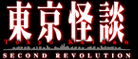 |
|
|
|
||
|
|
調査コードネーム:蓬莱館の秘宝
〜あるいは、天才・河南教授の異界フィールドワーク
執筆ライター :リッキー2号【オープニング】 【 共通ノベル 】 【 個別ノベル 】 |
|
|
|
||
|
|
||
|
|
 【オープニング】
【オープニング】応接室のソファーには、ひとりの男がふんぞりかえって座っていた。 今ひとつ年齢不詳の風貌である。仕立てのよいスーツにがっしりした体を包み、髪は輝くような金髪。外国人かと思えば、しかし、そうではないようだ。 ファッションに詳しいものなら、男の着ているスーツがイタリアの高級ブランドの、ちょっと信じられないくらいの値段のものだと気がついたかもしれない。……だが、そんなことはこの際、どうでもよい。 問題は――男が、その高級スーツの胸元に、真っ赤なバラの花を一輪、挿していることである。 マンガの中ならいざしらず、現実にこういうセンスの男にはなかなかお目にかかれない。いかにここが――東京の知られざる闇の側面をつかさどる場所のひとつ……宮内庁地下300メートル・調伏二係のオフィスであるにしても、だ。 八島真は、なにごともなく自分の席について、カタカタと型落ちの端末を叩き始めた。 職員のひとりが、おずおずと声をかける。 「あの……八島さん……河南教授がお見えですけれど」 「わかっている。だから無視しているのです」 にべもなく、八島は言った。――しかし。 「つれないなァ、八島クンは」 うしろからがばり、と、腕をまきつけられ、八島の喉が絞まった。濃厚なメンズフレグランスの香りが嗅覚を圧倒する。 「……ッ。ちょっと――やめてください……教授!」 「ひさしぶりに旧友が訪ねてきたというのに」 「あ、あなたがわざわざ来るとろくなことがないんだ」 八島の黒眼鏡に、その男の、彫の深い日本人離れした顔が映じた。すっと通った鼻筋に、潤んだような黒い双眸。ラテン系の面ざしの、それなりに美男だと言えたかもしれないが。 「お願いがあって来たんだよ」 八島を解放すると、ふたたびソファーに腰をおろしながら、男は言った。 「……今度、フィールドワークに出掛けるんだが……助手が必要でね。人手を用立ててもらえないかと思って」 「ご自身の研究室の学生をお連れになったらどうです、教授」 教授、という単語に、アクセントをこめて、八島が応える。 「ところが行き先が行き先だけにそうもいかない。――蓬莱館……知っているだろう? 高峰女史から聞いているはずだ」 「……だったらなおのこと、協力できませんね。だってあそこは――」 「いいのかい。キミが協力してくれないなら、『一係』に頼んじゃおうかなァ」 男は唇に微笑をのぼらせる。 「ヤツら飛びつくと思うよ。なにせ百年に一度の機会。それに……ボクの仮説では、蓬莱館にこそ、アレがあるんだ。……人類が永きにわたり追い求め続けた不老不死の霊薬――『変若水(おちみず)』が」 ぴくり、と、黒眼鏡の上で、八島の片眉が跳ねた。 * こんにちは、宮内庁・調伏二係の八島です。 みなさんにお願いがあって連絡させていただきました。 私の旧い悪友で、河南創士郎なる男がいます。現在は神聖都学園大学で民俗学を教えている大学教授なのですが、彼が、フィールドワークに同行してくれる人を募っているのです。単に人手があればいいようなので、専門知識や技術の有無は問いません。もし、おひまがあれば、協力してやってくれませんでしょうか。旅には私も同行します。 行き先は富士山のふもとにある――『蓬莱館』という旅館です。 ご存じかもしれませんが、ここは高峰心霊学研究所の高峰さんが所有する温泉宿なんです(高峰さんがツアーを組まれているようですから、もしかしたら、みなさんもすでにお誘いを受けておられるかもしれませんね)。 まあ、堅苦しく考えず、タダで温泉旅行をするつもりでいらしていただいても結構です。 よろしければ、私宛に返信を下さい。よろしくお願い致します。 追伸/河南教授については、根は悪い人間ではないのですが、あまり気を許されないほうがいいと思います。その点のみ、くれぐれもご留意下さい。 【ライターより】 そんなわけで、調伏二係・八島を通じて、神聖都学園大学の河南教授のフィールドワークへの協力依頼がやってきました。八島と面識のない方にも、依頼がある可能性があります。『二係』には東京で怪奇事件にかかわるほぼすべての人々のデータベースがあるのですから。 河南教授にどのように協力するか、またはしないのか。不老不死の霊薬『変若水(おちみず)』は、果たして蓬莱館に実在するのか、あるとすれば、どこに隠されているのか。あなたの考えと行動を、プレイングにておしらせください。 NPC河南教授については、リッキー2号の異界個室『宮内庁地下・300メートル』内にデータがあります。ご参考まで。 http://omc.terranetz.jp/creators_room/npc_view.cgi?GMID=TK01&NPCID=NPC0342 |
|
|
|
||
|
|
||
|
|
【共通ノベル】 ■オリエンテーション 富士の裾野に、銅鑼の音が高らかに鳴り響いた。 「いらっしゃいませー!!」 一行を出迎えてくれたのは、中国風の衣裳をまとったひとりの少女である。 「ようこそいらっしゃいました。神聖都学園大学・河南ゼミご一行様ですね。わたくし、当蓬莱館で皆様のおもてなしを務めさせていただきます、蓬莱と申します」 ――と、その眼前に、真っ赤なバラの花が一輪、差し出される。 「お近づきのしるしです、小姐」 シャオジェ――中国語でお嬢さん、と呼び掛けたのは河南創士郎だ。 「おっと、あなたにはバラよりも艶やかな牡丹のほうがお似合いのようですね。ここ蓬莱館には季節を問わず花の咲き乱れる中国庭園があるとうかがっています。滞在中、日に一輪ずつ、あなたにふさわしい花を摘んでお届けするようにしましょう」 「まあ、お客様」 蓬莱と名乗った少女はぱっと頬を赤らめたが、それも一瞬のこと―― 「お部屋にご案内しますわ。さあ、どうぞこちらへ」 すぐに、一行を奥へと促す。 「……バラの花って……いったい何年前のセンスよ」 藤井百合枝が、重そうなカバンを持ちなおしつつ、ぼそりと呟く。その声が聞こえたものかどうか、河南は彼女に向き直って、 「ああ、百合枝さん!」 と、馴れ馴れしく呼び掛けた。 「そんな重い荷物をレディがお持ちになることはありません。さあ、八島クン、お持ちして差し上げて!」 「はァ? 私がですか!?」 「何のためにキミに来てもらったと思ってるんだ」 「…………」 すくなくとも荷物持ちではないと思うが――と言いたい気持をぐっとこらえて、八島は百合枝のカバンを持った。 「さあ、花梨さんもどうぞ」 河南は、一行のもうひとりの女性メンバーである村雨花梨に言った。 「あ、いや、わたしは結構です」 「なんて奥ゆかしい!」 「べつにそういうわけでも……ないんですけど……」 高級ブランドもののスーツに金髪、モデル並の長身――とうてい学者とは思えない河南の、妙なテンションに押され気味の花梨である。 「……“気をつけろ”ってこういうことなの?」 苦笑まじりに、百合枝は八島にささやいた。 「でも……嘘つきではないみたい。彼、歯の浮くようなことでも“本気”で言ってるわよ」 「ああ、百合枝さんにはそれがご覧になれるんですね。なんと言いますか……体質みたいなもんなんでしょうね――って、どあ!」 ずっしりと、中身のつまったリュックサックが八島の首にぶらさげられた。 「へへへー、お願いね〜!」 瀬川蓮が、八島に荷物を預けると、風のように駆け過ぎて行った。 「蓬莱館って大きいんだねー! お姉ちゃん以外に宿の人たちがいないみたいだけど?」 「お出迎えはわたしのお仕事だから」 さりげなく、蓬莱と手をつないでもおかしく見えないのは、少年の少年ゆえの特権か。 そのあとを、河南、百合枝、花梨が着いてゆく。 「なんだありゃ。いけすかない野郎だな」 聞こえよがしに言ったのは張暁文(チャン・シャオウェン)だった。 「先が思いやられるぜ。……ま、俺は温泉と酒がありゃそれでいいわけだが」 言いながら、手に提げていたカバンを、衣紋掛けにでも掛けるように八島にひっかけた。 「おぉおおぉ、シャ、シャオ――」 「首を鍛えとけ」 重みに動けない八島を残してすたすたと歩き出す。 「大丈夫?」 最後に残った城田京一がアクアマリンの瞳で八島をのぞきこんだ。 「し、城田さん」 「あ、わたしの荷物は持たなくていいからね」 京一のトランクを見る八島の表情があまりに同情を誘ったからだろうか、そう応えて、彼は暁文に続いた。 「自分の物くらい自分で持つよ。――こんなところで爆発しても何だしね」 「……って、城田さん、何を持ってきたんですか!何を!!」 含みのある微笑を浮かべて去っていった医師の背中に叫ぶ八島だけが、ひとり取り残される。 「……八島さん、よかったらお手伝いしましょうか」 そんな彼に声をかけてきたのは僧服(カソック)姿の青年――ヨハネ・ミケーレだった。まさに、今の八島には天使のように映ったかもしれない。 「お久しぶりです! ヨハネさんたちもこちらへ?」 「はい。師匠たちと一緒なんですけど――八島さん、師匠にメールを下さったでしょう? あの方が河南教授?」 「ええ、まあ……」 「なんだか師匠たちは忙しいみたいで……僕は八島さんを手伝っておいで、ってお払い箱になっちゃったんです。だから僕もフィールドワークにまぜてもらっていいですか?」 「それは願ってもないことです」 「永遠の命をもたらす霊薬だとか――」 「まあ、それは眉唾ですけどねえ」 どこかで新たな銅鑼の音が鳴った。 八島が担ぎ直した蓮のリュックから小悪魔が顔をのぞかせ、ケケケと笑う。 こうして、かれらの奇妙な休日は幕を開けたのである。 ■第一講:変若水の基礎知識 「では、まず簡単に、変若水(おちみず)に関して、おさらいしておきましょうか」 そう――。八島たちがこの宿を訪れたのは、高峰沙耶からの誘いがあったからだけではない。それに乗じて、河南創士郎が計画したフィールドワークの手伝いという名目なのである。 (ボクの仮説では、蓬莱館にこそ、アレがあるんだ。……人類が永きにわたり追い求め続けた不老不死の霊薬――『変若水(おちみず)』が) 河南の言葉を思い出して、八島がそっとため息をついたのに、気がついたものがいたかどうか。 当の河南だけは、それがこだわりなのか、胸にバラを挿したスーツ姿をくずしてはいなかった。あとのものたちは、部屋に荷物を置くと、各自、蓬莱館の浴衣に着替えている。前の合わせの部分がチャイナボタンの、中国風のデザインの浴衣である。 男性陣は偶然か、妙に気が合ったものと見えて、暁文に京一、それに別口で先に蓬莱館に着いていて、先ほど着替えてきたヨハネも、白地に黒がアクセントの入った浴衣だ。もっとも、男性陣でも八島は、黒眼鏡はそのままに、浴衣も黒ずくめだったし、蓮は少年らしい薄いブルーがさし色の浴衣を着ている。 女性陣は百合枝が蓮と同じすがすがしい青みのはいったもの、花梨があわいクリーム地に桃色のさし色が入った可愛らしいもので、それぞれの個性をなかなかよく示していた。 「『変若水』というのは、それを飲んだり浴びたりすれば若返るとか、不老不死になるとかいう伝承の霊薬のことです」 河南が時ならぬ講義をはじめたのは、蓬莱館の庭園である。 旅館を取り囲む森を背景に、青々とした水をたたえた池を中心に造られた池庭で、石橋で渡る浮島には中国風の東屋がしつらえられている。蓬莱に呼ばれて東屋に来てみれば、そこには人数分の茶の用意がととのえられており、さっそく、午後の飲茶となった。 円卓の上には香り高い中国茶に、干し果物や蒸し菓子などが並ぶ。 「こんな昔話を聞いたことはありませんか。――柴狩りに出たおじいさんが、山で泉を見つけ、その水を飲んで帰ったところ、なんと若返っていた。驚いたおばあさんは、おじいさんから泉のありかを聞き、出かけて行ったが、それきり戻ってこない。おじいさんが心配して探しに行ってみると……」 「ボク、知ってる」 発言したのは蓮だ。 「泉のそばでおばあさんが赤ん坊になってたんだよね」 「そう。すこしでも若返りたい、と思うあまり、水を飲み過ぎてしまったんですね。この話などは“若返りの水”の典型的な伝承です」 「それが変若水?」 と百合枝。 「いえ、変若水という名称については――」 「それ、調べてみました」 花梨が生徒よろしく手をあげた。 「万葉集の中にこんな歌があるんですって」 彼女の澄んだ声が、庭園の池を渡る風に乗る。 「天橋 (あまはし) も 長くもがも 高山も 高くもがも 月読 (つくよみ) の 持てる 変若水 い取り来て 君に奉りて 変若 (をち) 得しむもの」 「エクセレント! パーフェクトです、花梨さん。それは巻の十三に収められているものですが、最後の部分を『変若しめむはも』と表記している底本もありますね」 「意味わかんないよう」 と言った蓮に、花梨は微笑み返して、 「天からのはしごがもっと長かったら、高い山がもっと高かったら、月の神さまが持っている『変若水』を取ってきて、あなたを若返らせてあげられるのになぁ――っていう意味よ」 と言った。 「ふーん。でもそれだと、変若水は月にあるってことにならない?」 「そうね。……月の神さまが人間に『変若水』をくれたっていう話もありましたよね、教授?」 「そう、永遠の命をもたらす『変若水』と、死の運命をもたらす『死水』の伝説です。月の神が人間には『変若水』の祝福を、人の天敵の蛇には『死水』を与えるよう、託したのに、手違いや思い込みから、与えられる水が逆になってしまう。……だから人間は定命のものとなり、蛇は脱皮をくりかえして永遠に生きるものになった――これは民俗学上は『死の起源説』と呼ばれる種類の民話なのだけど」 「それが」 百合枝が口を挟んだ。 「そもそも、どうしてこの蓬莱館に変若水があるって話になったの? あなたの仮説とやらを聞かせてほしいわ」 「ああ、そうか」 なにかに気づいたように声を上げたのはヨハネだった。 「月――ですね、教授」 「気がつきましたか」 「実は、師匠から蓬莱館とこの周辺の地理・風土から伝承にいたるまで資料を渡されたのがあるんですけど」 照れたように、ヨハネは言った。 「みなさん、『竹取物語』の、ラストはどうなったかご存じですか」 「『かぐや姫は月に帰っちゃいました』」 蓮が元気よく答えた。 「では、そのあとは?」 「あと? つづきなんてあるの?」 「かぐや姫は、お世話になったおじいさん、おばあさんに、贈り物を置いていったんですよ。……それが『不老不死の薬』だというんですね」 「ああ、そうか、かぐや姫は月から来たんだから……月にある変若水を持っているのも自然よね」 と百合枝。 「ええ。ですが、おじいさんたちは、かぐや姫がいないのに、自分たちが長生きしてもしようがない、とこの薬を捨ててしまうんです」 「当然だ」 まるで興味がなさそうにそっぽを向いていた暁文が、このときだけ、ぼそりと反応した。 「年寄りが散々長生きしておいてまだ生に終着することほど、みっともないものはねぇからな」 「あー、それわかるなー。うちの病院も末期ガンのホスピスとかあるけど……何のためにあんな経費かけるのか、不思議なんだよね」 さらりと、医師とも思えない京一の発言が続いたが、暁文はそれを無視した。 「……そして、この薬を捨てた場所が――富士山だと言われているんです」 「あー……」 「そもそも『富士山』という名前からして、『ふし(不死)のやま』という言葉から来ているんですからね」 ちょうどそのとき、蓬莱がお茶のおかわりを盆に乗せてあらわれたところだった。新しい茶が注がれると、深い茶葉の香りが東屋に充ちた。 「また、かぐや姫は、求婚してきた男性にわざと無理難題をふっかけてそれを退けたというエピソードがありますが……その中で、『蓬莱の玉の枝』というものを取ってこい、と言うミッションがあります」 「蓬莱――」 自然と、屋号と同じ名を持つ少女のほうへ、一同の視線が集まる。 「『蓬莱』というのは、中国の伝承で、仙人が住む島のことですよね」 ヨハネが、少女に問いかけた。 「ええ。それにあやかって、当館は『蓬莱館』と名付けられました。うちの温泉を浴びると、寿命が伸びると言われてるんですよ」 「わかった!」 蓮が叫んだ。 「ここの温泉のお湯が変若水なんだよ!」 「あらら」 花梨が目を丸くした。 「それじゃ、わたしたち、全員、不老不死になっちゃうわね」 場に笑いが起こった。 「…………」 京一は――ふと、石橋を渡って戻っていく蓬莱の後ろ姿を、じっと凝視しているものがいるのに気づいた。河南と八島である。河南は唇に笑みを、浮かべ、八島はどこか神妙な顔つきで、少女を見つめているのである。やがて、八島はかすかにかぶりを振って視線を落とし、河南は満足げに少女を見送る。 まだあきらかになっていない秘密が、そこにはあるようだった。 ■第二講:蓬莱館の調査 「不老不死の薬なんて本当にあるのかしら。どう思う、花梨さん?」 百合枝は半信半疑、という色をにじませた声音で、花梨を振り返る。 「そうですね……たしかに変若水、月、蓬莱、と、キーワードは繋がっているように思いますけど」 ひとしきり飲茶を楽しんだあとは、各自、手分けして蓬莱館やその周辺を「調査」することになった。もっとも、皆が皆、変若水の存在を信じてもいなければ、河南に協力的なわけでもない。それが「調査」という名目のただの散策になるのは目に見えていた。 ふたりが歩いているのは、蓬莱館の棟と棟をつなぐ吊り回廊である。 蓬莱館は異様に広い。いくつもの別棟にわかれ、それらが、こうした回廊でつながれ、その合間にたくさんの庭園や木立が入り組んだ複雑なつくりになっているのだ。 「もし蓬莱館の中に隠されているというのなら、蓬莱さんに聞けばなにか手がかりがあるかもしれませんね」 言いながら、花梨は手すりに体重を預けて窓から顔を出し、春の木々が発する新芽の香りを深く吸った。樹木に取り囲まれ、匿われるようにして建っている蓬莱館は、居るだけで森林浴ができそうな場所でもあったのだ。 「彼女、なんだか不思議よね。そもそも、こんなに大きな旅館なのに彼女以外の従業員をひとりも見かけないわ――あら」 噂をすれば、か。 百合枝は、窓の外の木立の向こうに、少女のまとううすものの衣がひらひらと見え隠れするのに気づいた。山菜か木ノ実でも採っているのだろうか。 ふと、悪戯心のようなものを起こして、百合枝はたもとからデジタルカメラを取りだした。望遠もできるタイプだ。スイッチを入れ、蓬莱のいる方向へカメラを向けると…… 「えっ」 百合枝は声をあげた。 画面には――ただ新緑の木々が映っているばかりだった。 はっと顔を上げると……たしかにそこに居たと思った蓬莱の姿が見えない。 「どうかしました?」 「ねえ、そこに蓬莱がいなかった?」 「さあ。私は気がつきませんでしたよ」 「そう……。気のせいだったのかしら……」 「あ、百合枝さん、あそこ」 花梨が、ふと、指差した方角を見れば、梢の上に白い煙がたなびいている。 「湯気ですね。あのあたりが温泉なんですよ」 「ああ――」 「そういえば、さっきの話。不死の薬を捨てて以来、富士山の火口からは毎日、煙が立ち上るようになった、って」 「ふうん。案外、本当に温泉が関係あったりして」 「……百合枝さん、夕食前に、ちょっと“調査”に行きません? 温泉の」 「あら、いいわね。賛成!」 そして女たちは、いそいそと温泉へと向かったのだった。 「あぁ? なんだと?」 暁文の低い声は迫力に充ち、眼光はひたすら鋭い。 「フィールドワークだか何だか知らんが、俺ぁ、そんなカッタルイもんに協力する気はハナっからねぇんだ。不老不死になんぞさらさら興味ないしな。あの眼鏡がタダで温泉に来れるっつうから来てやっただけだ」 そのときロビーでは、河南と暁文、京一の姿が見られた。 「まあ、そう言わずに」 普通人ならそれだけ畏縮してしまうほどの、暁文の凄みに接しても、河南は柔和な態度をくずさない。 「あなたは興味なくても、変若水をお土産に持って帰ったら、喜ぶ方がいらっしゃるんじゃないんですか」 「てめぇ、なにを知ったふうな――」 くわっ、と、暁文の目から火花が散ったかに見えた。それは本当のことだった。もともと高峰沙耶から誘われ、気乗りしないでいたところ、八島からの依頼を受けた暁文を熱心に後押ししたのは、彼の属する組織の長老たちだった。 「不老不死を求める発想は、古来、日本より大陸において盛んだ」 講義のつづきとばかりに、河南は言った。 「仙道もそうして発達したのだし、歴代の中国王朝の皇帝たちはこぞって不老不死の秘法を――」 「うるさい。それ以上、くだらねえ御託を並べると……」 「――おっと」 「あ」 「……」 両手を上げる河南。 その鼻づらに、トカレフをつきつける暁文。 そしてその暁文のこめかみを、京一のUSPが狙っていた。 「……てめぇ、何のつもりだ」 「あ、いや、すまない。つい反射的に」 それは奇妙な三すくみ(?)の様相を呈していた。 【図解】河南←暁文←京一 「あら、あなたたち」 そのとき、たまたまそばを通りがかったのは、碇麗香だった。 「あなたたちも高峰さんに誘われたの? ……というか何やってるの」 「罪つくりな私のせいでふたりが争っているのです」 「いや、それは違うでしょ、教授。――あ」 しれっと麗香の問いに答えた河南に、京一の銃が向けられた。その隙を突いて、暁文のトカレフの銃口が京一のほうを向く。 【図解】暁文→京一→河南 「ふうん。そうなの」 「信じんなよ、てめぇも! ――う」 しかし、あまりに無邪気な麗香の返事に、暁文は銃ごとつっこんでしまい、またもや京一に狙われることになる。 【図解】麗香←暁文←京一 「じゃ、そういうことで」 そしてひとり、自由になった河南はさっさと立ち去っていく。 「オイ!てめぇ!待ちやがれ!!」 「あー、教授。わたしはちゃんとお手伝いしますよ」 「……それで結局、何やってるのよ、あなたたち」 麗香の問いに、答えられるものは誰もいなかった。 「えーと、このあたりだと思うんですけど……」 ある意味、変若水探しに一番熱心だったのは、この組だったかもしれない。ヨハネが入手した資料にあった、蓬莱館とその敷地の見取り図を頼りに歩く、ヨハネ、蓮、八島のトリオである。 かれらが歩いているのは、蓬莱館の裏手にあたる森の中である。地面に勾配がつき、急な斜面になっているところもあって、すこぶる歩き難い。 「こっちかな。木が途切れてる」 「あっ、これだよ、ほら」 蓮の発案によって三人が探しているのは、高峰温泉の源泉だった。なるほど、蓮が指したところには、湯気のたつせせらぎのようなものが流れている。 「たしかに……これをあそこから引き入れているみたいだ。あの壁の向こう、もう湯殿でしょう?」 斜面のふもとにある蓬莱館の棟のひとつを、ヨハネは指さした。 「これを汲んでいこう」 蓮は遠足よろしく提げていた水筒に、湯を汲み上げようとする。 「あ、蓮くん、熱いかもしれないから気をつけて」 ヨハネが注意した。 「仮にこれが不老不死の温泉だとして……」 急な山道を登ってきたせいか、少々、息のあがっている八島が、一休みとばかりに、近くの岩場に腰を下ろす。 「だったら高峰さんがわざわざここに私たちを招待するというのもね……」 「お裾分けのつもりかもしれないよ。あの人も侮れないからね。実は自分はとっくに不老不死だったりして」 「あはは、高峰さんならありえますねー。……あれ」 「この音――」 低い地ひびきのような音と、かすかな振動を、そのとき、かれらは感じた。 「真さんのあたりから聞こえるよ!」 「はい……?」 「あ。八島さん。もしかしてそこって――」 ヨハネの言葉をかき消して、轟音と、熱気と、水蒸気の爆発が起こった。 「熱―――――――――――――――――ッ!?」 「か、間欠泉……っ」 高峰温泉の源泉が、熱湯とともに、圧倒的な圧力でもって噴出し、その真上の、岩の割れ目に腰掛けていた八島を空高く放り投げた。 「あーあ……」 ヨハネの視線は間欠泉の圧力と地球の引力とに翻弄される八島を追って、空中から山の斜面、そしてその下へ。彼の隣では、蓮が手を叩いて大笑いしていた。 斜面に落下し、そのままそこを転げ落ちていく八島。彼が勢いよく湯殿の壁を突き破るに至って、ヨハネは静かに十字を切った。 (神さま……こんなお約束の展開も、ご意思なのでしょうか……) そこがたしか女湯であることを、蓬莱館の見取り図を持っているヨハネは承知していた。 さすがに、折悪しく百合枝と花梨が湯につかりはじめた矢先とは知らないまでも。 ■第三講:秘宝の発見 「八島くん、女湯をのぞいたら、藤井さんに一本背負い投げかまされて、村雨さんのカマイタチに切り刻まれた上に、温泉の熱湯でお尻を火傷したって本当?」 「…………もう、そういうことでもいいです」 京一の無邪気な問いに、部屋の隅にうずくまっている八島は言葉少なに答えた。 「あの……火傷と女湯の順番が逆なんですよね」 ヨハネが、微妙にフォローし切れていないフォローを入れた。 「火傷したのに女湯をのぞいたのかい。さすが若いね! わたしなんか、さっきロビーで暁文くんとかるく撃ち合いしただけでもう疲れちゃってね」 京一は感心したように言った。 「とにかく、火傷診てあげるから、ちょっとお尻を見せてごらん」 「いいです、いいです! もう平気ですから!」 高峰沙耶の広範囲にわたる招待によって、蓬莱館にはさまざまな能力者たちが滞在している。そのなかには治癒の能力を持つものも少なくなかったから、かれらの協力によって、八島の負傷も事なきを得ていたのだが。 「そう遠慮せずに。保険効くんだから。……蓮くん、ちょっとそこ押さえて」 「はーい」 「ああ、ちょっと!やーめーてーくーだーさーいー」 あばれる八島を、京一と蓮、さらには蓮が呼び出した小悪魔たちが総出で押さえ込んだ。――と、そのとき、がらりとふすまが開いてあらわれたのは河南である。 「……うわ、なにコレ。やだなァ、ボクのいないところで盛り上がっちゃって」 「教授、変若水の手がかりは見つかりましたか?」 ヨハネが背後の惨状からあえて目をそらそうとするかのように、河南に尋ねた。 「いや。残念ながらまだはっきりしないんだ」 ちょうどそのとき、銅鑼の音が蓬莱館中に響き渡った。 「お食事のご用意がととのいましたー。食堂までおいでくださーい」 そして蓬莱の声が客たちを呼ばわっている。 食堂として供された大広間へ出ると、女性陣はすでに食膳の前についていた。 「八島さん……さっきはすいません。つい、ざっくりやっちゃって」 「あら、謝らなくてもいいわよ。いくら事故とはいえ、こっちだって被害者なんだから」 「…………」 「帰ったら二係のひとたちに言っちゃおーっと。八島さんが女湯のぞいたんだよ、って」 「それは違うでしょう!だいたい、もとはと言えば蓮くんが温泉の源泉を探しに行こうなんていうからー!」 「ほらほら、子どもにあたらない」 「……ところで、暁文さんは?」 花梨があたりを見回して言った。 広間には、他の滞在客たちも三々五々、集まりつつあったが、暁文の姿はないようだった。 「城田さん、さっき撃ち合いしたって仰ってませんでした?」 とヨハネが京一に問うた。 「あー、でも殺してないよ?」 「おーい」 まさにそれに応えるように、蓬莱をともなってあらわれたのは暁文である。 「センセーよゥ」 と、これは河南への呼び掛けだ。 「オレが『変若水』を見つけてやったぜ」 「なんですって……!?」 一同にざわめきが走った。 「見ろ……こいつだ」 暁文は、蓬莱が手にしたひとかかえもある大きな瓶を示す。そして少女は、にっこりと微笑んで言った。 「蓬莱館名物、地酒『変若水』です」 沈黙――。 「…………」 「…………」 「………あ」 「えっと……」 「お酒……」 「これが……」 「『変若水』の正体……?」 たまり兼ねたように、暁文が吹き出した。 「一種の霊薬には違いねぇわな! こいつぁ、たしかに寿命も延びるってもんだぜ!」 暁文は河南のとなりにどっかりと腰をおろし、馴れ馴れしく肩を組んで笑った。 「さあ、飲むぞ!!」 そして――。 冴え冴えとした月が、天に架かっていた。 蓬莱館の食事は、山の幸をふんだんに用いた、彩りは豪華で、味も申し分のないものだった。宴は果てしなくつづくかと思われたが―― 「あーあ、バカバカしい。そうよね。不老不死なんてあるわけないんだから」 蓬莱館の浴場はひとつではない。広大な敷地の中に、泉質や趣向の違う湯殿が数知れずあるのである。百合枝と花梨がやってきたのもそのひとつで、先刻、八島が壁を破って乱入したのとは違う露天風呂であった。 竜の口から清浄な湯が蕩々とあふれ、湯面に映る月をゆらしている。 「でも美味しいお酒でしたよ」 酒と、温泉に上気して朱に染まった頬で、花梨が言った。 「いろいろ面白かったし、いいじゃないですか。……ほら、月もきれいですよ」 「そうねぇ。……うーん、久しぶりに温泉ってのはいいもんね」 百合枝は、湯の中で思いきり、手足を伸ばした。 「極楽〜って感じ」 「やだ、百合枝さん、おばさんくさいですよ」 「だって極楽じゃない。なんかずっとここに居たいわぁ」 「森の中だからでしょうか、時間がゆったりしてますよね、ここ。食べ物も美味しいし、たしかに極楽かも。……ここにいるあいだだけ、不老不死になったみたい」 女たちは笑い合った。 なにげないそんなやりとりに、真実が隠されていたとも知らずに。 ■終講:不老不死の考察 一方。 すこし離れた男性用の露天風呂では、阿鼻叫喚の宴が舞台を変えてまだ続いていた。 「いやぁ、ドクター。あんたにぁ驚いた。日本人でさえなけりゃウチの組織にスカウトしたいくらいだ」 「とんでもないよ、暁文くん。わたしなんかすっかり身体のキレがなくなってね」 「よく言うぜ。あれだけ暴れといて」 「暁文くんこそ、早撃ちには参ったよ。二丁使ってあの連射ができたら、十人くらい、いちどに相手できるんじゃない?」 真っ赤な顔をしたチャイナマフィアと医師は、湯舟の中で肩を組み、湯に浮かべた桶の中に徳利を並べて、なお酒を酌み交わしていた。 「つまんねえ謙遜しやがって、これだから日本人はイヤだね! この身体の傷痕を見たら大概、修羅場くぐってるってわかるってもんだ」 「わたしは医者だよ。救急のほうは修羅場だけど、これは別に……子どもの頃、犬に咬まれたりとかね……」 「ギャハハ、嘘つけ。ハイエナの群れに襲われたの間違いだ」 笑いながら、勢い余って暁文が投げた手ぬぐいが、すこし離れたところに浸かっていた八島の側頭部にぺしゃりと命中する。 「…………」 鼻の下まで湯に浸かった八島の目の前を、黄色いアヒルの玩具が、列をなして過ぎて行った。蓮が大量に持ち込んだものの一種だった。 「イェーイ!」 水鉄砲が勢い良く水を噴いて、手ぬぐいとは反対側の、八島の頭を撃った。 「……どしたの、真さん。元気ないよ?」 「…………」 「ほら、蓮くん。そっとしておいてあげようよ。八島さんみたいに、普段忙しい人は、休みがあると虚脱しちゃうんだって。燃え尽き症候群っていうらしいよ」 「そうなの?」 「さ、蓮くん、背中流してあげるからおいで」 ヨハネが蓮を招いた。 「はーい。……ところで、キョウジュはどこに行ったの?」 「あれ。……部屋で寝てるのかな」 「キョウジュも燃え尽きちゃったんじゃない? 不老不死の薬がなかったのがショックでさ」 「不老不死なんてあってたまるか!」 それに大声で応えたのは、暁文だった。 「人間、いつか死ぬから、一生懸命生きられるんじゃねぇか。それに生き物が死ぬのは普通のことだろ。死なないなんて不自然だぜ」 「張暁文がいいこと言った!」 京一が拍手をおくった。 「中華三千年の知恵だねー、深いねー」 「謝々!謝々!」 そして握手をかわす。酔っ払いたちの頭のネジははずれっぱなしだった。 「そっかぁ。不老不死なんてやっぱりないんだなぁ」 「……いいえ、そんなことないですよ」 ぽつりと、どこか残念そうに言った蓮に、石鹸の泡を立てながら、ヨハネが静かに告げた。 「神さまの前では、人の命は永遠なんです」 なるほど、ヨハネにしてみれば、それは正論だった。 だが。 「……え、真さん、なんか言った?」 蓮が耳ざとく振り返る。 ごぼごぼ――と、湯の中で、八島が何事かを呟いていた。 (……河南教授がこんな単純な見当違いをするはずがないんだ……やっぱり、なにかある……この蓬莱館には……) 「……どうでもいいけどさぁ、ずっと気になってたんだけど、真さん――」 蓮が小首を傾げて、八島に尋ねた。 「……なんで、温泉の中でもそのサングラスかけたまんまなの?」 * ふわり、と湯気の中を舞うその姿は、まぼろしのように美しい。 月光のもと、まるで花から花へと飛ぶ蝶のごとく、温泉の上をただよっているのは、あの蓬莱という名の少女であった。 夜風にうすものの衣がはためき、わずかにその爪先がふれた湯面に波紋が広がる。 「……!」 はっ、と、少女が顔を上げた。 胸に挿したバラの花の紅さもあざやかに――河南創士郎がそこに立っている。 「地酒『変若水』とは、してやられましたねぇ」 「お客様」 宙に浮かぶ蓬莱の身体は、あわい燐光に包まれていた。 「ぼくの目はごまかせませんよ。……すくなくとも――この蓬莱館がそれ自体、ひとつの異界だということはわかっているんです」 くす……と、蓬莱は微笑った。客の前では見せたことのない、あやしい陰のさす表情だった。 「そこまでご存じなら……もはや隠しだてすることなどございませんわ」 「不老不死の秘宝はあるんですね」 「無論です」 「なら……」 「それはこの『蓬莱』そのもの」 「……?」 少女・蓬莱は夜空を見上げた。遠い瞳に、月が映じていた。 「もう二千年以上、昔のことです。……秦の始皇帝の命を受け、不老不死の秘薬をもとめて、徐福という名の術士が旅立ちました」 「それなら知っています。三千人の若い男女をともなっての大船団だったと言いますが」 「わたしもそのひとりでした」 「……! それでは――」 「ええ。徐福さまがたどりついた蓬莱山こそ、まさにこの地。ここで、わたしたちは不老不死の方法を見い出したのです」 「ですが……蓬莱山は海の中に浮かぶ浮島と――まさか」 「そうです。世界と世界、虚無とのはざまに浮かぶ浮島としての異界、それがこの蓬莱館です。ここは――徐福さまの秘術により、三千人の人間の命をもって造られた『不老不死をもたらすための異界』、すなわち……」 「この異界にいる限り、誰であれ不老不死でいられる……」 「そのとおり」 ふぅわり、と、蓬莱は笑う。 「いかがですか、お客様。わたくしたちと一緒に、永久にこの宿にとどまられては。美味も美酒も、不老も……なにもかもが、思いのまま」 だが。 河南創士郎は高らかに、そんな誘いを一笑するのだった。 「……これはやはり、見込み違いだったようですね」 「……不老不死を、もとめられていたのではなかったのですか」 「ぼくはただ――永遠のものを探しているだけです。この世に、本当に確かな、信じるに足るものがあるかどうかを。……異界『蓬莱』。もしやと思いましたが、たとえ不老不死を実現しようと、こんなものはまやかしでしかない」 河南は語った。 「それならなぜ、高峰女史と結んで、百年ごとに、外界の人間を受け入れたりするのです」 「そ、それは」 「そうしなければ、この異界を維持できない。違いますか?」 「…………」 「残念です。……ここは、ただ美しいだけのまぼろしです。ぼくの求める――永遠とは程遠い」 彼は胸のバラをむしりとると、少女の足下に投げ捨てた。そして、鋭くきびすを返すと、湯煙の向こうへと消えてゆく。あとには、蓬莱だけが取り残された。 「……そうして……皆、わたしを置き去りにしてゆく」 声は、たとえようもない寂しさに充ちていた。 「百年にいちどのお客さまたちも……三千人のかつての同士も……そして徐福さまだって……。いつだって、わたしは独りきりで後に残されるのだわ。……そう、これからだって、永久に――」 二千年の孤独を過ごす少女の独白を聞いているのは、水面に浮かぶ、一輪の薔薇だけだった。 (完) □■■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■■■■■□ ■ 登場人物(この物語に登場した人物の一覧) ■ □■■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■■■■■□ 【0213/張・暁文/男/24歳/自称サラリーマン】 【1286/ヨハネ・ミケーレ/男/19歳/教皇庁公認エクソシスト・神父、音楽指導者】 【1790/瀬川・蓮/男/13歳/ストリートキッド(デビルサモナー)】 【1868/村雨・花梨/女/21歳/保育士】 【1873/藤井・百合枝/女/25/派遣社員】 【2585/城田・京一/男/44/医師】 |
|
|
|
||
|
|
||
|
|
【個別ノベル】 【0213/張・暁文】 【1286/ヨハネ・ミケーレ】 【1790/瀬川・蓮】 【1868/村雨・花梨】 【1873/藤井・百合枝】 【2585/城田・京一】 |
|
|
|
||
|
|