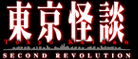 |
|
|
|
||
|
|
調査コードネーム:蜃宝珠 執筆ライター :間垣久実 【オープニング】 【 共通ノベル 】 【 個別ノベル 】 |
|
|
|
||
|
|
||
|
|
 【オープニング】
【オープニング】「あら、此処に居たの」 高峰沙耶が、丁度良い所で出会ったと笑みを浮かべて近寄ってくる。手に小さな袋を持って。 「少し、預かって欲しい物があるのだけれど、良いかしら?」 そう言いながら、袋を開けて取り出したもの、それは、 どうみても只の丸い玉。それも、遠慮ナシに言えば発泡スチロールで作られたボールに見える。手に取ってみても、軽々としていて。 「――そう。そう見えるのね」 不思議な事を呟いた沙耶が、直径3センチ程の大きさの其れをころころとロビーにしつらえてあるテーブルの上へいくつも転がし。 「いい?…よく耳を澄ませてごらんなさい」 その1つを手に取ると、少し離してテーブルの上に落とした。…と。 ――リィ…ン えもいわれぬ音を立てて、その玉が弾け、そして消える。 「…綺麗な音色でしょう?」 ここでしか手に入らないの、と沙耶がその音の余韻が十分消えるまで待って告げる。 「貴重な物なのだけれど、今も見たように壊れやすくて。こうしてまとめて持っているだけでも、帰る頃には1つしか残らなくなっちゃうの。…1つは必ず残るのだけれど」 だから、と言葉を続け、 「預かってもらえないかしら。今ここには割れた物を除いて10個あるわ。私もこれとは別に持っているの。…なるべく割らないで取っておいて貰えたら、戻った時にお礼をさせてもらうから…お願いね」 そう言い置いてすっと立ち、質問の隙を与えずにぱたぱたと上品なスリッパの音を立てながら立ち去って行った。 「…高峰様」 蓬莱の声がどこかから聞こえて来る。声のするほうを見れば、沙耶と蓬莱が何か話し込んでいる様子。 「……宜しいんですか?あれは…」 「大丈夫よ…だって、彼らは…」 心配そうな声の蓬莱とは対照的に笑みを含んだ声を返す沙耶。 「まあ…少しは幻覚が見えたりするかも…でも…一晩…でしょう?」 2人の話し声が遠くなっていく。 …幻覚? 改めて見ても、やはり発泡スチロールで作ったボールの表面を綺麗に磨いただけにしか見えない。触り心地も軽さも。だが指で押すと、あれだけ軽快に割れたにもかかわらずぷにょん、と柔らかな弾力が指に返って来ていっそう分からなくなった。 |
|
|
|
||
|
|
||
|
|
【共通ノベル】 「………」 優雅に旅館での休日を楽しんでいた筈だった。 が。 黙ったまま、テーブルの上に転がっている10個の白いボールを見つめ、了承云々を確認する前に立って行ってしまった沙耶を追いかけることも出来ず、何となく言葉を出すのも憚って黙ったままで居る4人。 「あ――あの」 不意に声を出した少年が居る。集まっていた4人の1人で、鮮やかな赤とオレンジの浴衣を着、さらりと柔らかそうな髪を額に流しながら首を傾げ、 「僕は受けるのは構わないんですけれど…どうしますか?10個だと、等分には分けられそうもないですよね」 おそるおそるその中のひとつを摘んで、手の平に乗せる。 少年…奉丈遮那は、とりあえずと自分の分2個を手の上に確保しておいてどうします?と言う風にもう一度首を傾げた。うーむ、と腕を組んだ青年、向坂嵐が困ったように口を曲げ、 「俺も自信は無いが」 そう言いつつ、遮那よりも丁寧に、慎重に2つを摘み取った。 改めてこうして触れるとぷにぷにと柔らかい。これが先程皆の目の前で音を立てて割れたかと思うと奇異な思いにかられてしまうのだが。 「本当は安全な場所にひとまとめに置いておくのが一番なんでしょうけどね…」 嵐と同じように軽く腕組みしながら少しばかり語尾を濁らせたシュライン・エマが自分の言葉に自分で否定するように緩やかに首を振った。 と言って、常識が通用するような品でもなさそうで。そういう意味では『安全な場所』など何を基準にしていいのか分からなくなる。 「――不安なら私が預かりましょうか」 その時、ぽつりとその場に言葉を落とした少女が居る。 ササビキクミノ――歳不相応な落ち着きと、穏やかと言うかどこかすぱりと切れそうな静けさを持った少女が、たまたま居合わせた最後の1人だった。 カラーリングが自分と同じ、赤にオレンジと言う色合いの女物の浴衣を見ながら、自分のそれと引き比べ、遮那が少しばかり羨ましそうな顔をし。そしてクミノの提案に僅かに首を傾け。 「せっかくの申し出ですけど、ここはやはり居合わせた僕達で分ける方がいいと思うんです。どういった保護の方法が一番適しているのか、分からない現状ですから」 「そうね。でもひとつ多く預かってもらおうかしらね?…あとは、僭越ながら年長ってことで私が。これで全部になるわね」 「そうだな。俺はそれで良いと思う」 どう?と目で聞いて回るシュラインに、嵐がぼそりと口を開き、2人は頷きで返した。 * * * 「――幻覚?」 部屋へ戻る途中で――途中までは皆一緒の方向だったのだが、そんな折に向こうへと消えていく沙耶と蓬莱の姿を見、誰かがぽつりと、不審も露な言葉にして口に乗せる。 だが、今更…という感もあり。 依頼は依頼だ、と。 頼まれごとはこの丸いボールを預かる事。たとえ幻覚でも其れが幻と分かっているのであれば問題ではないと結論付け。 そして、4人は各々の部屋へと戻って行った。3人は比較的近い位置に、クミノはずっと遠くの部屋に。 * * * 「触っても大丈夫…それにしても柔らかいなぁ」 ぷにぷに、とその感触を楽しむように指で何度も押してみる遮那。落とすことだけは避けたものの、触れても押しても、何が起こる様子も無い。水風船のような感触が手に残るだけ。 部屋に戻り、腰を落ち着けた後のこと。僅かな恐怖は好奇心にあっさりと負け、こうして先程から手で弄んでいるのだったが。 「とりあえず」 ぽつりと呟いてきょときょとと辺りを見回した。目的に適う品を見つけ、其方へと移動した。 そぉっと。 備え付けの茶のセットを取り出し、丸い湯呑みの中へそぉっと、白いボールを降ろし。無事底に置いてほっと息を付く。 そして、蓋。 そうやって2つのボールをそれぞれの中へ仕舞うと、やはり緊張していたのだろう。体の力がふっと抜けた。 抜けて――すとん、と『落』ちた。 * * * 同時刻。 「どうしたらいいのかしらねぇ」 その殆どが壊れてしまうと言うその白く丸いボールを、窪みを作ったバスタオルの上に隙間を空けてひとつずつ配置していく。 指先で摘んだ時の柔らかさも、手の平に乗せた時の不思議な軽さも、そして蓬莱と沙耶が話していた『幻覚』のことも――様々なものが頭に浮かんでは消えていく。 どう見ても安っぽい代物にしか見えないのに。 「柔らかくても壊れやすいのよね…これで守りきれるならいいのだけど」 やや不安を帯びた声を呟きながらそっと其れに触れる。ぷに、と柔らかな弾力が指先に跳ね返ってくるのが感じ取れ、何とはなしに小さく微笑を浮かべた。 「どういう時に幻覚が起こるのかしらねぇ」 沙耶の言葉のニュアンスで言うとこの旅館に居る間だけ預かって欲しい、というようなものだったから、せいぜいが今晩一晩、もしくはその次の日まで、ということなのだろう。その間何も起きなければ良し、何か起きたとしても初めから幻覚だと聞かされている以上驚く事も無い。 「一晩、二晩と言ったら長いけどね」 ぽつんとそう呟いて、立ち上がり、気分を入れ替えようと言うのか部屋の窓をからりと開けた。 * * * 同時刻。 嵐は、丁寧に丁寧に、そして慎重を期しながらハンカチにくるんだ其れをバッグの、柔らかな部分へと仕舞いこんだ。そして、ほぅ、と息を付く。 「神経に悪い」 ぼそりと言った一言、そして重要書類でも此処まで神経質に仕舞いこんだことなどなかったな、と思う。 さて。 顎から喉を軽く撫でて、ひょいと立ち上がる。緊張のせいかそれとも単に口寂しくなっただけか、喉の渇きを感じたためだった。放っておいても大丈夫ならロビーに出て飲み物でも買って来ようかと思ったらしい。 財布をポケットに、ちらと部屋を出る前にバッグに目を向け――そして、無理やりというほどではないが目線を外し、のんびりと外へ出て行った。 がしゃこん。 自動販売機で目当ての品を押すと、耳障りな音と共に清涼飲料水が転がり出て来る。拾い上げたその手でキャップを捻って飲み物を口に運びながら、嵐は暇潰し用のいい物は無いかと辺りを見回した。 「お」 つい、と目の前の角を曲がって消えたのは蓬莱の姿。沙耶と預かったあのボールに付いて話していたところを見ると彼女も何かを知っているらしい。それも、心配する程の何かを。 冷たい缶を手にとるや、すぐさま彼女の後を追って角を曲がった。が、蓬莱は誰かに呼ばれたらしく何か言葉を口にしながら向こうへと消えていく。 仕方ない。 手に持った缶に目をやり、そして言い訳がましく「一旦戻るか」そう呟いて自分の部屋へと足を向け、扉を開けた。 * * * 同時刻。 自分ひとりきりの部屋に戻るなり侵入者の有無をチェックし、少し部屋を出ていた間に何か変化があったかをほぼ無意識に確認し、持ち込んだ機材の状態を見、それからようやく少し体の力を抜く。 もちろんそう簡単に自分の居場所に誰かが入り込めるようにはしていないが、こればかりは身体に染み込んだ習慣で消えることはないだろう。 「……」 行き掛かり上頼まれることになった品をちらと見、注意は払いつつも無造作にプローブのケースの中へと仕舞いこむ。精密機器用のケースだからこそ、対衝撃設計は万全の筈だったからだ。とは言え、幻覚云々の症状に衝撃耐性は無意味であり、預かる身として完全に安心しきれる訳でも無い。 まあ…気にする必要もなかったが。 これしきのことで気に病むようなものでも無かったことだし。 身動きしないクミノの居る部屋は、不思議な静けさに満ちている。 人が来ないよう隅の部屋を取り、そして本人が部屋に居ながら彫像のように動かずにいて。 視線だけは、ケースに注がれている。まるで何かが現れるのを待ち望むように――本人はそう見られていたと気付けば否定するだろうが。 暫く見ていたが、ケースが動くような様子も無く、静かな時間だけが過ぎていく。 ――単に、あの品のお守りをすれば良いだけなのだろうか。それとも、まだ何かあるのか。 ほんの少しの失望と、倦怠感。 ケースから目を外したのはほんのひと時。 だが。 次に目を向けた時には―― * * * 「え?」 その声を最初に上げたのは誰だったか。 沙耶に頼まれごとをしていた筈だった4人が、何故だか集まってぽかんとした顔で互いを見合わせている。 「どうして…」 遮那の言葉が、ようやく形を結んだ。 「各自が部屋へ下がった…そうだったわよね」 確認を取るつもりなのか、シュラインが呟くように言い、 「俺は飲み物を買って来て…」 嵐がそう言い、手に持ったままの缶ジュースを不思議なものでも見るような目で見た。汗をかいていた缶からしたたった水滴が手を伝い、足元にぽとりと落ちる。 固い床の上に落ちた水滴は、いくつもの小さな粒に砕けて消えた。 「幻覚なんだろうな」 嵐がぐるりと辺りを見回し、そしてどこか感心した声を出す。 ――見慣れた風景。 草間興信所の、事務所の中に居たのだから。 幻覚なのだろうと、思う。 各自の部屋に移動していた皆がこうしていつの間にか顔を合わせていることなど在り得ないのだから。しかも、温泉地から遠い『怪奇探偵』の事務所内とあっては―― 「けれど…随分、リアルなんだね」 すい、と静かに視線を動かすクミノ。もし、幻覚でなければ、きっと瞬間移動させらたのではないかと考えてしまう位リアルな質感と、肌で感じる感覚。零がいつも掃除しているせいでかろうじて『居心地の良い汚れ』レベルで止まっている事務所内も、ついさっきまで誰かがいたように灰皿に置かれた一本の煙草からゆるゆると立ちのぼる煙も、そして室内の匂いも。 きぃ、と奥の扉がいつものきしみを持って開きかけ、その中からちらりと見慣れた人物の横顔が覗いたように見えた。 シュラインの目が、揺らぐ。幻覚だと、自らに言い聞かせても…それでも、毎日のように通っているこの事務所はとても幻のようには見えなかったらしい。嵐と遮那が引きとめようと伸ばした腕より早く一歩足を踏み出す。 皆が危惧していたような、足を踏み出したシュラインが掻き消えるといったようなことは起こらなかった。 ただし。 皆の足元は、ひたひたと押し寄せる薄い波の上にあった。足の下は酷く濃い青に見える、深くまで澄んだ湖。 ――湖の、上。 広い湖は周囲をぐるりと険しい山に囲まれている。空は低い位置を薄墨を掃いたような雲が平べったく山々の間を縫って移動しており。――どこかで見たような、そんな景色の中で。 ふと何かを見つけたシュラインがすっと身体を足元へ折り曲げて何かを拾い上げた。 見覚えのある銘柄の煙草――其れは、先程皆が居た事務所の主が好んで吸うもの。 そして。 ぽとり、と。 もう1つ、同じ銘柄の煙草がシュラインの足元へと落ち。 顔を上げる前に、すぐ見える位置にあった革靴を履いた足へと目が引き寄せられた。 ――その異様さに意識を払う前に、皆は他のモノに目を、意識を取られていた。 シュラインの目の前に事務所の主である武彦が現れたのと同時に、他の3人にもそれぞれ誰かが現れていた。 はっ、と息を呑んだのは、4人の中の一体誰なのか、そんなのもはもう分からなかったけれど。 * * * 『どうした』 咥え煙草の武彦が、火の付いていない煙草を口に、目をすっと細める。それは、穏やかな――酷く穏やかな、微笑み。一瞬見惚れそうになりながらも気を取り直し、そして答える事無く武彦を見つめ続け。 『――シュライン?』 軽く語尾を上げるその声も。 楽しい時に目を細め、口の煙草を緩やかに上下させる其れはどう見ても、見慣れた『彼』の姿。 だが、居る筈はない。絶対に。 ――何処の世界かも分かならい、水墨画の世界のような水の上で。 「何のつもり」 シュラインには、余裕が無い。固い表情には其れが顕著に表れている。切り捨てるような言葉も同じく。 『何が?』 「…幻なら、消えて」 相手を想えば想う程、思い通りに行かないもどかしさに泣きたくなる。――今は、何故だかその気分に酷く近かった。だからこそ、吐き捨てるような言葉づかいも出来た。 困ったやつだ、と言わんばかりの肩を竦める様子を見るまでは、まだ我慢も出来ていたのに。 『何を拗ねてる?』 「すねてなんか…!」 甲高い声を出しかけ、そして――はっ、と小さく我に返った。 心を下手に乱してしまったら、今も幻だと分かっているこの現状が悪化しないとも限らない、いや、寧ろ悪化の方向へと進んでしまいかねない。 すぅ―― 立ったままの武彦のすぐ近くで呼吸を整え、自分でも落ち着いたと思ってからようやく改めて武彦へと向き直った。 「あなたは、誰」 『――言わなくても分かってるだろうに』 小憎らしい程彼らしい答えに、ゆるりとシュラインが首を振り、 「武彦さんじゃないことだけは、確かよ」 そう言いきった。相手に恨みは無いのだが――いや。武彦の姿を取って現れただけでも十分過ぎる恨みの対象になる。だが、息を整えたせいだろうか、視線がやや強まったもののそれ以上の動きは無かった。 ぱん。 酷く頼りない音と共に、武彦の頬を叩いた以外は。 …まさか、あの一撃だけであっさりと武彦が消え去ってしまうとは思わなかった。 * * * 「――」 クミノの目の前には2人の人物が。 それは彼女も良く知る――にこにこと楽しげな笑みを浮かべ続けている中年の男女2人。 『おいで、久実乃』 父親そっくりの其れが呼ぶ。――クミノの、通り名を。 「―――――」 自然、目蓋は薄く閉じられ、そして視線は鋭く、細くなって行く。 それは、幻だと分かっているため。 それは、分かっていても許せないことがあるため。 『どうしたの?おいでなさいな』 母――らしきモノが何か言っている。其れを遮断する――2人の言葉も、自ら溢れ出そうとする感情も。 そのくらい出来なければ、これからやろうとする事が出来なくなるのだから。 「お父さん、お母さん」 なんだい?と、酷く遠い昔に聴き覚えがある、柔らかく笑みを含んだ声に、一瞬何かを思い出しそうになった、が――其れを無理やり消し去って駆け出していく。 くん。 2人の元へ行こうとしたクミノの足を、何かが掴んだ。足元を見下ろし、そして其処に居たモノを見て酷く冷たい表情に変わっていった。 クミノの足を押さえていたのは、遥か昔に何処だったかで相手した記憶のある1人の…女の子だった。 必死でしがみ付くその姿は、見えているだろうに意に介すことなくにこにこと笑い続けている2人と酷く対照的で――そんな事を考えていると不意に足を針でつついたような痛みを感じ、再び下を見る。 にぃっ。 体中から血を流しながらも、自分を倒したクミノに一矢報いようとしたのか、クミノの足に爪を立て、噛み付いていく。くっきりと残った歯形からは血がにじみ、クミノに立てられた爪は抉り取るように足の肉へと食い込んでいた。 「…駆除するよ」 ぽつり、と呟くクミノ。その言葉を聞いたからかそれとも殺気を感じたのか、びく、と竦みあがった少女は水の中へと溶け込むように消えていった。 「―――」 残ったのは2人。 人形か何かのように、2人仲良く立ったままクミノに笑いかけている。その穏やかな表情はとても幻とは思えず、だが幻とでも思わなければこの場に居ることも在り得ないと結論は付いている。 幻を消す方法、単純なものは2つある。 1つは自らを傷つけることで意識を戻そうというもの、だがこれは先程少女に噛まれた時に何も変化が無かったために無効と分かっている。 もう1つの方法は――幻を作っている『核』を破壊するというもの。 そして。 クミノは躊躇いも何も無いまま、『両親』へと無遠慮に攻撃を――華麗なフォームの蹴りと突きを繰り出し。 2人が全く抵抗しないと言うのに、何故だか手加減といった方法はクミノの頭からあっさりと吹き飛んでいた。 2人が、交互に折り重なって倒れるまで。 * * * 『遮那君』 その女性は、他の人間など見えていないように遮那しか見ておらず、そしてゆっくりと近づくと唇に邪気の無い笑みを浮かべつつ、柔らかな――労わりの表情を見せて。 まるで包み込むように。 そっと――遮那の身体を抱きしめて行く。 その間の遮那は何をするでなく、直立のままで、その女性を見ることが出来ずに肩越しの遠くの風景を見つつ、 「離れて下さい。――」 口の中だけで、その女性の名か、それとも他の呼称か、そんなものを呟いたようだったが誰の耳にも其れは届かず。 ぐい、と肩を掴んで押し離し、そしてまっすぐ女性を見つめ。 「――此れは…夢かもしれない、夢じゃないかもしれない」 けれど、とポケットから持ち歩いている24枚のカードを取り出し、細い指先で神経質なまでにシャッフルする。 「貴女の姿だけは、許す事は出来ません」 ぱらぱらぱら、数枚のカードが手元から落ちた。其れを意に介す事無く、遮那は一枚のカードをめくり相手に突きつける。 『――?』 かくん、と可愛らしく首を傾げるその姿。其処へ差し出されたカードは――塔。 その瞬間。 目の前の女性が、何処からとも無く現れた雷に打たれ、激しく痙攣してばたりと後ろ向きに倒れこんだ。 『嵐…』 ふわり。 柔らかく、現実味の無い笑みが、目の前に立っている女性から言葉と共に零れ落ちた。途端、 「やめろ――――ッッ!」 ぶわっ、と、嵐から『何か』が噴出した。それは見る間に形を変え――そして目の前に立っている女性へと刃物の輝きを持って降り注いで行く。 「ちょっと…」 ひやりとしたものを感じたのだろう、シュラインが嵐へと手を伸ばし。 嵐は片手で、爪が白くなる程力を込めて頭を押さえつけながら尚もその、穏やかに微笑む女性に向かって牙を剥き出していく。何が彼をそこまで追い立てているのか、それは彼ではない他の者には分かりようが無い。 ただ、これだけは言えた。 その女性に対する嵐の顔は、殺気等何処にも見当たらない。むしろ、酷く歪んでいた。今にも泣きそうに。 嵐はただ微笑み続けているその女性に向かい、激しく攻撃を繰り返しながらも。 何故だか、傷ついているのは彼自身だった。 ぴし。 女性の笑みに、文字通りヒビが入る。顔中央からぴしぴしとヒビが広がり、それはその女性の身体に沿って体中にモザイクを描き出していく…時折ぱらぱらと欠片をこぼしながら。 「っく、が…ッ」 痛みが襲ってくるのか、爪を立てた部分から滲む血に構うことなく手に力を込め、何か吐きだしでもしているのか呼吸を荒げる嵐。 つぅ、と額を伝って降りた赤い筋が、まるで…血の涙を流しているように、見える。 ――――リィン…リィ、ン… 砕けた女性が倒れた際の酷くかすかな音が、皆の耳に、心に、響き渡った。 * * * 気付けば―― 皆、元の、自分の部屋に戻ってきていた。寝ていたのか、奇妙に体がだるかったがそれ以上のことは無く、のろのろと身体を起こす。 「――」 起き上がった視線の先に、酷く薄いガラスのようなものが見え…そして、それは暫く待つうちにすぅ、と空気に溶けて消えていった。 嫌な予感がし、仕舞ってあったボールを入れていた、もしくは包んでいた中身を確認すると、やはり割れていたのはその中のひとつだったらしく、1つずつ中に入っていた珠は減っており。 そして、残っていたモノを見て、小さく息を呑んだ。 * * * 「ありがとう」 艶やかに沙耶が笑う。その唇は、紅を塗っているのか、それとも地なのか、いつ見ても色が褪せることは無い。 一晩預かったその品を受け取りに来た沙耶は、細かい細工を施した函を手に最初に皆がいた場所――ロビーのソファで寛いでいた。 礼を言いながら、1人1人から品を受け取り、自分でも良くひとつひとつ拾い上げては見つめ…そして満足の息を漏らした。 「完成したのね。…満足の出来だわ」 す、と顔を上げて、1つの珠を指先で持ち上げる。皆の視線も自然そこへと集まっていく―― 「此れはね。真珠なの」 その視線に気付いているのかいないのか。まるで独り言のような囁きで、沙耶が口を開いていく。 「真珠?」 あの発泡スチロールめいたのが?と嵐が言いかけ、だが沙耶の手の中にある透き通った珠を見て口をつぐむ。 「そう」 僅かな頷きの後で、再び珠へと視線を戻し。 「蜃気楼の謂れは知ってるかしら」 突然、取りとめも無い言葉を口にした。きょとんとしながらも、頷きを返す数人にちらと視線を送り、 「この珠はね。『蜃』の核とでも言うべきものよ。あなた達に始め見せた時は、まだ虚ろなままだったのだけれど」 さらりと。 とんでもないことを言い出した。 「どういうこと」 クミノの視線が、次第に針のような鋭さを増していく。いつでもその細首を貫ける、とでも言うように。 「あの珠が『宝珠』としての役割を果たすためには、養分が必要だったわ。――そう…これ以上は言わずとも分かるわね?」 にこり。 「幻は珠が生み出した物ではないわ。あれは――貴方たちの様々なモノを吸い出した欠片」 そして、と再び、柔らかな視線を珠へと注ぐ。 「吸い出して…楼を築くの。この、珠の中にね」 沙耶の微笑は皆に向けられている。それでいて、とても遠い、遠い――誰にもたどり着けない何かを見ているようでもあり。 「…綺麗ね。本当に、綺麗」 各々違いはあるものの、発泡スチロールめいた白々しさを見せていたボールは、正に珠となり――不思議な輝きを見せていた。 遮那の持つ珠は淡い空の色を。 嵐の持つ珠は穏やかな緑を。 シュラインの持つ珠は鮮やかな赤を。 クミノの持つ珠は水底の目を打つような紺を。 それでいて、手の平に乗せれば接している部分が透けて見え、指で摘んで翳せば中に何かがいるように見える。 そして――割れずに残ったそれ以外の珠は全て様々な色を見せながら輝いていた。 「そう言えば、高峰さんもあの珠を持っていましたよね?…やはり色が変化したんですか?」 遮那がようやくと自分の珠から視線を外し、訊ねる。 「――私の色?」 それに返す言葉は肯定を含んでいるのか、語尾をゆるりと上げながらも是も否も言わず。 穏やかな笑みは崩す事が無いまま、沙耶が小さな袋から何かを取り出す。 はじめ、それは黒い布でカバーをかけているだと思っていた。 だが、それは。 「この中に宿る幻…見てみたいと思う?」 ――光さえも通さない、闇色の珠。 沙耶の愛猫よりも更に黒く、深い。――負の感覚は無い。無い、が。 「……」 4人はゆっくりと首を振った。 「そうね。それが良いかもしれないわね」 そう言いつつ、受け取った全ての珠を用意の函へと――丸いくぼみを幾つも作ったビロード張りの函の中へと丁寧に一つ一つ収めていく。 「そうそう。今夜のメニューは蛤料理だそうよ」 楽しみね?と少しばかり悪戯っぽい笑みを口の端に浮かべながら、 「礼は戻ってから――」 そう言い、さらりと立ち上がって優雅に部屋を出て行った。 「…蛤料理?」 嵐がぼそりと呟き、 「大蛤だったりして」 くすっと笑いながら遮那が沙耶の去った後を何気なく見つめ。 「――真珠を取った後の貝柱を食べるみたいね…」 「…食欲が無くなってきた…」 シュラインの言葉に、クミノはうんざりしたような表情で首を振った。 □■■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■■■■■□ ■ 登場人物(この物語に登場した人物の一覧) ■ □■■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■■■■■□ 【整理番号 / PC名 / 性別 / 年齢 / 職業】 【0506/奉丈・遮那 /男性/17/占い師 】 【2380/向坂・嵐 /男性/19/バイク便ライダー 】 【0086/シュライン・エマ/女性/26/翻訳家&幽霊作家+草間興信所事務員】 【1166/ササキビ・クミノ/女性/13/元企業傭兵 】 NPC 蓬莱 高峰沙耶 |
|
|
|
||
|
|
||
|
|
【個別ノベル】 【0086/シュライン・エマ】 【0506/奉丈・遮那】 【1166/ササキビ・クミノ】 【2380/向坂・嵐】 |
|
|
|
||
|
|