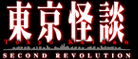 |
|
|
|
||
|
|
調査コードネーム:百年仕掛けの睡魔 執筆ライター :栗須亭 【オープニング】 【 共通ノベル 】 【 個別ノベル 】 |
|
|
|
||
|
|
||
|
|
 【オープニング】
【オープニング】深い緑を覆う朝霧。 白のレースは赤い回廊にも微かに届き、一瞬、雲の中に取り込まれた、という幻想にうっとりしてしまう。 中華風の装飾に目をやる。小さな凹凸と、連続する幾何学模様。ラーメンドンブリの縁を連想してしまう自分に、小さな幻滅。 富士の嶺が近くに見える。今すぐに、飛び出して向かいたい。という気持ちにならないのは、手前に広がる樹海の存在が明確だからだ。綺麗ではあるが、一種の誇張された美しさ、あるいは畏怖によってもたらされる感覚に近い。本当は、それほど綺麗な物でもないであろうに。と、考えるのはリアリストとしての性質なのだろう。 碇は絨毯の感触をハイヒール越しに確かめながら、朱色の手すりを右手の人差し指でなぞって歩いている。曲面の手すりには、微小な水滴が付着していて、指でその脆弱な水滴たちを薙ぐことで、ある種の快感を得る事が出来る。すでに快感というより、本能的行動に近い、癖になっているのだが。 ただ、感心したのは、その手すりがとてもツルツルとしていて綺麗だった事。滑らかな手触りに、少し陶酔していたのかもしれない。 フロントロビーで少女に荷物を預けてから、数分経つ。歩きながら、建物の平面図を想像していたが、思ったより広いフロアに驚いた。遠くへ行くほど不気味に静かで、戻れなくなってしまいそうな錯覚を感じるようになる。少し遠くで左右に別れる分岐が見えた。右へは、クランクしながら外面沿いに回廊が続いている。左方向は部屋の壁が障害になっていて、ここからではわからない。 分岐路までやってくると、左側を確認した。朱色の手すりと、外の景色。どうやら、向こうの回廊と繋ぐ通路だったようだ。割と広い、二メートルほどの通路。通路というよりも、直角形の空間、と言った方が正しい。それよりも、碇はその空間にぽつんと置かれたオブジェクトに興味を持った。手すりから指を離して、それに接近する。艶のある彫刻台に置かれた、小さな桜の盆栽だ。細かなひびの入った青磁器。その小さな檻の中、桜は見事に落ち着き払っている。しかし、その見事さは、かえって嘘くさい印象を与えてしまう。特に、このリアリストには。碇は行動を決めると、濡れてしまった右手の人差し指を、親指で擦り拭った。 碇は、花びらへ手を伸ばす。造花ではないのか、という疑惑を払拭するため。そして、今に触れるか、という場面。花びらの感触を指先のごく僅かな部分が、脳へ信号を伝達するや否やのこと。薄ピンク色の花びらは、器の形にはまった土壌へ墜落してしまったのだ。本物か、と心の中で呟き。悪い、と桜へ、あるいは桜の持ち主へ呟く事で、ちっぽけな贖罪を施す。 何か、諦めた気分になった碇は、踵を返してもとのコースへ戻る事にした。また、手すりの水滴を相手にしなくてはならない、という使命があるのだ。手すり沿いまで戻ると、直角、左へ曲進。クランクコースはドライブでも得意なものだ。進行方向には、左へカーブする手すりと、森と森の香り。ようやく、建物の最遠端まで到達したようだ。きっと、U字にカーブして、先ほどの桜の盆栽を点対称に通じる反対側の回廊へループしているのだろう。 碇は手すりの水滴を薙ぎながら、正方形の三面をなぞるように旋回した。そして、先ほどの直角形の空間へ繋がる分岐路(対称側)で立ち止まった。左手側には、桜の盆栽。その奥に、クランクカーブ。 違和感。 二秒間が経過した。 霧がかった森林。 冷たく、ナーバスな空気。 遠くで烏が鳴いた。 桜に近寄る。二点を結ぶ、見えない直線を、碇は辿る。 花びらが、碇が落としたはずの花びらが消えていた。 そして、それは、 いや、断言できようもない。 落としたはずの花びらが、元に戻っているように見えた。 碇は、花びらに触れようと指を差し出した。そして、やはり、微かに触れたと同時に、花びらは落ちてしまった。他の花びらにも触れてみるが、触れただけでは、どれも落ちない。あたかも、繰り返しているように花びらは落ちた。 りん、と鈴の音。 「どうかいたしましたの?」と、少女が呟いた。碇は首だけ振り向いて、いえ、と一言だけ返答する。ばつの悪い気分をどこかで否定しつつ、しかし、一方では、呆れてしまう行動をとった自分を卑下したい気持ちになった。 いや、待て。やはり、勘違いではないだろうか。今しがた、桜の花びらに気がついた誰かがそれを拾い上げただけなのだ。そして、その誰か、というのがこの少女にあてはまる。彼女は私と対称側の回廊を歩いていて、私が外側を回っている間に花びらを回収。そして、先ほど落ちた花びら、そして錯覚は偶然。完璧だ。まさに、ベスト・オブ・リアル。これ以外の推論はあり得ない。事実を100%撃ち抜いている(それも、もの凄い火力でだ)。間違いなく確実。審査員も納得の論理構築。どうだ、これが碇麗香だ! 一度、口先でため息を吹いた。 「ああ、ええと、部屋まで案内お願いできるかしら?」 「はいな。お荷物は蓬莱が先に届けさせて頂きましたの」 そう言うと、少女は髪留めや、膨らみのある着物の裾についた鈴を鳴らしながら、回廊を戻った。碇もその鈴の音を二メートルおいて追跡した。 しかし、妙なイントネーションを抜きにしても、どこか浮世離れした少女を眺めていると。碇は、先の推論の評価を下げずにはいられなかった……。 【ライターより】 初めまして、栗須亭と申します。今回が初の物語になるので、それなりの覚悟をしておくことをお勧めします(笑)。 話のきっかけは、この碇氏の不思議な(?)体験になります。なぜ、花びらが元に戻ったのか。この旅館の秘密にせまってください。 しかし、これは一種のサイドストーリー。タイトルとオープニングが、今ひとつかみ合っていませんよね。話は、蓬莱館の探索と、館の少女、蓬莱と話を重ねる事で展開する仕組みです。 ミステリィドラマが織りなす多元展開仕様。推理と推理のテーマパーク。推奨参加人数は4人〜。 倒錯の館はいかがでしょう。 『※キーワード設定をお願いします』 四季 料理 睡魔 誤差 卓球(※※) (※説明) キーワードをキャラへ割り振ってください。一人(大人数の場合、一グループ)一つのワードを選ぶ事で、役割を持つ事が出来ます。 参加人数が三人以下の場合、ワードは余っても構いません。余ったワードはこちらでランダムに割り振りますのでご了承を。 (※※説明) ネタバレですけど、熱い卓球の試合が行えます。カップル、ライバル、師弟などの関係の方、スポ魂で爽やかな汗をかきましょう(正直、コメディです)。 なお、『卓球』に限り、他のワードとのダブリを認めます。 例)「PC(A)とPC(B)で卓球。さらにPC(A)は料理で。PC(B)は睡魔」 という事が可能です。 ダブルスも可。 |
|
|
|
||
|
|
||
|
|
【共通ノベル】 1 バスは国道を外れて、山道を登る。そうしてから随分経った。正弦波のように滑らかなカーブの連続。左右へ軽い加速度。その度に身体が傾く。見えない糸で引っ張られているようだ。誰もが、見えない糸を身体に繋いでいるのだ。見えない赤い糸で結ばれているのよ、というフレーズを思い出した。見えないのに赤色が識別できるとは、全く矛盾しているではないか。彼女は、そんなことを考えているうちに眠ってしまった。昨夜に飲んだアルコールが、まだ体内に残留しているようだ。眠っているのか、起きているのか、今も判断が怪しい。ここはバスの車内だ、と微かな理性が、遠い星の輝きのように何光年もかけて言葉を発する。少しだけ頭痛がした。目が覚めてきた証だろう。一定のリズムを刻んで、断続的に側頭部が痛む。ゆっくりと瞼を持ち上げた。外の景色を眺めてみると、一面のパノラマに山、そして森林。まだ霧がかかっていて、遠くの方はよく見えなかった。腕時計を見ると、時刻は10時になろうという所。すでに二時間ほど走行しているはずだ。もちろん、寝ている間にパーキングエリアに入ったりしていたのなら話は別だが。ただ、その可能性を考慮したとしても、目的地はそろそろではないだろうか。しかし当然、その予測に意味はない。 葛生摩耶は、車内でも後方の位置に座っていた。自分より後ろに座っている人間はいないはずだ、と思い、後ろを振り返ってみるけれど、やはり誰も座っていない。前方に視線を戻す。女性が二人と男性が二人。内三名は顔見知りだ。高峰と碇、とその部下。彼の名前は何だったか、と考えたが、一瞬で諦めた。もう一人、男性が一番前、運転席の真後ろの席に座っていたが(と言っても、ほとんど横になっている)、全く見覚えがない。おそらく、交代のドライバだろう。着衣の襟部分が独特な色見の青をしていた。 摩耶の席から通路を挟んで左側、三つ手前の席に、碇麗華が座っている。そして、そこから通路を再び通路を挟み、二つ手前の席には彼女の部下がいる。摩耶を原点に置くと、y軸方向へ5進んだ所だ。碇から四つ手前の席には高峰が黒猫を抱いて着席している。バスの車内へ動物を連れ込んで良いものだろうか、という疑問は、彼女ならOKだろう、という回答で一蹴される。その黒猫が、高峰の肩越しに乗客達を観察している。もしかしたら、見張っているのかもしれない。碇はと言うと、何かの雑誌を読んでいるようだ。紙の擦れる、軽やかな音が一定間隔で聞こえてくる。彼女の部下の男は、熟睡しているようだ。そう言えば、車内の五人を線で結ぶと、冬の星座になる。名前は思い出せなかったのだけれど。確か、北極星を見つける時に役に立つ、という断片的な情報だけは思い出せた。 もう一度、緑を眺める、遠くに赤い色の建物が見えた。数キロほど離れているが、鮮やかすぎるほどの赤が、遠目にもはっきりと映る。しかし、自然への侵攻を始めた人の文明を思わせない。異様だが、自然界に調和している。あるいは、建物の周りに自然が栄えているのだ、というパラドクスを感じさせる。その時、妙な音が車内に響いた。詰まった排水溝のような、小さな断面積の空洞を、空気が吹き抜けるようなノイズ。音の発信源は、碇の部下の男だった。そこを中心に、音の波が拡散している。今度は周波の高いノイズ。碇の方角だった。彼女は、雑誌のページを破りとり、おにぎりを作るように紙切れを整形すると、手首を軽くしならせて、それを投射した。目に見えない緩やかな坂道を下るように紙のボールは加速を増し、位置エネルギィを運動エネルギィに変えて、男の後頭部へ。一瞬、地面と垂直して軽やかに弾み、水平方向への運動力を失ったボールは上空で急旋回し、そのまま落下した。あのインパクト後の跳ね方を見ると、どうやら消しゴムか、それに準ずる物が内包されていたに違いない、と分析。男は身体をぴくっと震えさせると、急いで右手を頭にあてて、まるで銃で撃たれた痕を探すかのように多少大げさに反応した。男は碇と目が合う。 「うるさい」とタイミングを見計らったかのように碇が言った。抑揚の無い発声である。「醤油とって」という言葉を言わせても、大して違和感のない口調だった。 摩耶はそれよりも、高峰の黒猫がそのボールを追って戯れてしまうのではないか、と心配した。今は、席の脇から顔を覗かせている。当の本人は、いたって冷静に事態を観察しているのだから、関心してしまう。 バスがほぼ直角に曲がり、進行方向に建物が見えた。朱色の大きな門が霧の中に現れた。 2 荷物を下ろし、玄関で少女が迎えてくれた。ロビーに入り、フロントで高峰が皆のチェックインを済ますと、摩耶は早速自室の確認にとりかかった。一応、話は聞いていたが、エントランスは見るからに中華風の内装である。朱色をベースに金色の装飾、というパターンが多く見られる。摩耶はフロントカウンタで少女に部屋の鍵をもらうと、ラウンジの壁にあったパネルの平面図に目を通し、場所を確認した。建物は左右のウィングに分かれ、ほぼ左右対称の構造をしている。ただ、外から見れば、完全にシンメトリィに映るだろう。階層は二つ。摩耶の部屋は、左ウィング二階の突き当たり、丁度直角に折れている部分にあった。ところで、外面を見た限り三階はありそうなものだったけれど、中に入ってみると空間が大きくとられていて、天井がとても高い。天井には格子状に梁が巡っていて、一定間隔ごとに照明が取り付けられている。そして、綺麗だ。意匠に凝っている、という芸術的な美しさももちろんだが、一つ一つのアイテムが真新しいような光沢を放っている。建造してからまだ間も無いのだろう。あるいは、想像絶する掃除の苦労の賜物だろうか。見た所、従業員はそれほど多く無さそうだ。出迎えも少女一人が行っている。それもまだ、十代の中ほどにしか見えない。旅館の女将の娘だろう、と予測した。 ロビーから碇が出て行くのが横目に見えた。彼女の部下は、いつの間にかいない。建物の観察をしにいったのだろうか。摩耶も、密かにその行動をおこしたくなった。部屋へ一度戻ったら、探検してみよう、と決める。そうと決めてトランクをとろうとして、少女に声をかけられ引き止められた。荷物を運んでくれるそうだが、二つ返事でそれを断った。赤い絨毯の上をトランクを転がしながら、ロビーから出て、階段脇のエレベータに乗った。場所はほとんど把握できている。エレベータのコントロールパネルには、やはり階層は二つしか無い。低い動作音と共に、下向きの加速度を感じた。数秒ほどで重力は緩やかに元に戻る。二重扉が重々しく両側へ収まると、二階のラウンジが見渡せた。大きな窓の向こうには、なだらかな緑の曲線。緩やかな高低差で作られた自然の造形だ。二階の内装は落ち着いた洋風の間取りになっている。柱が無く、移動のストレスがない。色相も明るく、ベージュの絨毯に、白い漆喰の壁。所々に絵画が飾られていて、窓際には観葉植物が病人のように静かだ。エントランスへ入る時の角度では、二階の内装までは展望できない。おそらく、視線の入射角度を計算して、地上から見えないような工夫を施されているのだろう。現に、ラウンジはロビーの半分程度の面積しかない。それでも、充分広いと思えるほどに開放されているのだけれど。ラウンジの大きなはめ殺しのガラス窓に挟まれて、中央にガラスの扉がついている。その先は長方形のデッキになっている。二階ではデッキだけ中華風になっているのが中からでもわかる。外際に沿って、朱色の手すりが連続している。四つの角には、大きな柱。梁と柱頭には細かい彫刻がある。そして、その上には大きな屋根。窓から見上げるように覗くと、刺繍のような模様が確認できる。荒波に揉まれる舟のようにも見えるが、抽象化されていて良くわからない。 部屋の番号を確認してから、ドアのロックを解除する。二階が洋風になっているのは、おそらくこのためだ。襖や引き戸では、セキュリティ面の心配がある。インテリアを統一することで得られる景観よりも、宿泊施設等では、個人の安全を第一に考える物なのだ。和洋の差異とは、内と外を遮断することへの厳密な定義ではないだろうか。 ドアノブを回転させ、肩から肘を使って押し開けた。片手でトランクを支えているからだ。入り口から寝室までの薄暗い空間を抜けると、大きなベッド。そして、窓と朱色のテラス。一瞬、声を上げそうになったが、思いとどめた。まず思い浮かんだのが、一泊幾らだろうという品の無い計算だ。ほぼ長方形の、大きな部屋だ。玄関から正面に大きな窓が二つ、左手にも一つある。薄いレースのカーテンで覆われているので、景色は薄らとしている。右手の奥には、屋根付きの特大ベッド。一体、どうやって部屋に入れたのか、と心配になるほどの巨大さだった。ベッドの三面は、窓にかかっている物より更に薄いレースで覆われている。クロゼットが入り口のドア付近に埋め込まれている。コートをハンガにかけ、トランクを脇に置くと、彼女はテラスの窓の方向へ歩き出した。部屋のコーナには観葉植物と、大きなテレビ。ソファまでついている。彼女は煙草を取り出し、火をつけた。着火音だけが、静かに響いた。ソファへ身体を沈める。テーブルの上に、クリスタルの灰皿。龍の彫刻が施されている。瞼を閉じると、眠ってしまいそうだ。実は、この時間帯は、普段ならば寝ている頃だ。摩耶は風俗で働いている。そう言うと、あまり良い顔をしない人間がむやみに多いのは事実だが、風俗にいる娘でも、将来は警官になりたい、という純朴な希望を持っている人間が少なからず存在していることも事実である。やり甲斐のない営業を、ただ経済的な心配を理由に続けている人間と大差は無い。いくらか楽しめる分だけ、こちらの方が有意義だと言える。だから、時間を無駄にしているという実感は少ない。 細い煙を吐き出す。ゆっくりと拡散し、ねじれ合う。絡まり合う。人のように。自然のように。形をとどめようとする力が働き、一方で、内部から外部へとエネルギィが移動し、絶えず、影響し合い、風に煽られて、関連し合い、法則に従って、漂う。起きていたいという意志と、眠りたいという願望のように、願わなくても、いつかは寝てしまう。それが一つの真理であるかのように、深く、沈み、収束していく。意識を繋ぎ止めるものは、ピアニシモの仄かな苦みと、呼吸という束縛。寝てしまいたい、と誰かが願っている。それは、あどけない少女の囁かな祈りとも思える、決して聞き逃せないような、穏やかな連行。龍を灰で汚す。ランダムに三人の顔を思い浮かべた。 今頃、何をしているのだろう。 3 何も変わっていない。これが永遠なのだろうか、と発想を飛躍させるような力をこの場所は持っている。変わるという事は、性質の不安定さを意味する。変化を求めるという事は、すなわち不完全であるということ。人は他人との干渉を望む。自らの不完全さを露呈することで、心地良いと感じる矛盾。それが潔さなのだろうか。そしてそこに、永遠はない。 断続的な鈴の音。規則正しい間隔で時間を刻む。彼女も、鈴の音も、何も変わっていない。 「何か、変化はあったのかしら?」 少女は頭を左右に回転させる。瞬間的に、髪留めについた鈴が規則を阻む混沌を示すかのように狂乱した。長く薄い桃色の髪の毛が、およそ半周期遅れて、頭の動きをトレースする。一瞬困った表情を見せた。理由は見当がつく。 「気にしないで良いのよ。ギブアンドテイク。そうでしょう?」 「いつも、お世話になりますの」足を止めて、少女が頭を下げた。鈴も声を挟まない。永遠ではなかったようだ。急には動きを合わせられなかったため、二人に三歩分の距離が空いた。 「の、はいらないわ」四分休符でもどこかに記されていたかのような一瞬の静寂の後、そう言うと、ゆっくりと振り返った。微笑を浮かべていた。同時に、少女も顔を上げる。少女も連鎖反応のように、笑顔を真似た。 「はいな。お世話になっています」 「相変わらず、素敵な接尾語ね」 眉を持ち上げた後、少女は目を細めて微笑んだが、おそらく意味は伝わっていないだろう。 高峰沙耶は、小さなため息をつくと、回廊の先を見つめた。少女の肩越しに、逆ウィングにある回廊が遠くに見える。ベージュ色のジャケットを着ている人影を、視界が捉える。人影は神経質そうに、通路のあたりを観察していた。 「あれは、碇さんね。どうしたのかしら」高峰が視線を逸らさずに言った。少女を意識した独り言だった。少女もそれを確認する。決断は早かった。 「あいや、ちょっと伺ってきますの」そう言うと、彼女は高峰に小さくお辞儀をした。そして、すぐに駆け出した。 「蓬莱さん」 「私は、あなたとこの場所を、大切に思っていますよ」 蓬莱は数メートルの所で、もう一度お辞儀をする。彼女は再び鈴の音を従え、スタートした。高峰はその後ろ姿を五秒間ほど観察した。途中から、観察対象が無意識のうちに柱の整列へ転換していることに気付くと、少しため息をつく。すぐ近くで人の気配がした。そちらへ視線をやる。 「ああ、高峰さん」葛生摩耶が反対側の回廊とを結ぶ通路から現れた。両手で黒猫を抱えている。「この子、迷ちゃったみたい」 「それは無いと思うわ」高峰は微笑む。「そうね、あちこちを見学して、懐かしんでいたんじゃないかしら」 「前にもここに?」摩耶は高峰に黒猫を渡す。彼女のシックな黒の衣装と同化するように、胸の上で静かに落ち着いている。 「そう、何年も前になるわね」そう言って、高峰はあての無い方向を見る。漂っている埃を観察する時の猫の仕草に似ている、と摩耶は思った。何とも、ロマンスに乏しい喩えではあるけれど。 「その浴衣、良くお似合いよ」 「え、ああ。うん。こういうのも、なかなかいいなって感じかな」摩耶は左手を突き出し、ボクシングのジャブの真似をした。 「バイクを運転できないのが、難点かしら」 「行動を制限することに意義があったのよ。活発な可動能力を排除する事で、清楚で可憐な行動作法を手に入れたのね。バイクを運転できない、ではなく、運転の必要が無くなった、と考える方が東洋思想的かもしれないわ」 なるほど、と摩耶は頭を揺らす。 「あ、高峰さん。夜は皆を集めて麻雀やりませんか? ここ、雀荘あるんですよね」摩耶は館の平面図を思い出す。その部屋は、右ウィングの奥手だった。 「ええ、断る理由が無いわ」 「面白そうね」 4 着替えには十分ほどかかった。慣れない服装なので、手際が悪い。黒い生地と、袖や裾にはえんじ色のラインがある。来る前にオーダしておいた色相だ。レースに囲まれたベッドの上で発見した。四角く、礼儀正しく鎮座しながら待機していたようだ。赤のチューブトップと、ロングコートはクロゼットに仕舞っておいた。眠ってしまおうと考えていたが、この浴衣を発見し、着替えているうちに目が冴えてしまったので、結局旅館の探索をしてみることにした。とりあえず、目指すは温泉。土産物も一通り見ておきたかった。 昼まではまだ少しある。午前十一時を半分ほどまわった頃だ。しかし、平面図を見る限り、建物の奥行きは相当深い。左ウィングを見て回るだけで30分は消化できるだろう、と計算した。 鍵をドア横のホルダから抜き取る。キータグがホルダに収まる事で、電気系統が稼働する仕組みだ。抜き取ると、もちろん、ブレーカが落とされたのと同じ状態になる。部屋を出て鍵をかけようとしたが、自動ロック式だったらしい。無駄な動作に時間を数秒ロスしてしまった。テラスのあるラウンジまで行くと、エレベータで一階へ降りた。 エレベータから出ると、左手へ回廊が続いている。右手方向にはフロントロビーがある。エントランスをすぐ左手へ向かっても回廊があった。エレベータ側の回廊は建物の内側を沿っている。大きな庭園が展望できた。大きな岩や、和を思わせるような、流線を象った小石の造形。朱色のアーチ橋。小さなジオラマが、そのまま巨大化されたような風景だ。作り物であるという認識が、逆に現実を遠ざける。遠くの方を覆う霧も、その効果を演出する。もう正午近くだというのに、朝のような静けさ。気温も、湿度も、鳥のさえずりも、とても澄んでいる。使われた、という形跡を見せない。誰も吸わない空気。誰の皮膚にも付着していない水滴。太古から何にも触れずに過ごしてきたような、腐敗しない真新しさ。それらが孤独という秩序を守りながら、ただ規則的な循環を繰り返してきたようだ。 少し遠くで、回廊が右に折れている。右を曲がるとその奥には、浴場がある。意識を近くに戻す。回廊は数メートル先で、クランクしていた。ここに来るまでに見当たった土産物の売店は、ほとんどがまだ開いていなかった。開いている店も、従業員の姿は見えなかった。本当に大丈夫なのだろうか、と心配にさえなる。クランクカーブの手前で、足を止めた。反対側を見ると、外縁をはしる回廊と、さらに連絡通路方向を奥へ伸びている渡り廊下。どうやら、厨房らしい。ダクトからは白い煙が雲を精製している工場のようだ。食器が接触するような、いかにも生活的なサウンドが小さく聞こえてくる。 旅館の経営に関して安堵のため息をつくと、摩耶はクランクカーブを曲がろうと視線を進行方向へスライドさせる。そのスキャニング途中で、ピンク色のオブジェクトを知覚したことを、数秒遅れて脳が認識した。桜、だったと思う。摩耶は視界を連絡通路に戻す。通路の中ほどにあったのは、小さな桜の盆栽だった。青く四角い陶磁器の中で、慎ましく花を咲かせている。 小石を敷き詰めた土壌に、身を削られて形を整われた桜の盆栽である。ピンク色は、淡く、白味がかっている。小石の上に、ひと枚の花弁が落ちていたのに気がついた。小鳥がつついたりでもしたのだろうか、まだ萎れていない新鮮な花弁だった。良く見てみると、花弁の足りない桜の花を見つけた。そのパーティだけ四枚だった。摩耶は落ちていた花弁を優しく拾い上げると、その花弁を元の場所に戻した。特に理由があった訳ではないけれど、不思議と笑いがこみ上げてくる錯覚がある。客観的にこの行動を観察すると、とても面白いと思えてくる。無意味な行動ほど愉快なものだ。 クランクカーブの奥を行くと、内外の回廊が合流し、浴場方面への回廊へ統一されていた。しかし、これ以上は先に進めそうも無い。準備中と書かれたつい立てが行く手を阻んでいる。浴場の開放は午後2時から、と柱の掛け札に記載されていた。仕方ないので引き返す事にした。 今度は外縁沿いの回廊を通って戻る事にした。遠目に厨房の離れへと繋がる渡り廊下が見える。しかし横から見ると、廊下と言うほどの距離は無い。あるいはブリッジに近い。 黒いものが動いた。連絡通路の壁の下付近である。摩耶が近づいてみると、壁の陰に潜むように黒猫が座っていた。高峰の猫である。 「あれ、もしかして迷っちゃった?」 摩耶の問いかけに対して、黒猫は無口に、厨房を眺めている。そもそも摩耶は、この猫が鳴く所を見た事が無い。これが平常的な反応なのだろう。摩耶は黒猫を胸に抱いた。しっとりとして柔らかい毛の手触りが心地良い。彼(彼女かも分からないが)はというと、ぬいぐるみのように動かない。 摩耶が立ち上がる時、桜が視界に入り込んだ。スローモーションを見るように、じっくりと観察した。 同じ位置だ。 同じ花弁だ。 戻る、という認識を考えた。戻った? 戻るとは? 小石の土壌に、ひと枚の花弁。先端に向かうほど赤みを帯びて、中心へ向かうほど、白く淡いグラデーション。 何も変わらない。 秩序だ。 規則だ。 摩耶は目を閉じて、先ほど見た映像を再生する。黒い石と、白い石。青みを帯びた、ひび割れた石。それらとの相対位置。幹から花弁への距離。軸方向。いずれも、大きな変位は感じられない。既視感覚という知覚でもない。しかし、記憶に自信があるわけではないので、多少の誤差があることは認めなければならない。 短絡的に飛躍させれば、同じ位置に花弁が戻った、という帰結になる。常識的に考えて、その可能性はゼロに限りなく近いのだけれど。もちろん、ただ一つの仮定、この場所が常識の範疇ではない、という可能性を排除してに限られる。 摩耶はため息をつく。おそらく、猫が台の脚に触れた際の振動で落ちたのだろう、という無難極まりない仮定を想像したからだ。火曜サスペンスのような展開を待ち望んでいる訳ではないのだが(容疑者と被害者、真犯人の配役を考えると、明らかに人員不足であるし)、普通の人間は、思考も行動も、世界の有り様も、普通であるようにとシミュレーションをするようなパターンが、すでに常套の解析手法として取り込まれているのだ。誰も言わない事なのに。誰も教えていない事なのに。自然に身に付いた、社会の汚れのようなものだ。 内側の回廊から声が聞こえた。話しているのは、女性の声だ。走り去る足音が聞こえる。同調、連動するように、鈴の音も聞こえた。摩耶は通路から顔を出す。 黒いドレス。 裾が風をはらんで波を作っている。 摩耶に抱かれた彼も、そちらを振り返った。初めての躍動だ。 「ああ、高峰さん」 5 昼食は二階の食堂で四人揃ってとった。摩耶が入室したときにはすでに配膳は完了されていたので、随分前から支度はされていたようだ。席は碇と摩耶が隣同士。その対象側に高峰と碇の部下の男がいる。 内容は人数に反比例して豪華なものだった。山菜と海鮮の天ぷら。高級そうな刺身。その他にも、懐石料理のように、一品ものの料理が小分けに盛りつけられている。一方で、食事中の会話の流れは碇が制していた。三年ぶりの休暇だとか、取材先のクライアントでの部下の不手際への言及、上司の判断に対する適正度への意見など、話のおよその構成は不平と不満に満ちていた。しかし、そういう話は割と面白い。安心できる、という感覚かもしれない。時々、碇の部下の男が訂正の発言を挟んだが、碇はそれを何倍もの勢いで追いやった。そういう情景も、苦笑しながらではあるが、なかなか微笑ましいものである。 「そもそも、なんであんたが私についてきているの? ってことよ。折角の休暇が台無しよ、まったく」 「そ、そんなつもりはありませんよ。僕は、ただ、高峰さんのお誘いに乗っただけで」 「ああ、そう。それは幸運だったわね」 碇はため息を落として、刺身に手をつけた。どうやら、彼女なりの皮肉のようだ。摩耶は横で聞いていて、少し笑いそうになる。 「ええ、まあ」 「何ですって?」碇は象牙製の白濁の箸を、ダーツのように持ち構えた。 「わあ、ごめんなさい」 「本当、疲れるわ。ビールでも頼もうかしら」 「あ、そうそう。夜に皆で麻雀しませんか?」摩耶はずっと頃合いを図っていた。碇が疲れてきたくらいが丁度良かった。 「ええ、私は構わないわよ」碇は箸を持ち上げて意思表示した。「あいつも麻雀くらいできるだろうし、高峰さんは?」 「高峰さんも大丈夫ですよね?」摩耶は再度確認する。 「ええ。返事は先に済ませてあるわ」 「よし、じゃあ、五時に集合ってことで。場所はロビーから右へ出て、ずっと奥です」 「ああ、あの、桜のある所か」 「え?」予期しないフレーズに、摩耶は緊張した。 「ん。向こうの奥の方にね、桜の盆栽があるのよ。それが目印になるわね」 「へえ。逆側の方にも、桜の盆栽がありましたよ」 「あれ、そうなの? でも、ちょっと、あれ、不思議よねえ」そう呟いて、碇は上を向いた。何かを思い出しているような表情を浮かべている。摩耶の心拍は早まっていた。言うべきか否か、その判断を何度も優柔しては押しとどめる。 「まあ、いいか。それより、温泉よね」 「浴場の開放は2時からだそうですよ」 「じゃあ、これが終わって一休憩したら、ゆっくり堪能だわね。本職の身体も、じっくり取材してやるんだから」碇は企むような微笑を浮かべて、摩耶に視線を送った。 「うわあ」 摩耶には苦笑するしか余地はない。結局、桜の話題には戻れなかった。その後悔もある。 1時過ぎには昼食を終え、4人は一時的に解散した。女性陣は左ウィング方向へ戻った。どうやら、女性と男性で離棟されているようだ。おそらく、浴場の位置関係もあるのだろう。 摩耶は部屋に戻ると、煙草に火をつけ、メールのチェックを行った。期待はしていなかったが、ディスプレイが圏外表示になっている。テラスに出て、外の景色を一望する。電磁波さえ遮へいしてしまう、富士の樹海が広がっている。拒絶、という性質が、一つの生命の示唆であるようだ。その先には、霊峰が近くに見える。頂上付近はまだ雪が残っている。 特にやることも無くなったので、化粧ポーチを持って浴場へ出かける事にした。途中で二度、売店で土産の選別作業を行った。ごま団子と薄皮まんじゅうを購入しよう、と頭の中のリストに書き加える。そうしているうちに、2時を大幅に過ぎていた。浴場へ向かうと、先ほどのつい立ても脇へ移動されて、奥へ進めるようになっていた。更衣室は抜け殻のように誰もいない。かごの中からタオルを取り出し、浴衣を脱ぐと、浴場へ入った。浴場内を見て、一瞬戸惑った。浴場内に、川のようなものが作られている。人工物ではあるが、それの意味するところが不明かつ不確定極まりない。川には幅の広い橋がかけられている。その先には、大きな湯船。壁際には、シーサーのような置物の口から、液体が止めどなく流れ出している。橋を渡って、右手の方にスモークガラスの引き戸があった。脇にある掛け札には屋外温泉、と明記されている。摩耶はそちらへ行く事に決めた。 平面に敷き詰められた岩と、白濁の液体。湯気は何所からとも無く漂う霧の様に深い。何かを隠す意図をもって発生した人工物のようだ。打ち湯を済ますと、身体を温泉に浸した。眠ってしまいたくなるほど心地が良い。そういう脱力感が伴う。 ただ、頭のどこかで、桜の事だけが映像として離れる事が無かった。 6 温泉から戻って内線連絡が来るまでの間、摩耶はベッドで寝てしまっていた。時刻は約束の5時を回っている。いそいで支度を済ますと、小走りで右ウィングの雀荘まで向かった。 ドアを開けると、変わった香りが漂った。 「はい、遅刻だよー」碇がグラスを片手に持ち上げてみせる。茶色い液体が揺れていた。「これ、結構利くなあ」 香りの正体は、紹興酒のボトルだった。ボトルは瓢箪の形をしている。現在の状態の碇がその瓢箪を手にすると、香港映画に出てくるクンフー使いのようにも見える。 「さ、面子も揃ったし、やろうやろう」 「こんばんは」摩耶は三人に挨拶をする。それに反応して、男が頭を少し下げた。 「あなたの席はここよ」高峰が微笑む。彼女はいつだって微笑んでいる。彼女の膝の上には猫が寝ていた。 摩耶が席に腰掛けると、扉がノックされて開かれた。蓬莱が紹興酒の瓢箪やグラス、簡単なつまみ類を持ってきた。 「お待たせいたしましたの」 「の、は」と高峰が言いかけて、彼女はもう一度台詞を繰り返した。ごゆっくり、と言い残し部屋を出ようとしたけれど、高峰に一杯誘われて、そのまま部屋にとどまっている。摩耶は年齢的な心配をしたが、高峰が誘ったのだから、もしかしたら自分と同い年くらいなのかもしれない、と想像した。 脚の低いテーブルがあるだけの質素な和室だった。碇は酒類を畳の上に置いている。摩耶も、少し紹興酒を口にした。軽い浮遊感が気持ちよかった。麻雀は4局ほど続いた。碇の部下が小さくリーチを積み重ねるごとに、彼は碇に殴られていた。点数などは誰も計算していなかったので、結局の勝敗はわからない。それに、途中で碇が眠ってしまった。高峰も、その頃になってようやくアルコールに手をつけ始めた。 「蓬莱さん、ここって、まだ新しいんですか?」摩耶は蓬莱にきいた。最初から気になっていた事だった。 「ええと、そうね。まだ、二年も経っていないよ」 「え? それは・・」 本当か、と続けようとしたが、一瞬の躊躇でやめた。 「あれ、高峰さんは、どうして?」 「人それぞれの時間認識感、というところかしらね」 「え?」 「彼女には二年にも満たない期間だった。それだけのことよ」そう言うと、彼女は微笑む。アルコールが多少入っているのにも関わらず、顔色は全く変わっていない。彼女は、両手でグラスを持ち上げて、婚礼の儀式にしかしないような優美な飲み方だった。 「二階のテラスは、もう見たかしら。あれは、秦の時代のお話を描いたものなのよ。2000年も前の事になるのね」 高峰が言っているのは、テラスの天井に摸写されていた抽象画のことだろうか。言われてみれば、何かのワンシーンに見えない事も無いことに気がついた。 「それが、何か?」 「いいえ。それだけのことよ。人は脈絡というものを追求する一方で、知らない間に行う発想の転換、飛躍を見逃しているものなの。鈍感さ。それが、人類をここまで肥大させた原因の一つね」 「それ、ものすごく話飛んでいません?」 「そうね。気にしないでちょうだい。少し酔っているんだわ」 「でも、意外だなあ。高峰さんって、もっと、霊的な因子を信じているんだと思ってた」 「神秘を知るには、まずそれに気付く事が前提となるわ。現実と乖離して知覚するにはね、背理法の要領で現実に沿った出来事だけを排除していく。そうすれば、そこに神秘という物質が残る。現実を見つめる事が、かえって不思議を増長させる要因がここにあるのよ。そう考えてみれば、何も可笑しい事ではないでしょう?」 摩耶は、気付く事、というフレーズが気になった。高峰の言葉が、何かを示唆しているようにも聞き取れる。蓬莱を伺うと、彼女は眠たそうにうつむいていた。 「そろそろ、お開きにしましょうか」 「ええ、そうね。明日の午後には戻りましょう」 高峰と摩耶の二人で碇を支えながら部屋へ戻ると、摩耶も自室へ帰り、そのままベッドの上で意識を無くした。 短い夢を見た。 桜の花弁と、天井の壁画。 それらの映像が、残像のように、記憶に焼き付いている。 内容は何だっただろう。もう、思い出す事は出来ない。 もしかしたら自分は、夢の中で、短い現実を見ているのかもしれない。 どうすれば気付く事が出来るのだろう。 せめて、その答えは、常に優しいものであって欲しい。 残酷な結果を予測できても、その可能性を捨てきれる。それが、人の武器である。その鈍感さが、人を育てた。生かした。そうやってこれからも生きて行くのだろう。 しかしそこには、優しさがある。 それだけが、人の望みであると言える。 高峰の微笑のようだ、と摩耶は、夢の底で思考した。 □■■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■■■■■□ ■ 登場人物(この物語に登場した人物の一覧) ■ □■■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■■■■■□ 【整理番号 / PC名 / 性別 / 年齢 / 職業】 >【1979/葛生 摩耶/女性/20歳/泡姫】 |
|
|
|
||
|
|
||
|
|
【個別ノベル】 【1979/葛生 摩耶】 |
|
|
|
||
|
|