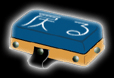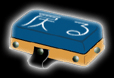●「学園祭」 オープニング
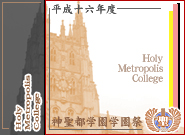
『この夏!楽しく過ごした貴方!
その記念写真に何か妙なモノが写っていると感じた事はありませんか!?』
校内の掲示板内に、数日前からそんな書き出しの紙が張り出されている。学園祭の
イベントに申請したもののひとつで、ちゃんと張り出すブースまで確保しているらし
い。コンテストをやる、というのは8月頭にはもう掲示板に書かれていたのだが、き
ちんとしたポスターになったのは学園祭の準備で学校中が色めきたってからだった。
『そこで、夏の最後の思い出として心霊写真コンテストを行います。我が怪奇探偵ク
ラブブースの心霊写真コーナーに張り出して審査を行い、優勝者には記念品も差し上
げます。尚、戴いた写真は後日全て鑑定の上必要な場合はお焚き上げも致しますので
ご安心ください』
…そこには、どこかの風景写真らしい…ただ、マジックで丸く囲いがされている、
荒くコピーした画像も一緒にプリントされていた。
『審査員は怪奇探偵クラブ代表から私SHIZKUと影沼ヒミコちゃん、怪奇モノに
造詣の深い一般生徒の草間武彦君、教師代表として響カスミ先生、そして特別ゲスト
としてなんと「あの」生徒会長も参加します!当日参加も大歓迎ですのでどしどし応
募して下さいね♪』
そして紙の最後にはよーく見ないと分からないくらいの小さな文字で、『申し訳な
いですが、想定外の事が起こった場合の責任は取りかねます』と、記されていた。
「結構集まったわねー。思ってたよりも大収穫♪」
「大丈夫…だよね?こんなにいっぱいあったら何か起こったりしない?」
そのポスターの前に立つ2人の少女。1人は嬉しそうに手提げの中にぎっしりと詰
まった封筒を覗き込み、影沼ヒミコは心配そうにその中身を見つめている。
「――なあ」
そんな2人に、だるそうな声がかかったのはそんな時。
「あ、武彦君。当日宜しくね、審査」
「…俺そんな約束してたっけ?」
「したじゃないの何言ってるの。ほら、この間学園祭でも宜しくねって」
「学園祭『でも』?俺が以前お前に何か協力した事あったか?」
「あったわよ。ほら、えーと。…とにかくあったのよ。だから今回もお願いしたのよ
?」
そしたら頷いてくれたじゃないの、とSHIZUKUが武彦を咎めるような目付き
をし。
「あーもう分かったよ。見るだけだぞ、見るだけ。…で…何で怪奇モノに造詣が深い
ことになってるんだ?」
その言葉にくすくす笑うSHIZUKUとヒミコ。
「やだ、何言ってるの。武彦君の通り名じゃない…草間君が歩くと怪奇に当たるっ
て」
「犬よりタチ悪いじゃないかよ」
そんなに怪奇な話に首を突っ込んだ覚えはないんだがな…と、そんな事を呟きなが
らも。SHIZUKUの断言した様子に口も挟めず、肩をひょいっと竦め、トレード
マークのシガレットチョコを口の端に咥えて飄然とその場を去って行った。
「忘れないでよー?当日、怪奇ブースに集合なんだからね?」
「へいへーい」
後ろを振り返らずに手をゆるく上げた武彦は、SHIZUKU達は気付かなかった
が…どこか険しい表情になっていた。その理由は、彼自身にも分かっていなかったの
だろうけれど。
*****
――頭が…締め付けられるようで。
その間は、自分が何を考えているのか分からなくなる。
否…
おぼえている
なにもかも
それこそが、自分の本性なのだと告げるのは、
ボクの中の――ボク自身。
*****
「…まだ、気付かないのか?」
「……ちかよらない、で…」
鬱蒼と茂る、学園内の林に…その中の一本の木にもたれかかる女生徒へ、目の前に
立った人物が静かに語りかけていた。
「仏心を出してみればこの有様だ。ほんのひと月前には、矛盾と秩序に満ちた世界が
それなりのバランスを取って存在していたものを。…今日に至るまで、きみは一体何
人もの生徒を『殺した』のかね」
「…う…く、ボ、ボク…ボクは…」
「今は苦しいだろうが抑えていられる。だがそれも…あと、20日足らずだ。それ以
上はきみ自身がもたないだろう」
「―――っ!」
ばっ、と顔を上げた女生徒…月神詠子が、噛み付きそうな目でその男、繭神陽一郎
を睨みつける。
「キミは、勝手にやって来たんだ。仲間まで引き連れて。――ボクを散々監視して、
楽しかっただろうね」
「なら」
すぅ、と陽一郎の目が細くなる。
「なら何故、わたしに――この『役』を与えたのだ?」
きみが拒絶しさえすれば。
わたしは歓迎されぬ者として、無理やり入り込む他無かった筈。
「―――」
先程までの歪んだ苦しそうな顔は、今の詠子の顔には無い。その代わり…一瞬だけ
浮かべたのは、泣き顔とも笑い顔とも付かないもの。
きゅっ、と唇を噛んだ詠子は何か言いかけ、そしてゆるりと首を振るとまた艶やか
な陶器人形のような表情になり、
「まだ大丈夫。キミの手を借りるまでも無いよ」
「そうか――」
先程の具合悪そうな様子は微塵も無く、寄りかかっていた木からつと身体を起こし
て陽一郎とすれ違う。
後に残るは――ずたずたに切り裂かれた木と、足元に散らばる枝葉。
「……」
つぅ…と、木の幹に生々しく残る爪痕に指を走らせる。その指に付着した樹液は、
まるで誰かの――『彼女』の流した血のようで。
「…っ」
不意に、ちくりとした痛みに気付けば、ささくれ立った木の皮で指先を切ったよう
で、見ればそこからぷくりと赤い血が浮かび上がってきた。
そんな痛みさえ、現実にしか思えないのに。
「―――――」
不意に湧き上がった嫌悪感は何の為か。
再び、眠らせる?眠らせなければ成らない?
「所詮は…墓守だ」
がつ、と普段冷静な彼に似合わず幹へと叩き付けた拳。振り上げた理由さえ分から
ぬままに。
――やがて、与えられた役割を…残された時間を演じ抜くために1人の男がその場
から去った後。
いつの間にか抉られていた傷を再生した木々が、何事もなかったかのように静かに
立ち並んでいた。
|
|