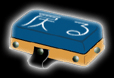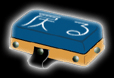●「学園祭」 オープニング
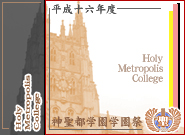
神聖都学園の校門の近く……そこにはあまり目立たない小さな白いテントがぽつんと建っていた。その下で質素な長机と折りたたみ椅子を並べて座っている男女がいる。彼らは学園祭が始まる直前までそこである種の人間を待つつもりでいた。自分たちが企画した学園祭のステージを彩る役者たちを、ただ当てもなくじっと。
彼らは学園内弱小サークルのひとつである『演芸部』の部長と副部長だった。今までメジャーな文化部に押し潰されそうになりながらも、なんとか細々と活動を維持してきた。しかし今年は違う。左に座っている男が部長になってからは、副部長の女子を含む部員たちとともに懸命なアピールし始めた。その結果、知名度だけはメジャーサークルに負けないというおかしな地位を手に入れた。だが部員は特に増えていないし、何かの大会で賞を取ったわけでもない。部員は三味線に興じたり、浪曲をやったりといつもと変わらぬ活動を根気よく続けているという状態だった。
そんな時、またアグレッシブな部長が動いた。学園祭で自分たちが体育館のステージを使って活動の成果を発表するのだと部員の前で高らかに宣言したのだ。すでに使用許可を取ったらしく、その手には生徒会が承認印が押された紙を持っていた。無駄に行動力のある部長にこれまでいくらかの理解を示していた部員たちだったが、さすがに今回の暴挙には閉口してしまう。次の瞬間、彼らが口を開けば「無謀です」「無理です」「勝負しすぎ」ですと不平不満をあらわにした。しかし部長はそんな彼らの不安を理解していたのか、こんなことを言って聞かせる。
『大丈夫だ。今回はわれわれ演芸部の技術向上のために、学園に眠る芸人や一流のプロフェッショナル、そして最強の素人とともに舞台を彩ることになっている。観客が君たちを鼻で笑っても、飛び入りの人間に芸で負けても一切構わない。この舞台が人生最後のものになるのではないのだからな。たとえ演芸部をやめたとしても、この経験はいつまでも君を人間として、そしてひとりの芸人として活かされることは間違いない。これはいい経験になると思って欲しいんだ』
今まで騒いでいた部員たちもこの言葉ですっかりおとなしくなった。そして部長の熱い言葉に動かされた。その結果、彼らは懸命に出し物の練習をしている。自分たちのサークルの名を冠した舞台を汚さないようがんばっているのだった。その間、部長と副部長は練習の合間を縫って外で飛び入り参加の人間の受付をしている……というわけだ。
ちゃんとチラシはばら撒いた。ウェブ上での宣伝も怠らない。そして口コミも利用した。あまり有名でない芸能オフィスや音楽事務所にもそれとなく噂を流してある。準備は万端だ。後は参加者を待つばかり……しかし副部長はどうしても腑に落ちない部分があった。ギャラも出ない仕事を引き受けるプロなどいるのかということだ。彼女は自信満々の笑みを浮かべる部長に問い質した。
「あのぉ、部長?」
「何かな」
「その……いくら神聖都が有名だからって、プロの人がノーギャラでこんな舞台に立つとは思えないんですけど……」
「誰がいつノーギャラだって言った?」
「へ……って、ああっ! なんですか、その札束は!!」
まさかの展開に副部長はあ然とする。目の前に開かれた一万円の束は扇子のように広がり、その数は恐ろしいものだった。目の前に用意されたギャラを見て大いに驚く彼女を見ながら、常に冷静に振る舞う部長。
「これで頬でも叩いてやろうか」
「……いくらあなたでもそんなことしたら殺しますよ?」
「今までの活動費の繰り越しで相当な金額がプールされてたらしい。もちろん違反ではない。ちゃんとした金だ。ただ、今までの部長がこれのありかにたどり着けなかっただけらしい。俺は伝説の古文書を頼りにそれを……」
「どこまで本当のことかはわかりませんが、とにかくギャラは出るんですね?」
「飛び入り参加の生徒の薄謝から、果ては事務所へのギャラまで行けるぞ」
用意された札束を見ながら副部長は確信する。なんとかステージを盛り上げることはできそうだと。いや、必ず盛り上げる。成功させてみせる。そのためには部員たちのためにもゲストを呼ばなければならない。それに心血を注ごうと誓うふたりだった。はたして情報を聞きつけて飛び入り参加してくれる人間はいるのだろうか……?!
●ライターより
皆さんこんにちわ、市川 智彦です。
幻影学園奇譚ダブルノベル、今回は学園祭ということで市川らしくギャグの匂いのするオープニングで攻めてみました。まったく本編の真相とは関係ない部分を走っています。だって学園祭といえばお祭りですよ。そんな真剣なネタ、僕ちゃんできな〜い。
……おほん。
さて今回は神聖都学園に存在する弱小サークル『演芸部』のステージに参加してくれる皆さんを募集します。何も難しいエンタメ技能が必要なわけではありません。別に部長や副部長による審査があるわけでもありませんので。カスタネットを叩きながら歌うんでも全然構わないんです(笑)。とにかく一芸を思いついたなら誰でも参加できるのです。どんなにネタが小さくても、皆さん同じくらいの大きさで扱いますのでどうぞご安心下さい。
なお個別ノベルはリハーサルや控え室での出来事を描写したいと思っています。プレイングの端にステージでの行動以外のものもぜひ書いて下さいね。もしかしたら参加者さん同士で話を絡めるかもしれません。その辺はお楽しみにと言うことで(笑)。
幻影学園奇譚に登録されている皆さんもそうでない皆さんもみんなで楽しめる企画にしました。本当に小さなネタからで構いませんので、ぜひ楽しんで下さい!
|
|