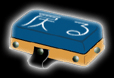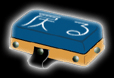●「学園祭」 オープニング
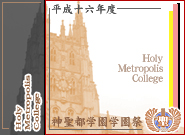
『よくもまぁ……そのような酔狂なイベントを考えたな』
「だって、“姫”の願いに少しでも協力したいですし」
『“姫”、か。その表現には些か引っかかる点を感じ得ないのだが、敢えて問うのは避けておこう』
「助かります。君の尋問は精神的に参る点が多いですからね」
『秩序を乱すな。――我に言えるのはそれだけだ』
一方的に切られた携帯電話を懐に仕舞うと、少年は乗っていた屋上のフェンスから軽く落下した。地上に膝を曲げて落下を和らげるも、勢い余って前方に倒れ込む。
「やはり此処でも体術面の向上は見込めません、か」
苦笑じみて立ち上がり、制服に付いた土を叩き落とす。
「さて、“騎士”はどこまで愉しませてくれるか。――本当に愉しみだ」
文化祭当日。
生徒用に配られた文化祭パンフレットには、一枚のチラシが挟まっていた。
『“要石の欠片”収集イベント』
生徒会発行印は押してあるものの、「パンフレットには書かれていない」アングラ的なイベントに、その日生徒達の風聞は密かに広がっていた。
「これって実は生徒会非公認のゲリライベントなんだってさ」
ふと視線を外せば、やっきになってチラシを回収に掛かっている風紀委員、生徒会役員達がいる。手には回収した数枚の紙をその場で燃やしているほどだ。
……それほどこれってやばいイベントなのか?
何人かは思いその場で隠そうとしたが、殆どが無駄に終わった。
「君、違法チラシを提出しなさい」
生徒会長、繭神陽一郎の声が展示物で一杯の教室内に響く。
「持っている人間は厳重に処罰する。文化祭自体参加出来ないものだと思え」
その異常な姿に興味を抱くには、充分すぎるものだった。
『“要石の欠片”収集イベント』
日時 :九月十三日〜十七日
詳細 :0×0−××××−××××の自動応答に指定された場所にて詳細を説明します。
景品 :真実
主催者:“騎士”に代わりて“姫”の望みを果たし者
●ライターより
【イベントについて】
初めまして或いは今日和、千秋志庵と申します。
今回のイベントは、まさに幻影学園の核とも言える“要石の欠片(グランドオープニングで繭神が探し、草間が拾った石)”を収集していただきます。収集最中には繭神を含めた風紀委員、生徒会役員達の邪魔が入ります。こちらが抵抗する場合は容赦なく“力”を使ってくると思われるので、対策を考える必要があります。
・純粋にイベント参加者
・風紀、生徒会のスパイとしてイベントに参加
・主催者の協力者
以上の中から選択してください。
収集と同時に他の学園祭イベントを愉しむことが出来ますので、是非こちらもお愉しみください。
このイベントの発案者である人間は、“騎士”こと繭神から“姫”こと月神を一時的に護ろうとしています。その意図は不明ですが、少なからず彼らの世界の一端を知り得ているものだと考えられます。
真実まで辿り着けるよう、主催者と共に願っております。
|
|